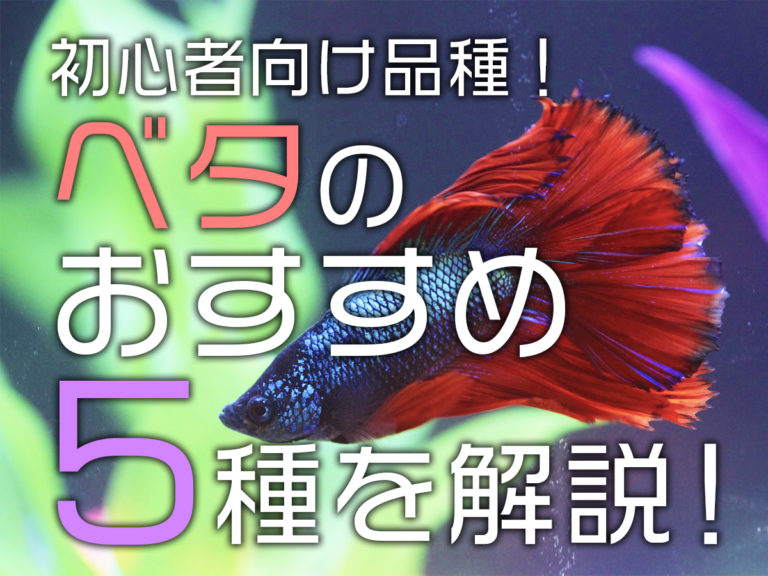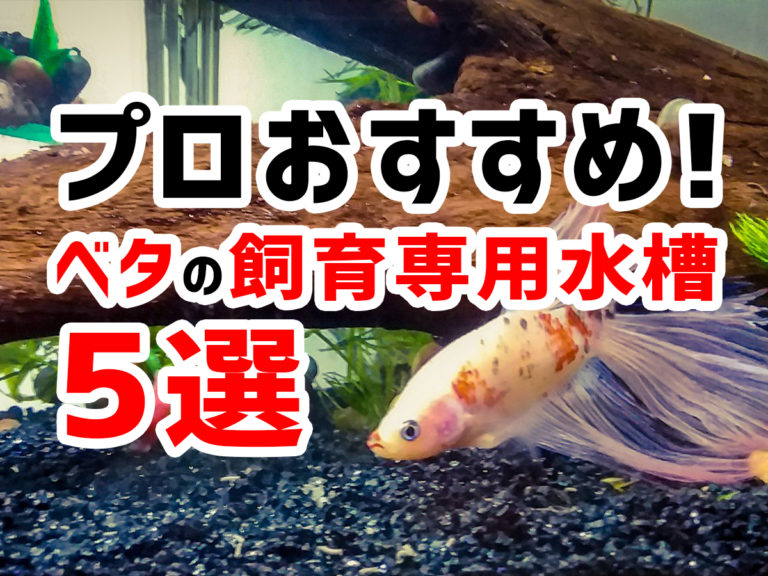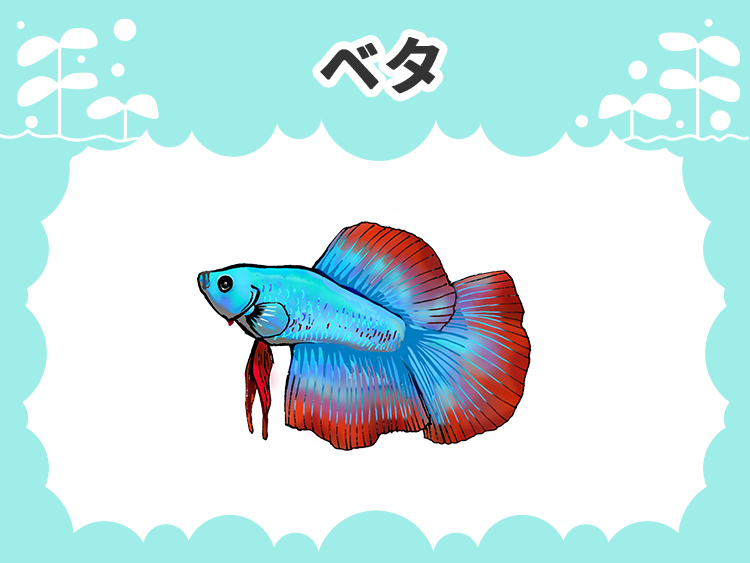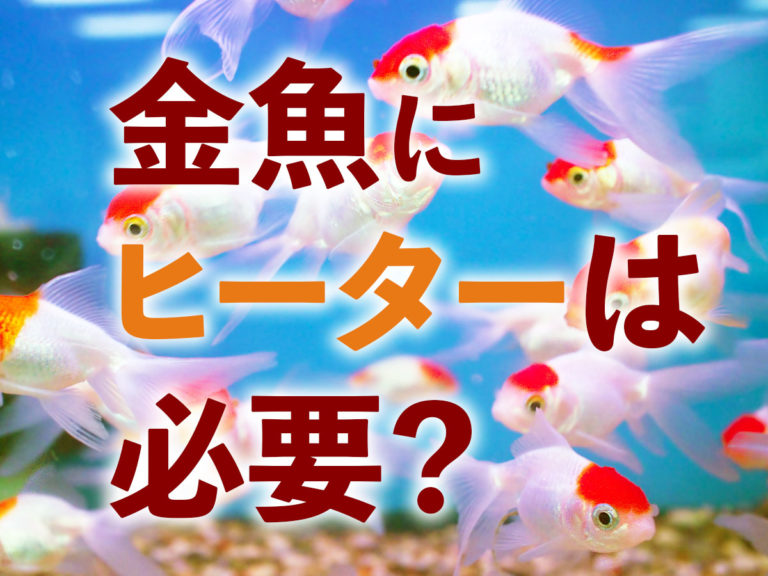ベタの体色がくすんだ!原因と色揚げの方法!鮮やかな体色を保つには!
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
ベタは飼い込むにつれ、体色に劇的な変化が現れることもあります。
成長期のベタは、模様がどんどん変わっていき、その様子を楽しめるのもベタ飼育の醍醐味です。
しかし、ときには体色がくすんでくることもあります。
ベタは老齢になるほど体色がくすむ傾向にありますが、下記のような条件で、若いベタがくすんでしまうことも起こり得ます。
- 水質が合わない
- 栄養不足
- 水温が低い
- 水流が強い など
ベタの体色を鮮やかに改善するには、原因を解決しつつ『フレアリング』を行うことが効果的です。
今回はベタの体色がくすむ原因と、鮮やかな色を保つコツについてお話ししていきます。
目次
ベタの体色がくすむ理由

老齢に差し掛かると、体色が落ち着いてくるベタを見ることがあります。実際、私も過去に飼育していたベタは飼育年数が長くなると、色がくすんでくることが多かったです。
しかし若いベタでも体色が鈍くなってくることがあります。
水質があっていない
ベタの体色がくすんでくる理由には、老齢というだけでなく、ストレスなどさまざまな説があります。
しかし若いベタの体色がくすむ理由は、「水質があっていなくて、ストレスを感じている」ことが多いのです。
意見が分かれるところなのですが、一般的にはベタが得意とする水質は弱酸性といわれています。
しかし鮮やかな体色を出すために、中性~弱アルカリ性傾向の水質で育成を行うことがあります。
実際、弱アルカリ傾向の中性でも飼育可能で、飼育水に少し塩を入れると元気が出るという飼い主もいるほどです。
とはいえ、個体によって好む水質が異なりますし、弱酸性環境に落ち着いて長いベタの水質をいきなり弱アルカリ性傾向に変えてしまうのは良くありません。
ただ、先述したようにベタは成長や年齢で体色が変化することも珍しくないので、その点も確認して水質調整を行いましょう。
ベタに合う水質など基本的な飼育方法については、こちらのコラムをご覧ください。
栄養不足
水質の見直しとともに、高栄養・高たんぱくな餌を与えることで体力をつけると、次第に色のくすみが改善していきます。
栄養不足の解消や色揚げなどを考えるのであれば、まずは実績と人気のある餌がおすすめです。
ベタは意外にもグルメな魚です。同じ餌であっても、あるベタは飛びつき、別のベタは見向きもしないことがあります。
さまざまなベタ用の餌が流通していますが、しっかりと食べてもらうことが基本です。
そのため実績が多い=食いついたベタが多い餌が推奨されるというわけです。
個体によって好みが違いますから、合わない場合は潔く他の餌を試すのが良いです。
ベタの餌については、こちらのコラムもご参照ください。
また、体調不良で体力が落ちても、体色は薄くなります。
病気についてはこちらのコラムをご覧ください。
水温が低い
ベタの原産地は東南アジアで、日本と比べると温かい地域です。
飼育環境でもやや高水温(25~27度ほど)の環境を好みます。水温が下がるとベタの活性も下がり、体色がくすむ原因になります。
購入時より体色が褪せてきたな…と感じたら、水温を27度程度に調節すると色揚げしやすいです。
ベタの飼育を開始して、保温対策を行っていない場合は、水量に適合した水槽用ヒーターを設置しましょう。
温度を一定に保つことで、発色も鮮やかになっていきます。
ここで注意なのですが、水槽用ヒーターは丸みのあるボトルには固定できません。
ですので、ベタ飼育には四角い形状のガラス水槽がおすすめです。
ベタに向いている水槽用ヒーターについてはこちらのコラムをご覧ください。
水流が強い
ベタは大きなヒレが特徴ですが、そのために水流が苦手です。
ベタはもともと、水流の弱い場所や、水流がなく水溜まりのようになっている場所に生息している魚です。
なので、ろ過フィルターを使用しない飼育が基本とされています。
ろ過フィルターの水流が強すぎると、体力を消耗し、そのことがストレスになってしまい、体色がくすむ原因にもなります。
とはいえ、ろ過フィルターを使用して飼育する方もいます。
無ろ過飼育とろ過飼育、どちらかが不正解ということはありません。
フィルターを使用する場合は、パワーがごく弱いものを採用し、できるなら吐出口を壁側に向け、水流を調節してあげましょう。
外部フィルターやスポンジフィルターなら、吐出口の向きを変えることができます。
今まで強い水流だったものを急激に弱めてしまうと、油膜ができることがありますが、水質が安定してくれば消えていきます。
もし油膜ができてしまったら、まずは水換えを行いましょう。
フレアリングで鮮やかな体色になる!

ベタのフレアリングは、ヒレの癒着を防ぐ効果が有名ですが、色揚げにも役立ちます。
ベタの体が活性化すると体色が戻りやすい
フレアリングは人間に例えると、ジムなどで体を鍛えるのと同じようなものです。
そのためベタの体液(人間で例えるなら血液)が体の隅々までしっかりと流れます。その結果、体内で必要な栄養や酸素が十分供給されるので、体色がくすむのを防ぎ、鮮やかさを取り戻しやすくなります。
体色がくすんでいるベタが、フレアリング後に鮮やかになった?と感じられたら、効果が出てきていると考えて良いでしょう。
やりすぎは逆効果!
ベタに体力をつけ、活力UPもできるフレアリングですが、やりすぎは禁物です。
フレアリングをやらせ過ぎると、ベタは激しく体力を消耗するだけでなく、大きなストレスを感じてしまいます。
広い水槽での飼育がおすすめ
ベタは小さな容器で飼育できると言われていますが、水質維持が難しいですし、やはり元気にのびのびと育てるのであれば、水槽での飼育がおすすめです。
水槽飼育でのメリットや、小さな飼育容器で飼育するメリットについては次のようなものがあります。
水質・水温を保ちやすい
アクアリウムメーカー各社から、ベタ専用の小型水槽用ヒーターが発売されていますが、それらは基本的に四角い水槽容器での使用を前提に製造されています。
ボトル容器は大きく見えても水量が1~2Lほどしか入らないなど、そもそも魚を飼育するには規格が小さいものがほとんどです。
水量に余裕があるほど、水温・水質維持が楽になります。
アクアリウム初心者やベタ飼育初心者でも、水質の維持がしやすく健康に育てやすいです。
ベタも広い場所でゆったりと過ごせるため、発色が豊かになり良い状態を維持できます。
10L以下の飼育容器は観賞用に適している

とはいえ、10L以下の飼育容器でも、飼育することは可能です。しかしどちらかというと、鑑賞性を重視しているもの、と割り切ったほうが良いでしょう。
適切に水換えなどメンテナンスを行い、充分な栄養を与えてフレアリングなどを適切におこなうことができていれば、色がくすむことなく綺麗な体色が出てきます。
小さな容器だと水換えやゴミ取りの頻度が増えてしまうため、慣れない場合は、大きめの水槽で飼育することをおすすめします。
おすすめのベタ飼育水槽はこちらのコラムでご紹介しています。
まとめ:ベタの体色がくすんだ!原因と色揚げの方法!鮮やかな体色を保つには!

アクアショップなどでひとめぼれしたベタの、体色がくすんでしまったら「何か健康に問題があるのかな?」と不安になることもあります。
体色がくすむ原因のほとんどは体力低下とストレスです。
ご紹介したポイントを振り返ってみて、水温や餌を変えてみるなどの、色揚げ方法を試してみてください。
ベタは小さな容器でも飼育が可能な魚ですが、できれば14Lくらい(規格水槽で30cmサイズ程度)の飼育容器を推奨しています。
飼育しているベタと出会ったのも、きっと何かのご縁です。
大切に飼育してあげてください。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。


 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談フォーム
お悩み相談フォーム