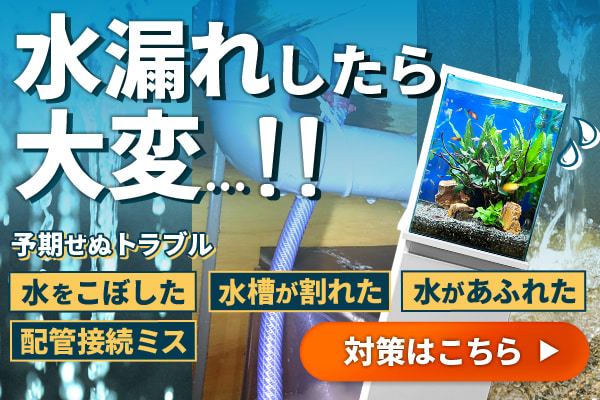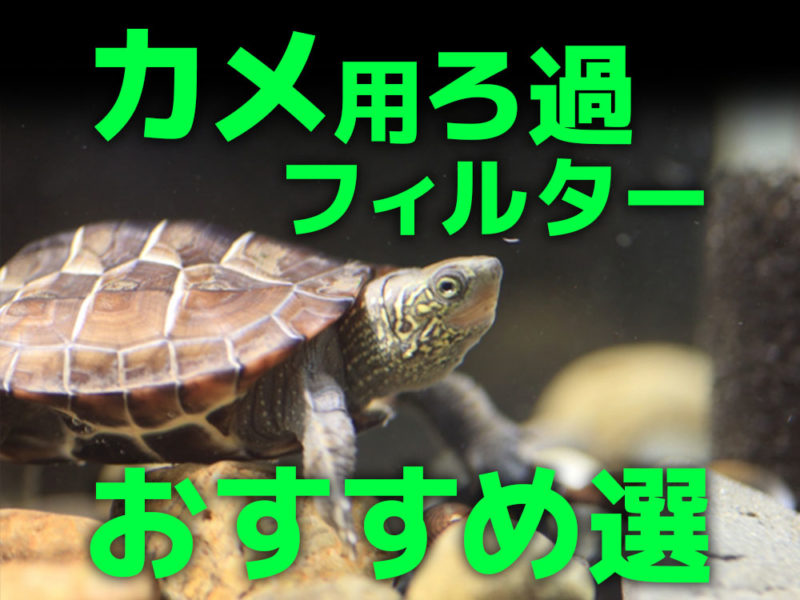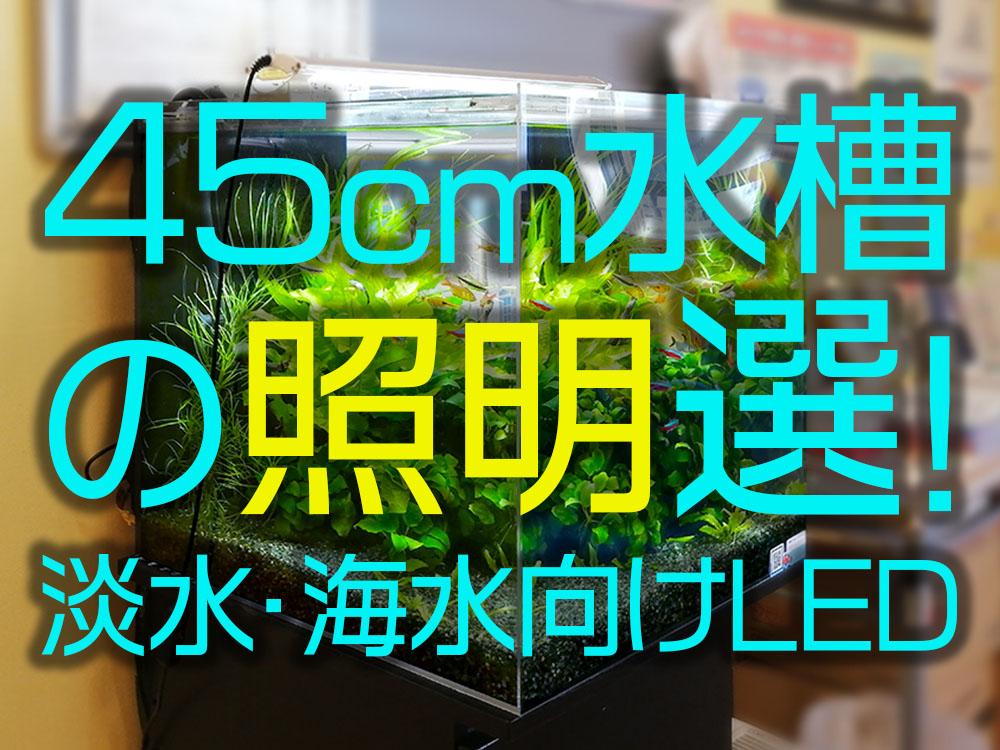水棲カメの冬飼育!冬眠させる・させない場合の飼育ポイントとは

投稿日:2024.12.17|
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
自宅で飼育ができるクサガメやイシガメなどの水棲カメは、丈夫で比較的飼育がしやすいことから爬虫類飼育の初心者からも人気があります。
そんな水棲カメは、野生では冬眠をして冬を越すのが一般的ですが、飼育しているカメはどのように越冬をするのが良いのでしょうか。
野生下と同様に冬眠をさせるのか、それとも保温をして暖かい時期と同じように飼育を続けるのか…特に初めて冬を迎えるときは管理の仕方や越冬の方法に迷ってしまうことも多いです。
そこで今回のコラムでは、水棲カメの冬の飼育について解説します。
冬眠させる場合、させない場合それぞれの管理ポイントをご紹介しますので、ぜひご一読ください。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとに水棲カメの越冬方法と冬眠の有無についてを解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
自宅でも飼育できる爬虫類として人気の水棲カメの冬越しは、冬眠させるか、冬眠させないかを飼育スタイルに合わせて判断する必要があります。
どちらの場合も適切に管理することで健康に春を迎えられますので、状況に合わせた飼育ポイントを抑えておきましょう。
ここでは、実務経験から得た知識をもとに、水棲カメの越冬方法と冬眠の有無についてを解説します。
水棲カメを冬眠させる場合の飼育ポイント

気温や水温がしっかり下がる屋外で飼育を続ける場合は、冬眠をさせて冬を越すことになります。
野生ではポピュラーな越冬方法ですが、冬眠はカメの体力を大きく消費させる一大イベント。
中途半端な状態だとダメージを受けてしまうリスクがありますので、しっかり下準備をしてから冬眠をさせてください。
もし、カメの体力や管理方法に不安があるならば、冬の間だけで室内飼育に切り替えて冬眠を回避するのも一つの方法です。
ここでは、水棲カメを冬眠させる場合の飼育ポイントをご紹介します。
水温が18℃を下回ったら餌切りをしよう
水棲カメは15℃を下回ると本格的な冬眠に入ります。
この時体内に未消化の餌があると、眠っている間に腐敗して健康を害する恐れがありますので、冬眠前に餌切りをして胃を空っぽにしておくことがとても重要です。
変温動物の水棲カメは、水温の低下とともに自然に食欲が落ちていくのでそこまで厳密に餌の量を管理する必要はありませんが、目安としては、水温が20℃を切ったあたりから少しずつ餌量を減らしていくのが良いでしょう。
低水温下では消化不良を起こしやすいので、体調の異変には注意してください。
そのままカメの様子を確認しながら、水温が18℃を切ったあたりで絶食に移行します。
また、カメは水中で冬眠することが多いため、水質を安定させておくとスムーズです。特に餌の食べ残しは水質の悪化を招きますので、見つけ次第取り除きましょう。
5℃以下の低水温には注意!
水棲カメが冬眠している間は、水温が5℃以下にならないように注意します。
特に水中が凍結するとカメが命を落としてしまう危険があるため、凍結対策には力を入れましょう。
凍結防止には、飼育容器の下にスタイロフォームを敷くか、プラダンや板などで容器に蓋をしたり、囲いを作ったりする方法が有効です。
また北風が強く当たる場所や直射日光が当たる場所は水温が急変しやすいため、なるべく気温が安定した場所に水槽を移動すると安全性が増します。
水苔や落ち葉で寝床を整えよう
野生のカメは水中に堆積した落ち葉などの下にもぐって冬眠をしますので、飼育容器でも水苔や落ち葉を使って同様の環境を整えてあげるのがおすすめです。
カメが落ち着きやすくなりますし、落ち葉が毛布のような役割を果たして体を保温ができるため、低水温対策としても役立ちます。
落ち葉はアク抜き、水苔は水でしっかりと戻してから飼育容器に投入しましょう。
ただ、このような植物は水中で朽ちてしまうと水質の悪化を引き起こすことがあるため、定期的に状態を確認し、腐ってしまっているようならば新しいものと交換するか取り除くようにしてください。
特に冬眠明けのころになると水温が上がって雑菌が湧きやすくなりますので、注意が必要です。
水棲カメを冬眠させない場合の飼育ポイント

元々室内で飼育している場合や冬眠させるのが不安なときは、水槽用ヒーターなどを使って水温を保つことで、冬眠をさせずに越冬できます。
普段屋外で飼育しているカメを冬の間だけ室内に入れるときは、水温が下がり出す前に早めに移動するのが良いです。
ここでは、水棲カメを冬眠させない場合の飼育ポイントをご紹介します。
保温機材は必ず用意しよう
水温10℃以下までは起きて居られるメダカなどと違い、カメは15℃を下回ると冬眠してしまいます。
外に比べて水温が下がりづらいとはいえ、室内でも無加温で15℃以上を確実にキープするのは難しいため、保温機材を使って水槽全体を暖かく保ちましょう。
陸地部分の保温にはバスキングライトが使いやすいです。カメが日光浴できるバスキングスポットができるのはもちろん、ライトの発熱効果で水槽全体の空気が温まって、カメの活性を高いまま維持できます。
一方水中は水槽用ヒーターを使って加温をしましょう。陸上部分と水中の寒暖差が激しいと水に入らなくなってしまいますので、冬だけでも水槽用ヒーターで水を温めるのが良いです。
しっかりと加温ができていれば餌は普段通りで問題ありませんし、特に冬を意識する必要なく普段通りの飼育スタイルを続けられます。
水温は20度以上に維持する
冬眠をさせずに水棲カメを管理するときは、暖かいときと変わらず水温を20℃以上にキープしましょう。
中途半端に水温が下がってしまうと、消化機能が低下して体調を崩してしまうことがあるため、しっかり活性を保てる水温を維持することが大切です。
熱帯魚用の水槽用ヒーターでもよいですが、水量が少ないときはカメ用の水槽用ヒーターを使用するのが安全です。
餌は水温で調整しよう
水温に応じて餌の量を調整しましょう。
先述した通り、水温20℃以上を維持できていればそこまで食欲が落ちることはありませんが、もし食欲が落ちているようならば無理に食べさせる必要はありません。
あくまでカメの調子に合わせて、食べ残しが無いように餌やりをすることが大切です。
水棲カメを冬眠させる基準

飼育している水棲カメでも、すべての個体が冬眠できるわけではありません。
冬眠はカメに大きな負担を掛ける大変作業であり体力に乏しい個体を無理に冬眠させると、体がもたずに命を落としてしまう可能性が高いです。
屋外で冬眠させるかどうかは、その個体のコンディションをよく見極めて判断するようにしましょう。
ここでは、水棲カメを冬眠させる基準を解説します。
健康的な個体は冬眠させよう

日ごろから屋外で飼育している水棲カメで、以下の条件に当てはまる個体は冬眠が可能です。
- 年齢をクリアしている(2歳以上)
- 病気にかかっていない・外傷がない
- 餌食いが良く、体力を十分蓄えている
先程も触れた通り、若すぎると体力が足りず冬を越せない可能性が高いです。少なくとも2歳を過ぎていて大きく成長している個体を選びましょう。
病気や外傷がないことも重要です。
冬眠時に健康であることは当然として、暖かい季節に体調を崩していて十分にエネルギーを蓄えられなかった可能性のある個体は、冬眠時点で症状が回復していても、冬眠を見送った方がよい場合があります。
その個体の状態をよく確認したうえで越冬方法を決定してください。
このように、冬眠できるかどうかは直前の状態だけでなく、これまでの1年間どの様に飼育ができていたかを総合的に見て判断することが大切です。
飼育容器の設置場所に注意
屋外飼育でも、昼夜で水温変化が激しい場所では冬眠をさせないほうが良いです。
例えば直射日光が当たるような場所は、昼と夜で水温が大きく変化してしまい、カメが冬眠の途中で目覚めてしまうことがあります。水温が低下すればまた眠る可能性はありますが、起きたり寝たりを繰り返すような状況は、通常よりもカメの体力の消耗が激しく危険です。
冬眠をさせるならば、水温の安定しやすい日陰に飼育容器を移すなどの対策をしましょう。
健康不安がある個体は屋内飼育に切り替えよう

繰り返しになりますが、エネルギーを大きく消費する冬眠はカメに大きな負担を掛けます。
少しでも不安がある個体は無理せずに冬の間だけでも屋内飼育に切り替えて越冬させるのが良いです。
- 持病(慢性的な疾患)を持っている、体調を崩している
- 海外の暖かい地域原産の品種
まず、生まれつきの特徴や慢性的な病気を抱えている個体、冬眠時点でや体調不良やケガをしている場合は冬眠を控えましょう。健康な個体に比べて冬眠のリスクがかなり高くなります。
また、一年を通して温暖な地域が原産のフロリダアカハラガメなどの品種は、日本の寒さに適応できないため、無理に冬眠をさせる必要はありません。このような品種は基本的に室内水槽でヒーターを使用して飼育しているかと思いますので、冬の間も同様に保温をしながら飼育を続けましょう。
繁殖をしない個体は冬眠不要
カメを冬眠させる大きな理由の一つが、繁殖がしやすくなることです。
冬眠を経験したカメは翌春以降の繁殖率が上がるため、繁殖ができる立派なカメに育てたいときは冬眠をさせる必要があります。
一方、繁殖を考えていない場合は冬眠をしなくても特に問題ありません。
冬眠は健康面でのメリットがある一方、管理の手間やカメ自身へのリスクが大きいため、マイペースに飼育を楽しむならばヒーターなどで加温をして冬を越すのがおすすめです。
まとめ:水棲カメの冬飼育!冬眠させる・させない場合の飼育ポイントとは

水棲カメの冬の飼育について解説しました。
水棲カメの冬の飼育は、冬眠させるかさせないかで大きく変わります。
いずれにしても、適した飼育管理をしないとカメに悪影響を与えるので注意してください。
屋外で越冬する場合は、基本的に冬眠させることになります。数か月前から計画し、しっかりと餌を与えて健康的に飼育しましょう。水温の低下とともに、徐々に餌の量を減らしていき、直前には絶食させるとスムーズに冬眠状態に移行できます。
一方、室内飼育の場合や体力的に冬眠が危険な個体は冬眠させずに冬を越します。
日光浴をする水棲カメはエアコンで水温、室温を維持するだけでは不十分です。バスキングライトに加え、水槽用ヒーターを使って温度を維持し、活性を保った状態で管理を続けましょう。
春になって暖かくなれば、また活性の高い時期がやってきます。厳しい冬を上手に乗り越えましょう。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。



 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談
お悩み相談