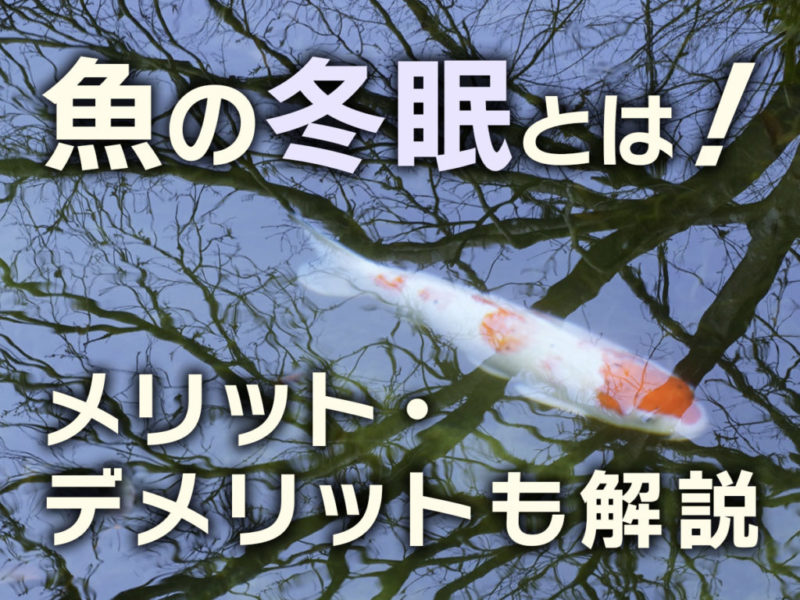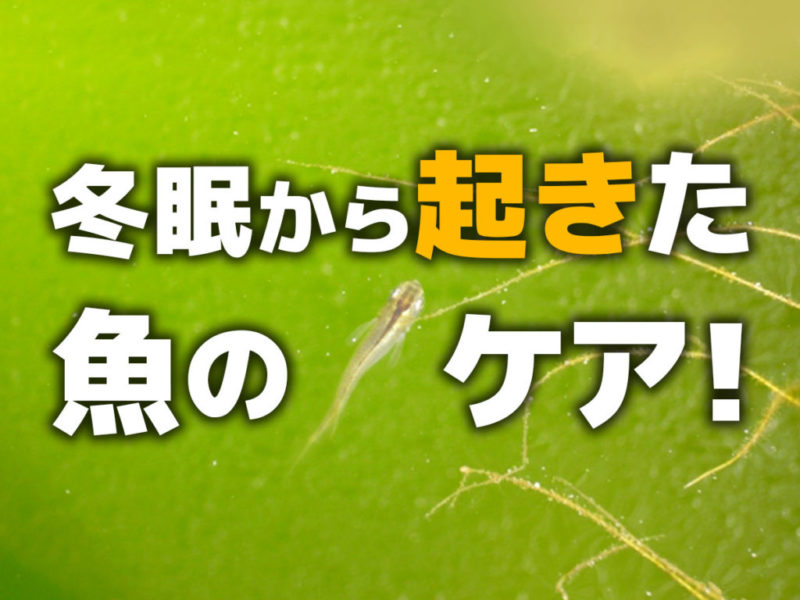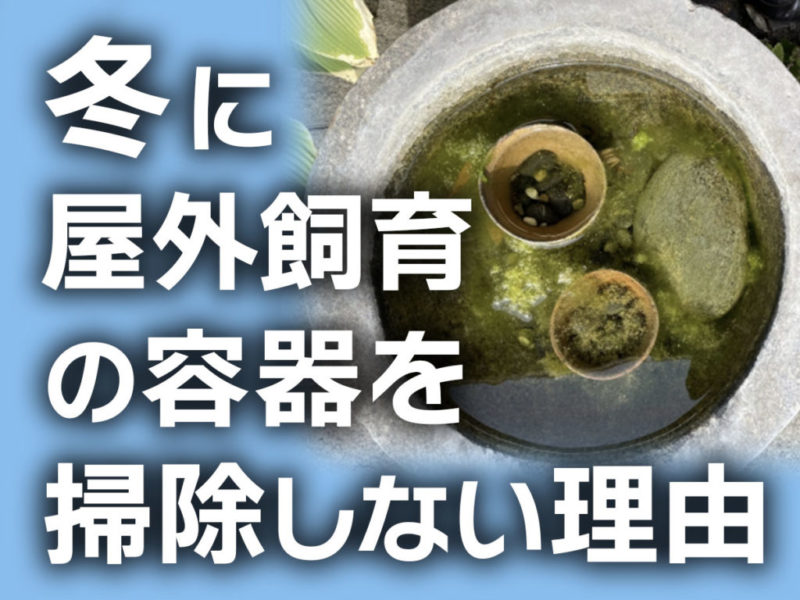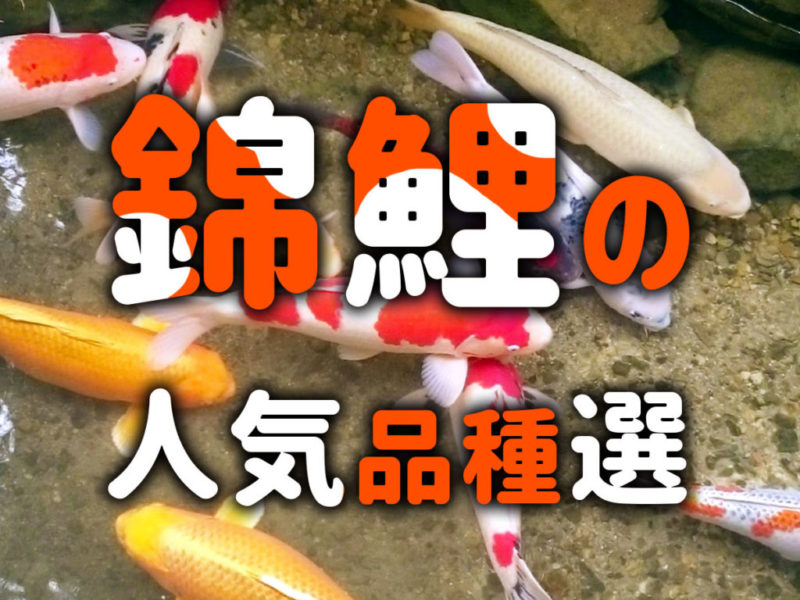錦鯉の冬飼育!冬眠させる・させない飼育方法のポイントを解説します

投稿日:2024.12.12|
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
以前は公園や神社といった公共施設にある池にいる魚というイメージが強かった錦鯉ですが、飼育機材が充実したことで最近は自宅で錦鯉の飼育に挑戦する方が増えています。
そんな個人宅の錦鯉飼育で気になるのが、越冬のさせ方です。
大きな屋外の池では冬眠をして春を待つのが一般的ですが、飼育スペースが限られている自宅の水槽やビオトープでは冬眠をさせることはできるのでしょうか。
また、屋内飼育では水温が下がりきらないことが多いため、そもそも冬眠をさせずに冬を越す方法があるのかも気になるところでしょう。
そこで今回のコラムでは、錦鯉の冬の飼育方法について解説します。
冬眠をさせる場合、させない場合それぞれの管理ポイントをご紹介しますので、参考にしてください。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとに錦鯉の越冬について解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
大きな池にいる錦鯉は冬になると冬眠をして春を待ちますが、自宅で飼育している場合は室内飼育か屋外飼育下によって管理方法が変わります。
水温が下がりきらない環境では無理に冬眠をさせなくても冬を越すことができますので、飼育環境に合わせた管理を実践して冬を乗り越えましょう。
ここでは、実務経験から得た知識をもとに、錦鯉の越冬について解説します。
錦鯉を冬眠させる場合の飼育ポイント

錦鯉を屋外で越冬させる場合は、冬眠をさせるのが基本です。
水温が8℃を下回るようになると動きがかなり鈍くなってじっとしているようになるため、それまでに冬眠に向けた準備を整えましょう。
また、冬眠中は水の凍結や眠り病に注意します。
ここでは、錦鯉を冬眠させる場合の飼育ポイントをご紹介します。
低水温での給餌方法
錦鯉は、昼間の水温が13℃を下回るようになるとかなり活性が落ちてきます。
低水温で動きが鈍くなってきたら、『キョーリン ひかり胚芽』などの消化しやすい低水温用の餌に切り替えましょう。
この時期に無理に餌を与えると消化不良を起こしてしまいますので、与え方には十分注意してください。
餌の量は普段の1/3程度を目安に少なめを心がけます。一日のうちでも比較的暖かい時間帯を選んで与えると、より安全です。
水温の低下に合わせて少しずつ餌の量や回数を減らしていき、水温が10℃を下回るようになったら餌やりを中止します。
また、安全に冬眠を迎えるには、それまでに十分な体力を付けさせておくことが大切です。
水温が下がり出してしまうと餌量を減らさなければなりませんので、大体11月頃までにはたくさん餌を食べさせて栄養を蓄えておきましょう。
極度の低水温・凍結に注意
錦鯉の冬眠中に注意したいのが、水温が5℃を下回るほどの低水温と凍結です。
錦鯉は水温0℃の環境でも生きることができるほど丈夫な魚ですが、あまりに低水温な環境が続くと冬眠中でもどんどん体力を消耗してしまいます。
また水中まで凍結するほど水温が下がってしまうと、さすがに生きていくことができないため、できる限りの保温や凍結防止の対策を行いましょう。
凍結対策として効果的なのが、循環ポンプや水槽用ブロアー(エアレーション)の活用です。
これらの機材で弱めの水流を作ることで凍結を防止できます。水換えにも凍結防止の効果が期待できますが、水換えは冬眠中の錦鯉に負担を掛けてしまう可能性があるため、水温が6℃を下回るようになったら控えるようにしてください。
保温には、スタイロフォームや板を使用します。錦鯉を飼育する容器の上に蓋のように乗せておくと、外気温の影響による水温の低下を緩やかにできるほか、雪が降る地域では雪の混入防止にも効果的です。
ただし、飼育容器の上部を覆ってしまうと水中が酸欠になりやすくなりますので、エアレーションを同時に行うことをおすすめします。
眠り病に注意!
水温が6℃を下回る環境では、冬眠中の錦鯉が”眠り病”と呼ばれる病気を発症するリスクが高まります。
眠り病は、当歳魚~二歳魚ぐらいの比較的若くて体力に乏しい個体がかかりやすい病気で、眠っているように水底で転覆・横転してしまいます。
眠り病の原因は明確には解明されていませんが、細菌性の転覆病と似た症状を呈することから、『エルバージュ エース』などの抗菌剤を使った治療が有効です。
また、本格的な冬眠前に塩水浴をすると予防効果があるとも言われています。塩水浴で体調を整えて病気への抵抗力を高めることで、無事に冬眠を乗り切れるというわけです。
冬眠はとても体力を使うもので、特にまだ体が完成していない若魚には過酷な環境となることが予想されます。冬眠させる前に体調管理や環境整備をしっかりと行い、リスクを最小限に抑えましょう。
錦鯉を冬眠させない場合の飼育ポイント

屋内の水槽で飼育している場合や平均気温が高めの地域にお住いの場合など、錦鯉が冬眠するほど水温が下がらないときは、起きたまま越冬をします。
とはいえ、暖かい季節とは管理方法が異なりますので、寒い季節ならではの注意点を確認しましょう。
ここでは、錦鯉を冬眠させずに越冬するときの飼育ポイントをご紹介します。
室内飼育では冬眠させない
室内で飼育している錦鯉は、基本的に冬眠をせずに冬を越します。
室内水槽は無加温でも、冬の水温が12℃を下回るようなことはあまりありませんし、エアコンなどの暖房設備を使っている部屋ならば、さらに水温が高めに維持されやすいからです。
錦鯉は水温12℃程度まではある程度の活性を保っているので、この水温を下回らないようならば無理に冬眠させずに、通常通り飼育を続けてください。
ろ過フィルターや照明などの機材も変える必要はありません。環境を変えるとかえって錦鯉の負担になることがあるため、できるだけ変化を起こさないよう心がけましょう。
水温が下がる場合は餌を控えめにしよう
冬眠をさせない場合は、水温の変化に合わせて餌の種類や量を調整しましょう。
水温を確認し、一日を通して20℃を下回るようになったら餌の量を減らし、消化に良い低水温用の餌に切り替えてます。
餌を与える時間はに日中の暖かい時間を意識すると、消化による負担を軽減できるのでおすすめです。
水温が15℃以下まで下がってきたらさらに給餌量を減らし、12℃を下回るようならば様子を見ながら給餌を中止することも検討してください。
屋外飼育ほどシビアになる必要はありませんが、水槽の設置場所によってはかなり水温が低下することもあるため、冬の間はこまめに水温をチェックしながら体調管理に努めましょう。
昼夜の温度差に注意!
室内管理の水槽でも油断ができないのが昼夜の水温差です。
無加温の水槽では、人が活動している時間帯は水温が保たれていても、暖房を切る就寝のタイミングから夜間や早朝にかけて水温が急低下する危険があります。
一日を通して5℃以上の水温変化が毎日続く環境では錦鯉に大きな負担を掛けてしまい、消化不良やコンディションの低下を引き起こす可能性があるため、冬の間だけでも水槽用ヒーターを設置するなどの対策をしましょう。
水槽用ヒーターの設定温度を15℃にすれば最低限の活性が保てますし、20~23℃前後に設定すれば、冬を気にせず暖かい時期と変わらないスタイルで飼育を続けることもできます。
また冬場は太陽の位置が低く水槽に直接太陽光が当たって水温差を招くこともあるので、状況に合わせてバックスクリーンを貼るなどの対策をするのもおすすめです。
春になったら!冬眠明けしたときの管理

厳しい冬を乗り越えたばかりの錦鯉は、想像以上に体力を消耗した状態です。
適切なケアをして疲れを癒してあげることで、通常の飼育に戻りやすくなります。
ここでは冬眠明けの錦鯉の管理方法をご紹介します。
餌は少量から再開する
外気が暖かくなってきて水温が12℃を超えだすと、錦鯉は冬眠から目覚めます。
目覚めから少しずつ動きが活発になってきたら、餌を再開するタイミングです。
ただし、早く体力を戻してほしいからといきなり大量の餌を与えたり、こってりした餌を与えるのは厳禁。冬眠明け直後の錦鯉はまだ消化能力が低いので、まずは消化に良い餌を少量から始めて、様子を見ながら段階的に餌量を戻していきましょう。
最初は一日一回、通常の餌量の1/4~1/3程度を目安にします。
春先はまだまだ気温が不安定で急に寒さが戻る日も少なくないので、天気や気温、錦鯉の状態を観察しながら慎重に餌の量を調節しましょう。
床直しをして冬の汚れを一掃しよう
錦鯉の調子が上がってきたら、床直しをします。
床直しは冬の間に溜まった汚れやゴミを一掃する作業のことで、生き物が冬眠から明けたタイミングで行うのが一般的です。
冬眠中は水が汚れづらいとはいえ、長期間一切のメンテナンスを絶っていた状態ですし、給餌を再開すると更に水質悪化が加速するため、飼育容器内の沈殿物やろ過槽の汚れをしっかり落として水を換え、清潔な環境を整えましょう。
また、冬眠明けの錦鯉は体力が低下しており、病気にかかりやすいデリケートな時期です。病気を防ぐためにも、水質の維持を心がけてください。
ちなみに、病気を予防する補助的な対策として、寄生虫予防や免疫力アップの効果が期待できる『キョーリン パラクリア』シリーズなどの餌を与えるのも良い方法です。
まとめ:錦鯉の冬飼育!冬眠させる・させない飼育方法のポイントを解説します

錦鯉の冬の飼育方法について解説しました。
錦鯉の越冬方法は、飼育環境によって変わります。
屋外で水温が8℃前後まで下がるときは、冬眠をさせて冬を越すのが一般的です。
冬眠前から餌量を控えていき、動きが鈍くなってきたら春が来るまで刺激しないようにそっと見守りましょう。冬眠中は水温の下がりすぎや凍結に十分注意します。
一方室内飼育や暖かい地域の場合は、冬眠をさせずに起こしたままで越冬するのが良いです。
こちらも餌やりは控えめに、水温に気を付けながら管理をしましょう。昼夜の水温差が激しい場合は水槽用ヒーターを使うと飼育が安定します。
いずれにしても、錦鯉のストレスを減らすことが大切です。水温=活性なので、活性に合わせた給餌や環境作りを意識してみてください。
厳しい冬を乗り越えて、無事に飼育の楽しい春を迎えましょう。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。



 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談
お悩み相談