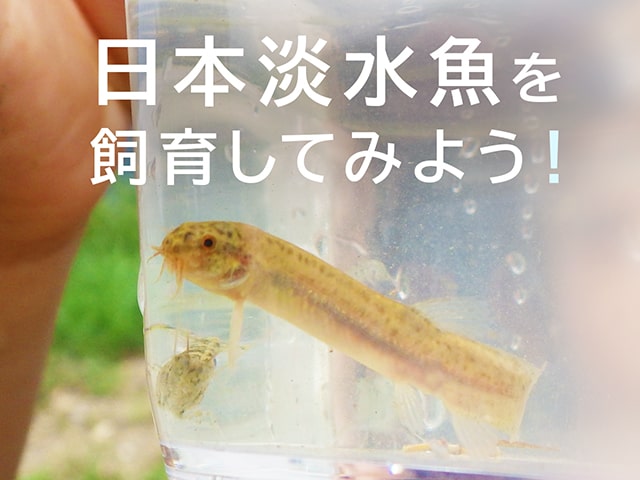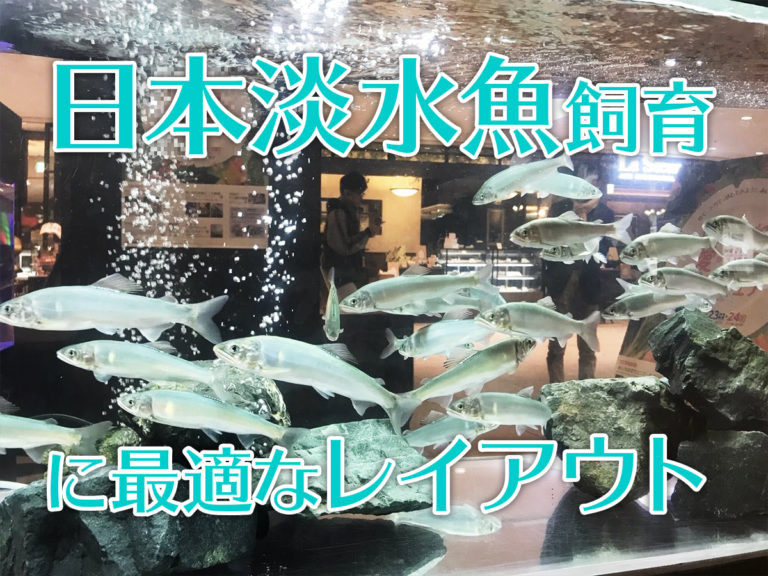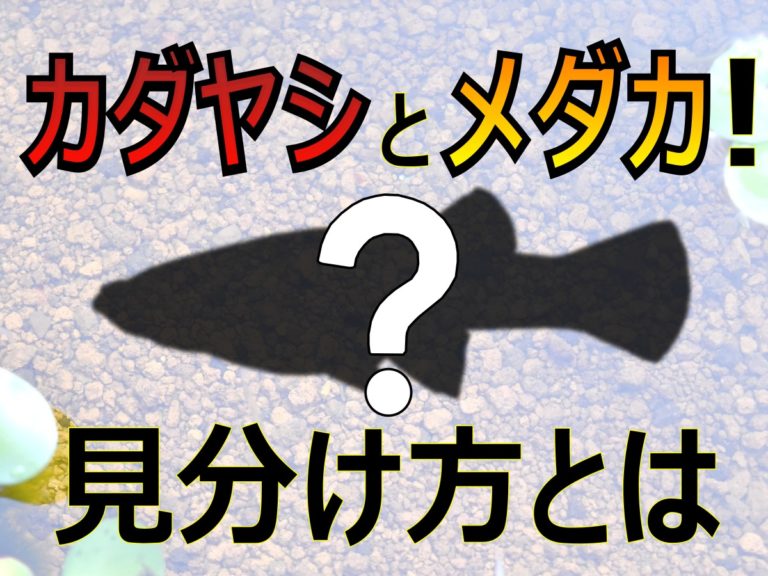国内外来種の魚とは!在来種でも放流禁止な理由と注意したい魚種を紹介

投稿日:2025.03.26|
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
“国内外来種”という言葉をご存じですか?
外来魚というと、日本にはいないはずの外国の魚が放流などで日本定着してしまう話を頭に浮かべるかと思いますが、実はこのような環境問題は外国産の生き物に限った話ではありません。
南北に広い日本は、地域によって生態系が大きく異なります。そのため、同じ国内でも本来の生息域ではない場所に広がった魚たちが、在来の生態系を脅かす“国内外来種”となる可能性が、近年指摘されているのです。
今回のコラムでは、ここ最近問題視されている国内外来種について解説します。
国内外来魚の影響や放流が禁止される理由、注意が必要な魚種などをご紹介しますので、ご一読ください。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとに国内外来種の魚について解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
日本に生息している魚でも、本来の生息域とは異なる場所に広がってしまうと、外来種のように環境に悪影響を与える可能性があります。
アクアリウムで見かける魚たちの中にも国内外来種として懸念を抱かれている魚種がいますので、飼育の際は取扱いに注意しましょう。
ここでは、実務経験から得た知識をもとに、国内外来種の魚について解説します。
国内外来種とは

通常の外来種に比べて、国内外来種の問題はまだまだ認知度が低めです。
そこで、まずは国内外来種とはどんな生き物のことなのか、また国内外来種が抱える問題点について解説します。
地域が異なる在来生物
国内外来種とは、本来その地域には生息していなかったにも関わらず、人間の手で持ち込まれて定着した日本原産の魚のことです。
近年、国内外来種は海外から入ってきた外来種と同様に、生態系を乱す要因として問題視されています。
外来魚と聞くと外国の生き物を思い浮かべる方が多いかと思いますが、日本の魚であっても全国に分布しているわけではないので、本来の生息地以外では”外来魚”として区別されるのです。
国内外来種が問題視される理由

では、なぜ同じ日本国内であるにも関わらず、生き物の生息域が変わってはいけないのでしょうか。
日本に生息している魚であれば、他の場所に放流しても問題ないように感じる方もいるでしょう。
しかし、実際は日本原産であっても生息域が異なる生き物が入ってくることで現地の生態系に影響を及ぼす危険性が指摘されています。
ここでは、国内外来種が問題視されている理由について解説します。
生態系に悪影響がある
国内外来種も外来種と同様に、元々その地域にいた在来魚を捕食したり、餌やすみかを奪ったりして、生態系を崩す可能性があります。
例えば、メダカやモロコなどの小型魚が生息する地域に外から持ち込まれたナマズを放流すると、小型魚がナマズの餌になって個体数の激減に繋がることがあるのです。
また直接捕食される危険が無くても、餌の奪い合いになって在来魚の餌が不足するといったことも起こりえます。
生き物が交雑する
そしてもう一点国内外来種の危険性と指摘されているのが、在来種と交雑して遺伝的撹乱をもたらす危険があることです。
国内外来種は外国産の魚に比べるとかなり近縁なため、地域の在来種と簡単に交雑します。
その結果、各地固有の遺伝子が薄まって、地域への適応形質(寒さへの耐性など)が失われてしまうことも。
このような他種同士の交配による遺伝子の汚染は気遣いないうちに進行して、本来の特徴や種の多様性を失う要因になりかねず、広義的な意味での絶滅を招く可能性も捨てきれません。
失われた遺伝子は二度と取り戻すことができないため、国内外来種を持ち込まないことが大切です。
放流厳禁!国内外来種になりえる魚7種

ここからは、実際に国内外来種になる可能性が示唆されている魚種7選を解説します。
どんな魚でも、別の生息地から連れてきたものを放流すればそれは国内外来種です。
今回は、その中でも特に生態系への影響が大きいと考えられている魚を厳選してご紹介します。
タナゴ
日本原産のタナゴには、 カネヒラ、アカヒレタビラ、シロヒレタビラ、ゼニタナゴ、アブラボテなど複数の種類がおり、それぞれが異なる地域に分布しています。
これらのタナゴが生息域を超えて持ち込まれることで起こるのが、産卵場所の奪い合いです。
タナゴの仲間は二枚貝に産卵する習性があり、近縁種が増えることで産卵場所が不足して繁殖が滞る危険があります。
最近は自然環境の変化により二枚貝の生息数が減っているという話もあるので、そのような地域では在来のタナゴの減少に拍車がかかる可能性も。
また、近縁種ゆえに交雑の危険もかなり高いと考えられるでしょう。
タナゴの一部の品種は絶滅危惧種に指定されているものもあるため、種の保護の観点からも無闇な移動は避けるべきです。
メダカ
メダカの野生種は日本全国の小川に生息するポピュラーな小魚ですが、近年問題になっているのが、鑑賞用に生み出された改良メダカの放流です。
カラフルな改良品種が放流されると、在来のミナミメダカやキタノメダカと容易に交雑して、純粋な在来メダカが激減してしまう恐れがあります。
また、野生に近い黒メダカや野生種のミナミメダカ、キタノメダカであっても、一度人の手に渡ったものを適当に放流するのは厳禁です。
たとえ同種でも地域が違えば遺伝子が異なるため、交雑によって種の多様性が損なわれる要因となります。
フナ
ギンブナ、ニゴロブナ、ゲンゴロウブナなどのフナの仲間は環境適応力が高く、日本国内に放流すると地域を問わず大抵の場所に定着してしまいます。
実際に琉球列島では、フナの移入により生態系が大きく変化して地元の在来魚に影響が出ているという報告がされているようです。
温暖化の影響で暖かい地域の生き物が寒い地域に定着する話はよく聞きますが、その逆も起こりえるという事例の一つでしょう。
またギンブナは魚類だけでなくカエルやサンショウウオなどの水辺の生き物も捕食するため、生態系全体に影響を与える可能性があります。
さらに単為生殖が可能で、一度移入されると爆発的に増殖する恐れがあるなど、国内外来種として厄介な特性を併せ持っている点にも注意が必要です。
モロコ
ホンモロコ、スゴモロコ、タモロコなどのモロコ類は、各地で放流が原因とみられる流出が確認されている魚種です。
例えばホンモロコとスゴモロコは元々は琵琶湖に生息している種類ですが、近年は多摩川で生息が確認されており、本来の生態系への影響が注視されています。
ホンモロコは食用としても人気の養殖が盛んな魚種のため、意図的な放流以外にも養殖場から逃げ出すなどした個体が分布域を広げている可能性が指摘されています。
モツゴ
モツゴとシナイモツゴは、交雑問題が深刻です。
元々は西日本にモツゴ、東日本にはシナイモツゴと生息域が分かれていましたが、モツゴが東日本に移入された結果、両種が交雑して繁殖能力のない個体が激増しました。
次第にシナイモツゴが数を減らしていき、現在はモツゴに置き換わってしまった水域が多く確認されています。
この事例は、国内外来種の交雑問題の中でも特に深刻なケースと言えるでしょう。
ドジョウ
シマドジョウやエゾホトケドジョウなどのドジョウ類も、本来とは異なる地域で発見されるケースが増えています。
以前は主に北海道の在来種であったエゾホトケドジョウが、富山県、山梨県、長野県などで確認されたことから、人間の活動による持ち込みと交雑が懸念されているのです。
ドジョウ類については食用に輸入された東アジア原産のカラドジョウが流出したことで、日本固有のドジョウとの交雑が問題視されている最中であり、そこに国内外来種の問題が重なると在来ドジョウの遺伝的純粋性が失われるリスクが高まることが予想されます。
ナマズ
ナマズは元々近畿地方以西に生息していた魚ですが、江戸時代にはすでに関東に分布を広げていました。現在では全国各所で見られるポピュラーな魚として扱われています。
ただし、どこにでもいるからと言って人間の手で放流するなどして生体数を増やすのは良くありません。
肉食性の強いナマズを他の地域に放流すると、在来の生き物を捕食して数を減らしてしまう危険があります。
またナマズは環境適応能力が高いため、一度定着すると駆除が困難です。
絶妙なバランスで成り立っている生態系の均衡はちょっとしたきっかけで崩れてしまいます。
くれぐれも気軽な気持ちで放流するようなことは避けましょう。
オヤニラミ
オヤニラミは元々は西日本の一部地域にのみ生息していた淡水魚です。
独特の風貌から観賞魚としての人気が高まり日本全国に広まりましたが、どこからか流出した個体が野生化し繁殖する例が増えています。
縄張り意識の強い肉食性であるオヤニラミが河川に定着すると、在来の小型魚を食べてしまう驚異となる可能性が高く、滋賀県では”指定外来種”として警戒されている例も。
その反面、本来の生息地では絶滅危惧種に指定されているなど、人間の都合で地域によって扱いが異なってしまった典型的な事例と言えるでしょう。
番外編:アユやイワナ、ワカサギなど

主に食用として人気のアユやイワナ、ワカサギは季節になると各地で開催される釣りやつかみ取りのイベントのために、度々養殖の個体が放流されています。
現在では当たり前のように定着して長い地域も多いため、外来魚というイメージは薄いかもしれません。
しかし、これらの魚たちも人間の手によって本来の生息地から分布を広げているのは確か。
食用人気のある魚の放流は産業として成り立っている上に、在来の魚とうまく共生していることから大きな問題にはなっていませんが、いつか国内外来魚として糾弾される日がくる可能性もあります。
まとめ:国内外来種の魚とは!在来種でも放流禁止な理由と注意したい魚種を紹介

国内外来種について解説しました。
国内外来種とは、本来の生息域とは異なる場所に人間の手によって持ち込まれた日本の魚のことを指します。
日本の在来種ではありますが、新たな環境に定着するとその地域の生存バランスが崩れて、本来の生態系を崩す危険があるため注意が必要です。
また交雑による遺伝子のかく乱を引き起こす可能性も指摘されており、仮に同じ魚種だとしても他の地域に持ち込むと固有の遺伝子が失われる原因になります。
私たちにできることは、釣りや飼育を楽しんだ後に安易に魚を放流しないことです。国内の魚だからといって、近所の川に逃がしてはいけません。
生態系は一度乱れると元に戻すのが非常に困難です。未来の日本の淡水魚たちを守るために、一人ひとりが意識を高め、責任ある行動をすることを心がけましょう。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。



 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談
お悩み相談


























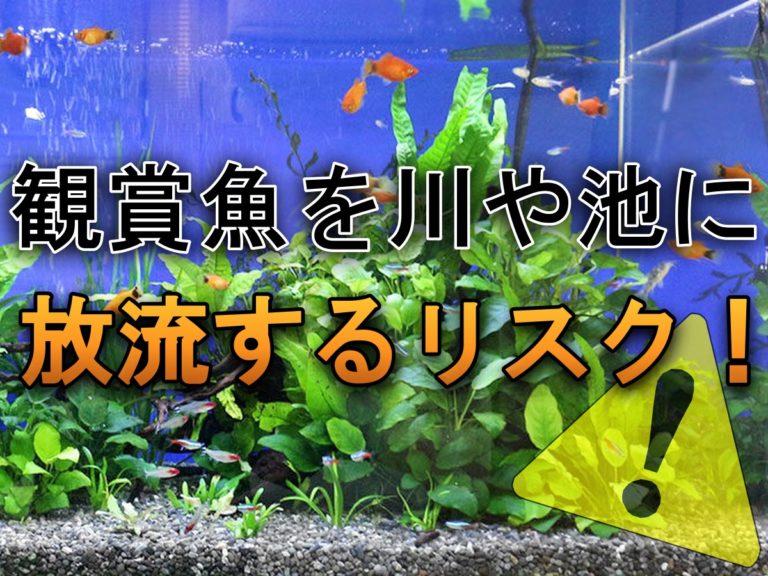

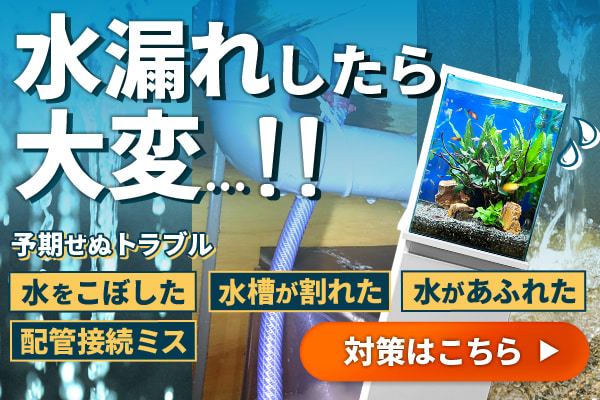



![【めだか物語】めだか色々お楽しみ 稚魚 SS~Sサイズ 20匹セット [生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/51OTP6z4f6L._SL500_.jpg)