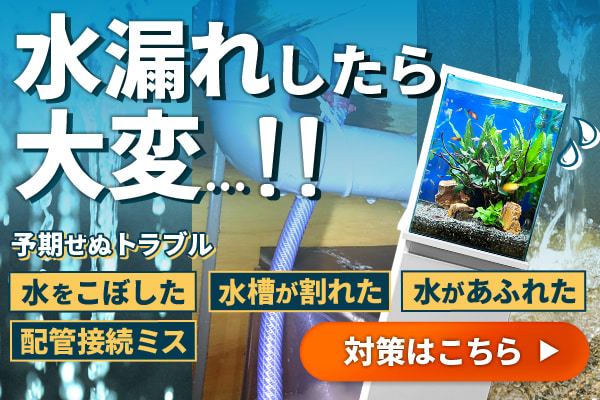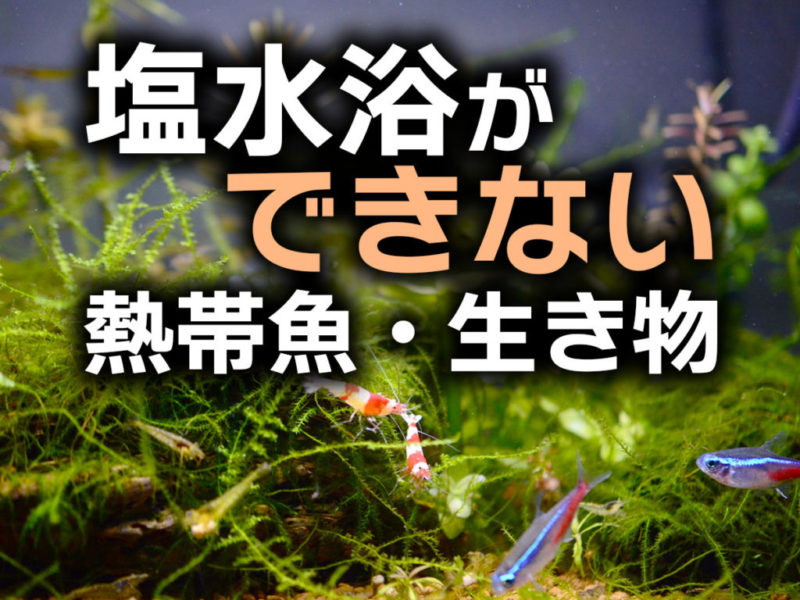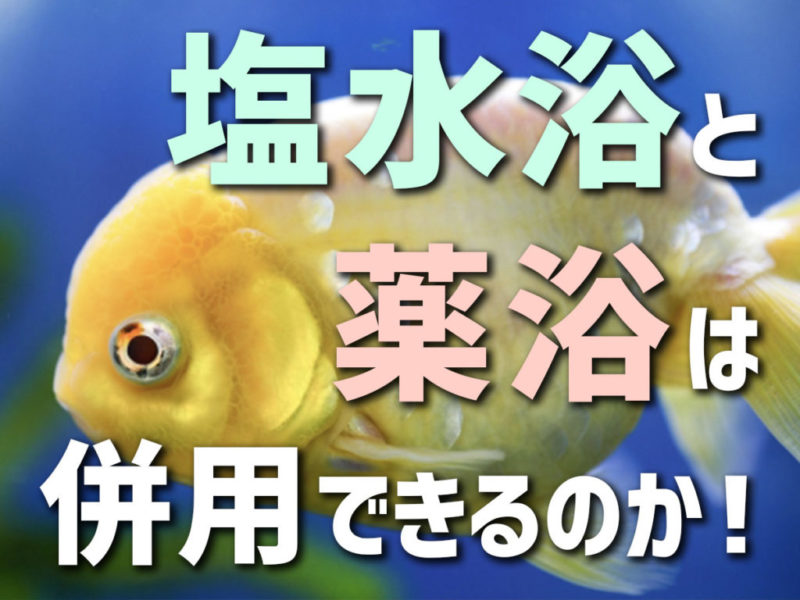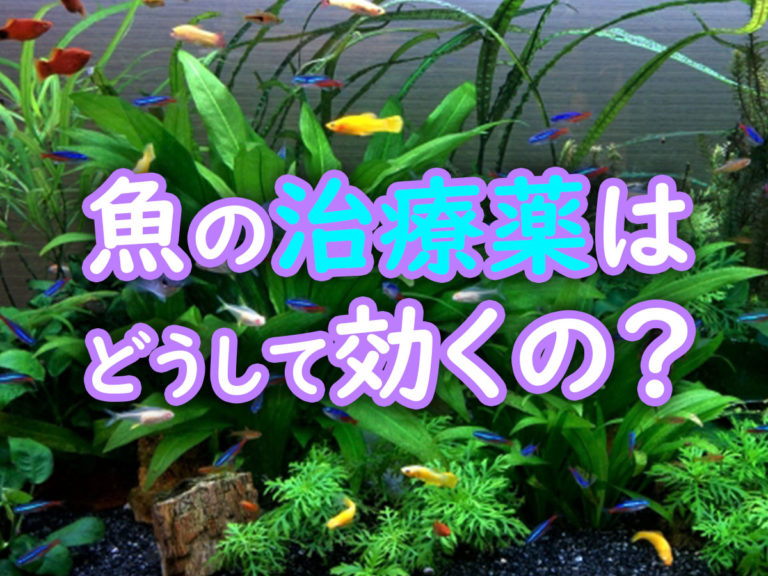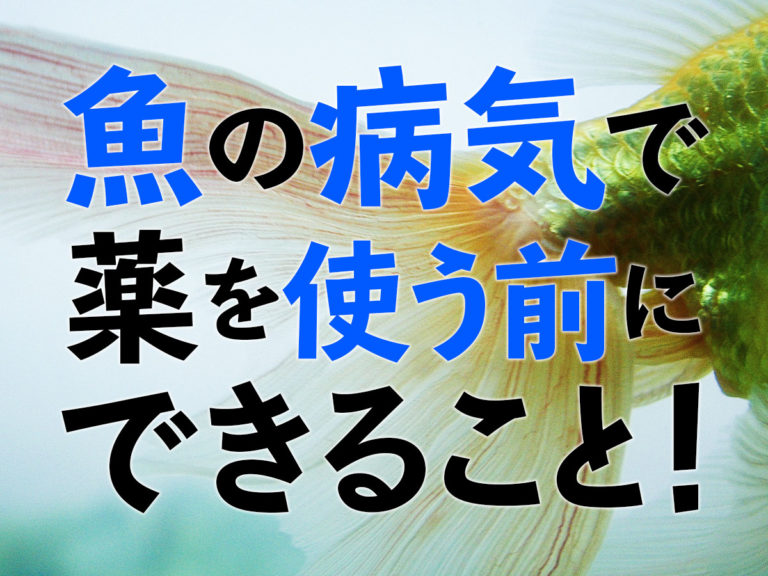魚の休薬期間とは!魚病薬の切り替え方と薬浴を継続する方法

投稿日:2025.06.04|
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
熱帯魚や観賞魚が病気にかかってしまったとき、有効な治療法として広く用いられるのが、魚病薬を使用した薬浴です。
種類によって違いはありますが、病魚への負担を考えて多くの薬は薬浴の期間を5~7日程度と定めており、日数を過ぎたら一度状態を確認するように注意書きがされています。
この時、症状が改善していれば薬浴を終えて通常の飼育に戻しますが、もし思ったように治療が進んでおらず薬を継続したいときは、どのように対処すればよいのでしょうか。
特に別の薬に切り替えたいときなどは、そのまま新たな薬を投与してしまうことに不安を感じる方もいるでしょう。
そこで今回のコラムでは、魚の病薬治療がうまく進まない場合の薬の切り替え方と休薬期間について解説します。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとに魚病薬治療を継続する方法と休薬期間を解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
薬のパッケージにある薬浴期間を経過しても症状の改善が認められず別の薬に切り替えたいときは、魚を一度休ませる休薬期間を設けることをおすすめします。
ここでは、実務経験から得た知識をもとに、魚病薬治療を継続する方法と休薬期間を解説します。
魚の休薬期間とは

魚の休薬期間とは、病気の治療の過程で魚病薬によって失った体力を回復させるための休養期間のことです。
病魚薬は病気の原因である寄生虫や病原菌を攻撃する効果がありますが、同時に魚の体にも少なからず負担を掛けてしまうもの。
そこで、魚病薬には魚を危険にさらさないための適切な用量と薬浴期間が定められています。
しかし、病気の種類や進行具合によっては、ワンクールの治療では思ったような成果が出ず、決められた期間を超えて治療を継続することも少なくありません。
特に継続のタイミングで別の薬に切り替えるときは、薬効が混ざってしまわないよう配慮する必要があるでしょう。
このようなケースでは、治療で受けたダメージを一度緩和し、薬を切り替える下準備を整えるのに休薬期間が非常に有効です。
体力を回復させることで以降の治療がスムーズに進みやすくなります。
魚病薬を切り替える方法!休薬期間の過ごし方

魚病薬を切り替える際の休薬期間中は、魚の状態をよく観察し状態にあった対処をすることが大切です。
魚の泳ぎ方や呼吸のリズム、体表や餌への興味などを確認しながら休薬期間を調整しましょう。
ここでは、魚病薬を上手に切り替えるための休薬期間について詳しくご紹介します。
3日かけて淡水に戻す
薬浴をしていた環境から休薬期間を過ごす水質に移行するため、まずは何も入れていないカルキを抜いただけの淡水に戻します。
このとき、一気に淡水に戻すと魚に負担を掛けてしまうため、3日程の時間をかけてゆっくりと真水に慣らしていくのがポイントです。
金魚などの元々体力のある魚種であれば、この3日間だけで再治療に耐えられるだけの体力が回復します。
魚病薬に弱い魚種や体の小さな魚の場合は、淡水に戻した後もしばらく時間をおいて十分に元気を取り戻したことを確認してから治療を再開しましょう。
3日という期間はあくまで目安と考え、新しい魚病薬への切り替えは体力の回復を前提として行うことが大切です。
治療を再開する目安
休薬期間を終えて治療を再開するかどうかに明確な基準はなく、飼育者が病魚の状態を見て判断する必要があります。
「再治療に耐えられる」「再治療で状態が回復する見込みがある」と判断する指針となるのが以下の2つのポイントです。
- 病気の症状が改善してきている
- 泳げる、餌に反応するだけの体力がある
まず、絶対条件として一度目の治療に効果が認められているということが挙げられます。
例えば、体表に見られた充血症状が薬浴によって改善してきているがまだ完治はしていないというケースの場合、治療を継続する価値は十分にあると考えられるでしょう。
次に、体力が回復しているという点です。
底でじっとしていて動きが鈍い魚は、著しく体力を消耗した状態であることが多く、このまま治療を再開しても薬効に耐えられない可能性があります。
この場合は治療を焦らず、休薬期間で水槽内を泳げる程度まで静養させてから、治療を再開するのが賢明です。
塩水浴を挟む
薬浴で体力を消耗している様子が見られるときは、休薬中に7日程塩水浴をして体調を整えるのも良い方法です。
塩水浴は飼育水の塩分濃度を調節することで、魚が浸透圧調整のために使う体力を温存させる治療法で、体力の回復やそれに伴う自己治癒力の向上といった効果が期待できます。
特に、金魚やメダカ、錦鯉などの淡水魚には休薬期間中の塩水浴が非常に有効です。
一方、ネオンテトラなどのアマゾン川に生息するカラシン類やミナミヌマエビ、ビーシュリンプなど、塩水に弱い性質がある生き物はそもそも塩水浴が行えないため注意してください。
また、水質変化に弱い魚種も休薬期間は、塩水浴ではなく淡水で過ごすのがおすすめです。
魚病薬の説明書をよく確認する
魚病薬を切り替えるときは、新たに添加する薬の説明書をよく確認してから使用しましょう。
どれも同じと思われるかもしれませんが、魚病薬にはそれぞれ効能や特徴があり、それに応じて使用方法も異なります。
また、まれに、治療の効果を高めるために複数の魚病薬を混ぜて使用する話を耳にすることがありますが、それは魚病薬の扱いに慣れたベテランの方が自己責任で行っているのであり、基本的には一度に使用できる薬は一種類です。
魚病薬の使用は、メーカーが記載している用法用量をしっかり守ることが大原則。魚病薬の切り替えも、メーカーが説明書に記載している方法を守って薬浴を行うようにしましょう。
魚の薬浴についての注意点

魚病薬による治療をより効果的に継続するには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。
ここでは、薬浴の効果を最大限に引き出すための注意点をご紹介します。
再投薬ができない魚病薬がある
市販されている多くの魚病薬は一定期間を空けていれば再投薬が可能ですが、中には休薬期間を空けていても再投薬ができない薬があります。
例えば、カラムナリス菌やエロモナス菌由来の完成症に用いられる『エルバージュエース』は、一般で購入できる魚病薬の中でも特に薬効の強い薬で、最長でも24時間で治療を切り上げることが推奨されており、期間を空けたとしても再投薬ができません。
そのため、このようなタイプの薬で治療した魚に病気の再発がみられるときは、症状に効果がありそうな別の薬での治療を検討しましょう。
同じ薬を継続投与する基準
説明書にある薬浴期間を終えたあと、同じ薬を使って治療を継続するかどうかは慎重に判断してください。
魚病薬は魚のために開発された薬ではありますが、治療が長期に及ぶと少なからず魚に負担を掛けます。だらだらと使用を続けてよいものではないため、確かに効果が出ていると実感できた時のみ継続使用するようにしましょう。
大抵の病気では、薬浴を始めて3日目ぐらいには治療の効果が現れ始めるはずなので、時間が経過しても症状が改善しない、悪化するといったときは、別の魚病薬に切り替えるのがおすすめです。
薬効を高めるには水温管理が重要
多くの魚病薬は水温25〜28℃程度での使用を想定して作られています。
飼育環境に比べるとやや高めの水温で最も効果が高まるため、必要に応じて水槽用ヒーターなどを使って水槽を保温しましょう。
ただし、水温が28℃を超えると魚毒性が高まる可能性があるため、上がりすぎにも注意が必要です。
そもそも薬浴中の魚はとても繊細で、ちょっとした水温変化にもストレスを感じてしまいがち。魚の負担を減らすためにも治療中は厳密な水温管理を心がけましょう。
まとめ:魚の休薬期間とは!魚病薬の切り替え方と薬浴を継続する方法

魚の病気の治療に効果を発揮する魚病薬ですが、一定期間治療を行っても効果が不十分と感じることがあります。
このようなとき、治療を継続する上での選択肢は主に二つ、
- 別の薬に切り替える
- 同じ薬を使って治療を継続する
のどちらかです。
別の薬に切り替える場合は、進行中の薬浴が終わったら一度真水に戻して、休薬期間を設けましょう。薬浴で消耗した体力を戻すことで、再治療を効果的に進められます。
現在の薬で一定の効果が得られているときは、薬を変えずにそのまま治療を継続するのも方法です。
ただ、一般的に魚病薬は投与してから3日程度で効果が現れだしますので、治療効果が薄いと感じるようならば薬の切り替えを検討してください。
魚病薬の用法用量を守ることで安全に使用ができます。使用の際はその都度注意書きを確認し、効果的に治療を進めましょう。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。



 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談
お悩み相談