
魚の再生能力とは!回復可能な魚・水生生物のケガ・病気などを解説

投稿日:2025.04.01|
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
水槽で飼育している魚が、ケガや病気で体調を崩してしまったとき、多くの方は塩水浴や魚病薬で治療を試みるでしょう。
魚は元々高い再生力を持つ生き物で、薬を使ったりゆっくり休める環境を整えたりして回復をサポートしてあげれば、病気やケガに打ち勝つことができます。
しかし、一方で完治が難しい症状があるのも事実。
水槽という限られた空間だからこそ発生する病気には重篤な症状を引き起こすものがあるため、魚の状態を見極めて早急に適切な対処をすることがとても大切です。
今回のコラムでは、魚や水生生物たちの再生能力に注目して、回復可能なケガや病気について解説します。
治癒を促す治療法や、回復が難しい症状についても触れていきますのでご一読ください。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとに魚の再生力と回復可能な症状を解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
魚には、病気やケガを直す高い再生能力が備わっています。
薬や飼育環境で回復をサポートしてあげましょう。
ここでは、実務経験から得た知識をもとに、魚の再生力と回復可能な症状を解説します。
魚は高い再生能力を備えた生き物!

人間に比べると小さくてか弱い印象の魚たちは、実は人間よりもはるかに優れた再生能力を有しています。
ヒレの先が欠けてしまったぐらいなら時間が経てば元通りになることが多いですし、ゼブラフィッシュなど一部の魚種は脳や心臓までもを治癒することができるという研究結果が出ているほど。
もちろん限度はありますが、本来魚が備えている能力を使えば、多少の病気やケガは自分の力だけで治癒することができるのです。
では、なぜ水槽内では病気にかかった魚がすぐに死んでしまうのかというと、これは水槽という限られた空間に原因があります。
水量が少ない水槽は水質が変わりやすい上に、狭くて病気やケガが蔓延しやすいため、野生よりも負担を掛けがちです。
また、自然界ではあまり罹患することがない、エロモナス菌などの常在菌が引き起こす病気のリスクが高いのも問題でしょう。
このことから水槽内の病気は、環境を整えて魚の回復力を引き出しつつ、薬を使って治癒を早めてあげるのがベストと言えます。
また、回復が難しい病気の多くは水質などの管理が行き届いていない水槽で起こるため、定期的な水換えなどをして水槽環境を適切に維持できるよう心がけましょう。
回復が見込める魚・水生生物のケガや病気

ここからは、水槽内で罹患しても治療次第で回復する可能性が高い病気やケガをご紹介します。
魚や水生生物は自己治癒能力を有していますが、再生力があるからと病気を放っておくと回復不可能なまでに進行してしまうことが少なくありません。
病気に気が付いたら早急に治療に専念できる環境を整えてあげることが大切です。
ヒレの欠け・尾ぐされ病
ケンカをしたりレイアウトに引っ掛けたりなどしてヒレを傷つけてしまっても、少し欠けた程度ならば、定期的な水換えと適切な給餌で自然と回復していくことが多いです。
ただし、傷から細菌に感染すると尾ぐされ病などの病気に進行することがあるため、いつも以上に清潔な環境の維持に努めましょう。状態に合わせて塩水浴などの自己治癒力を高める工夫をするのも良い方法です。
ヒレが白濁し、症状の進行とともに溶けたように消失する尾ぐされ病は、カラムナリス菌が原因で発症する厄介な病気ですが、初期ならば『グリーンFゴールド顆粒』や『観パラD』を使った薬浴で治療ができます。
症状が進むと治癒が難しくなるため、病気に気づいた段階で早急に治療を開始してください。
鱗剥がれ・擦り傷・赤斑病
鱗や体表についた傷は適切な水換えをしていれば自然に再生します。
こちらも治療中に細菌に感染しないよう細心の注意を払いましょう。感染予防には『メチレンブルー』を用いた薬浴がおすすめです。
赤斑病はエロモナス菌が原因で起こる感染症の一つですが、初期段階ならば水換えや底砂掃除をして水質を改善することで自己治癒する可能性があります。
ハサミの欠損

エビやヤドカリ、ザリガニ、カニなどの甲殻類のハサミは、欠損してしまっても脱皮を繰り返すうちに再生することで知られています。
もしハサミが完全に取れてしまっても、あきらめずにカルシウムやたんぱく質の多い餌を与えて飼育を続けてみましょう。
3回ほど脱皮すると再生し始めることが多いです。
貝殻の穴

水槽のお掃除生体として様々な水槽に導入される貝類の殻の穴は、ある程度は成長とともに修復されます。
先端の古い部分に空いた穴はそのままになってしまうことが多いですが、殻口付近ならばほとんど気にならなくなるでしょう。
ちなみに、カタツムリも殻口に近い部分ならば再生します。
貝類の殻の穴は、水質の変化や混泳魚につつかれて開いてしまうのが大半で、特に石巻貝は水質が酸性傾向の環境では殻が溶けて傷つきやすいです。
小さな穴程度で死んでしまうようなことはありませんが、水換え回数を増やして水質を中性に近づけることで、症状の悪化を防ぐことができます。
水カビ病
水カビ病は、体表の傷に真菌が入り込んで発症する病気で、感染部位が白い綿状のカビに覆われたような状態になります。
自己再生力だけで完治するのは難しいですが『メチレンブルー』や『アグテン』、『ヒコサンZ』などの薬を使ってサポートしてあげることで、回復する可能性が高いです。
治癒に用いる薬は、いずれも着色性なので別容器に隔離して治療を進めましょう。
寄生虫(白点虫・イカリムシ・ウオジラミ)
寄生虫感染も、軽度であれば薬浴で簡単に駆除できます。
しかし中程度以上に進行すると魚の衰弱が進んで回復が難しくなるため、なるべく初期の段階で発見して対処することが重要です。
白点病ならば『アグテン』『ヒコサンZ』『グリーンFクリアー』を使用します。
イカリムシやウオジラミが寄生している場合は、『ムシクリア液』がおすすめです。
回復が難しい魚・水生生物のケガや病気

多くのケガや病気は生き物が持つ再生能力と薬の力で治癒することができますが、中には完治が難しいトラブルも存在します。
ここでは発症すると回復が難しいケガや病気について、詳しい症状や予防方法をご紹介します。
ドジョウやナマズのヒゲの完全な欠損
ドジョウやナマズの仲間にあるヒゲは、根元から完全に欠損してしまうと再生が見込めません。
ヒゲは周囲の状況を探ったり餌を探したりするセンサーのような役割を果たす器官で、無くなると食欲不振から衰弱してしまう危険があります。
ヒゲが欠損する原因としては、
- 底砂が粗くて傷ついた
- 水質の悪化で溶けた
- 汚れた底砂から細菌に感染した
といったものが考えられており、飼育環境を改善することで予防が可能です。
底砂は触れても傷がつかない柔らかいパウダー状のものがおすすめですが、目が細かい底砂は汚れが蓄積しやすいため、クリーナーポンプを使って定期的に汚れを吸い出して清潔な状態を維持することを心がけましょう。
また、ヒゲは根元の方がある程度残っていれば再生する可能性があります。
手遅れにならないうちにヒゲが消失する根本原因を特定して、十分に養生させてあげましょう。
松かさ病

鱗が逆立って松ぼっくりのようになる松かさ病は、エロモナス感染症の中でも特に重篤な段階で見られる病気です。
エロモナス菌由来の症状が進行して内蔵がダメージを受けたことで、体内の不要な水分を排出できなくなっている状態で、家庭でできる根本的な治療はほとんどありません。
水換えや薬浴・薬餌を与えることで対処しますが、薬効を内臓まで届けるのは非常に難しく、当然自然治癒も見込めないと考えてよいでしょう。
理論上は抗菌剤を直接体に注射することで一定の治癒効果が期待できますが、魚の体力を大きく奪うため、推奨はされていません。
エロモナス菌に関わる病気がみられるときは、総じて水槽の状態が悪くなっているときです。
まずは大幅な水換えや掃除をして環境の改善を図りましょう。
pHショック
水合わせ不足や大量の水換えで水質が急変すると、pHの変化に魚が付いていけずショック症状を起こすことがあります。
しばらくすれば水に馴染むだろうと思いがちですが、ダメージが深刻だとそのまま数日以内に亡くなってしまうことも珍しくありません。
pHショックを予防するには、魚を新しい環境に慣らすこと、水質を急変させないことが一番です。
水槽導入時には時間をかけて水合わせをしたり、水換えの量は1/3程度に留めたりするだけでも、ショックを起こすリスクを減らすことができます。
クリノストマム症
クリノストマム症は、メタセルカリアという吸虫の一種に寄生されて発症します。
発症してもすぐに死ぬようなことはなく、症状は表皮にぼこぼこした卵嚢ができて鑑賞性が著しく低下する程度です。
しかし、取り除こうと薬やピンセットで刺激すると魚の体表を突き破って吸虫が飛び出してくる危険があるため、治療法がないという点で非常に厄介な寄生虫と位置づけられています。
クリノストマム症を発症した個体を見つけたら、基本的には別の容器に隔離して様子を見ましょう。水槽内に入れたままにしておくと何かの拍子に病気を蔓延させてしまう可能性があるため、必ず隔離をしてください。
また、新しい生体を水槽に導入するときは体表に異常が無いかよく確認をして、水槽に寄生虫の混入を防ぐことも大切です。
金魚ヘルペス・アロワナエイズ

金魚ヘルペスやアロワナエイズと呼ばれる病気は、どちらも治療が困難な病気とされていました。
金魚ヘルペスは、ヘルペスウイルスが金魚の内臓に感染して重篤な貧血を引き起こしたのち、多くが死に至る恐ろしい病気で、外見に異常が見られないことから発見自体が非常に難しいとされています。
アロワナエイズは体表に水ぶくれや瘤ができるのが特徴ですが、進行が早くあっという間に重篤な状態に進んでしまうため治療が追い付かないことも少なくありません。
どちらも以前は治療法が確立されていませんでしたが、近年の研究の結果、初期段階であれば、
- 金魚ヘルペス:34℃以上の水温で4日以上昇温治療を実施する
- アロワナエイズ:34度以上の昇温治療+『グリーンFゴールド顆粒』で薬浴
である程度の治癒が望めることが分かってきています。
まずは初期の段階で異常に気付くこと、また早めに原因を特定して治療を開始することが大切です。
まとめ:魚の再生能力とは!回復可能な魚・水生生物のケガ・病気などを解説

魚や水生生物は非常に優れた再生能力を持っており、水槽内で発生するケガや病気の多くは自己治癒力で回復する可能性があります。
特にヒレやハサミの欠損、寄生虫の初期症状であれば、短期間の薬浴と適切な水換え・給餌で回復が見込めるでしょう。
一方で治癒が難しい症状があるのも事実であり、特に松かさ病やクリノストマム症、金魚ヘルペスやアロワナエイズは、一度発症すると命を落としてしまう危険が高いです。
いずれの異常も進行すると回復が難しくなるため、わずかな体調変化も見逃さないように日頃からよく観察することを心がけましょう。
また、魚たちの再生能力を最大限に引き出すためには、定期的な水換え・底砂の掃除・適切量の餌やりなどが重要です。
回復可能なケガや病気もなるべく発生させないよう、日常の水槽メンテナンスを徹底することを意識してみてください。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。


 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談
お悩み相談

























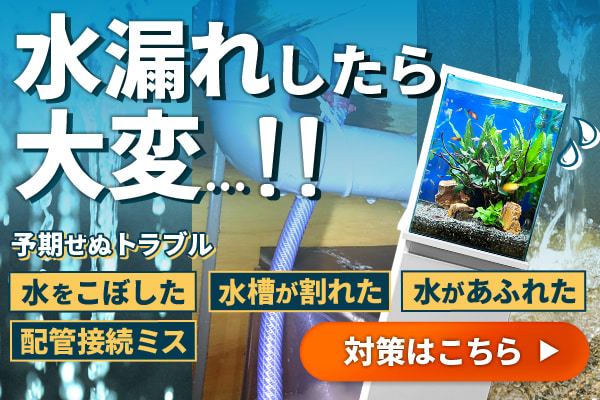




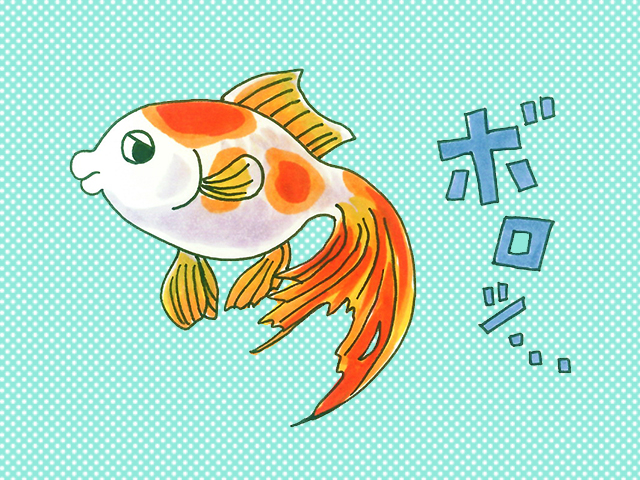








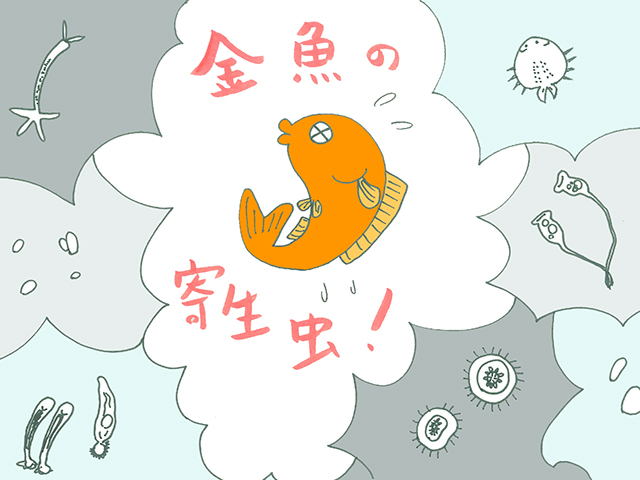










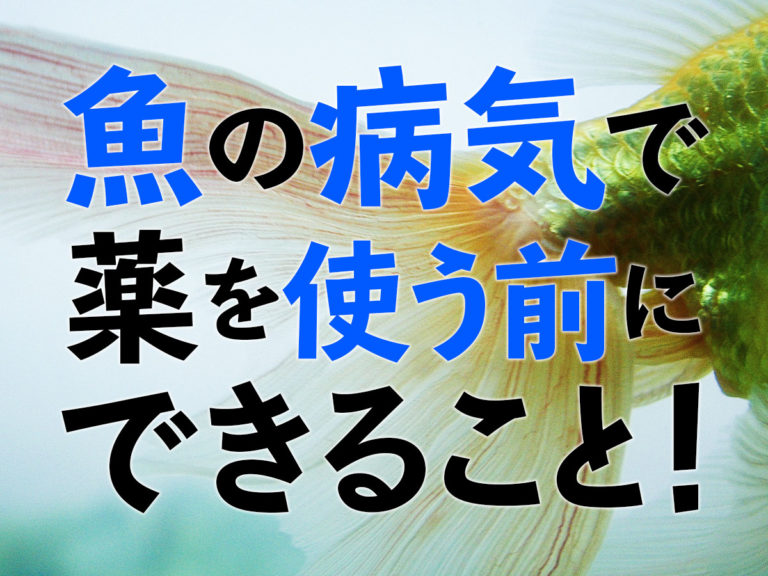


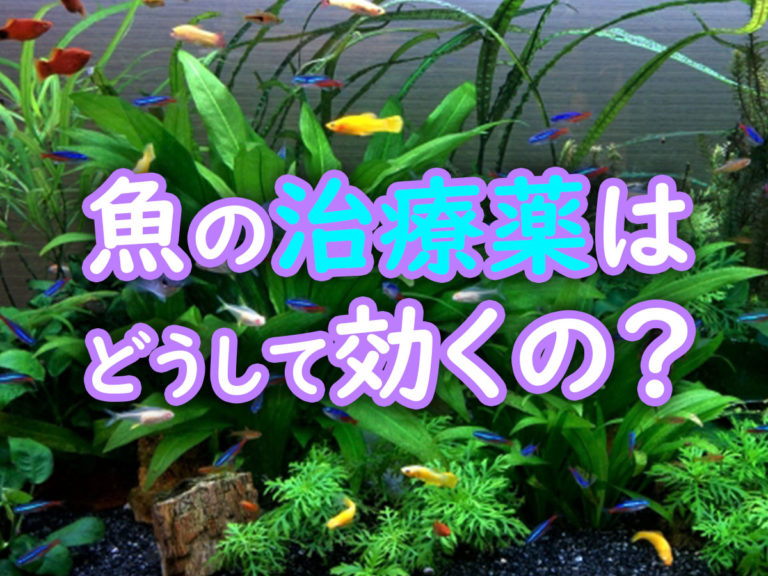


投稿されたコメントやご相談と回答
お忙しいところすみません。自宅でフェニックスバルブを観賞用に飼育しているのですが、便秘なのかフンをしていませんし、沈んでしまっています。そしてお腹が異様に膨らんでしまっています。どうしたらいいか対処方を教えてください。
実際に拝見していないため、正確な回答ではないことをご了承ください。
腹水病ではないかと考えています。
グリーンFゴールド顆粒での薬浴治療がおすすめです。その際、こまめな水換えをしながら薬浴すると効果的です。
こちらのコラムもご参照ください。
・魚のお腹が膨らむ!腹水病とは・グッピーや金魚などかかりやすい魚と治療
https://t-aquagarden.com/column/ascites
よろしくお願いします。