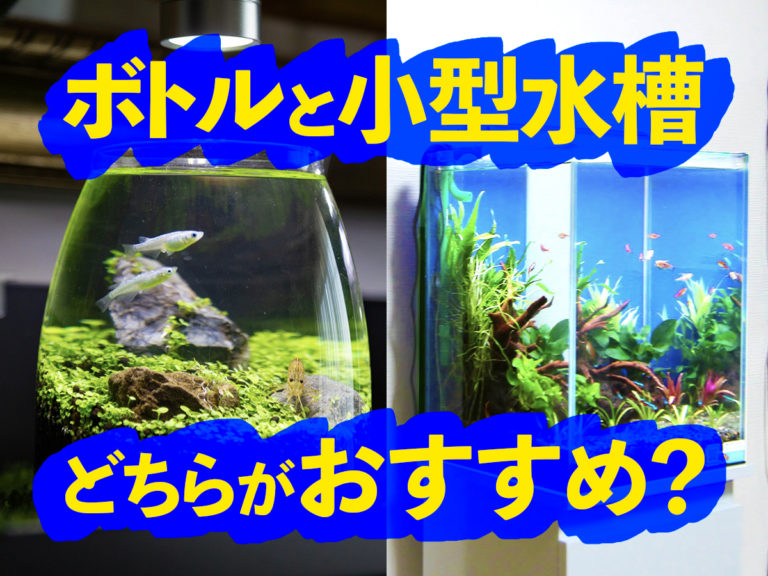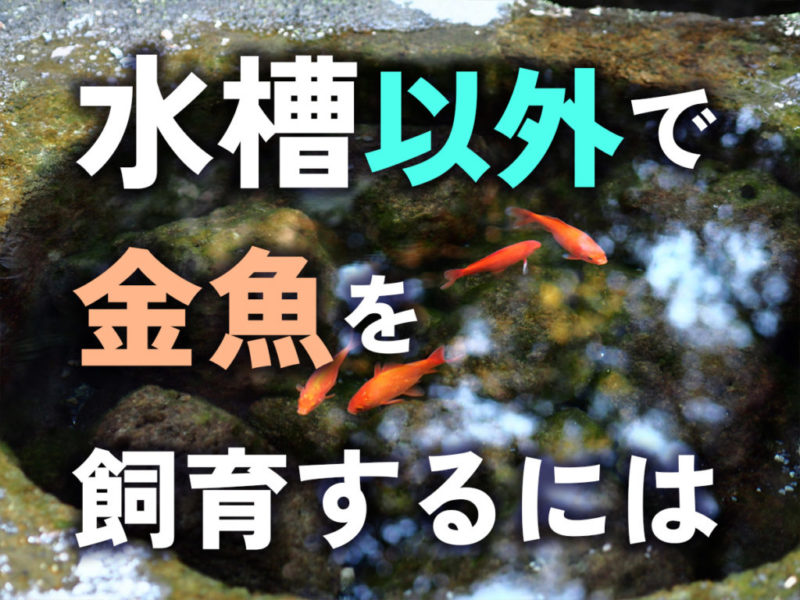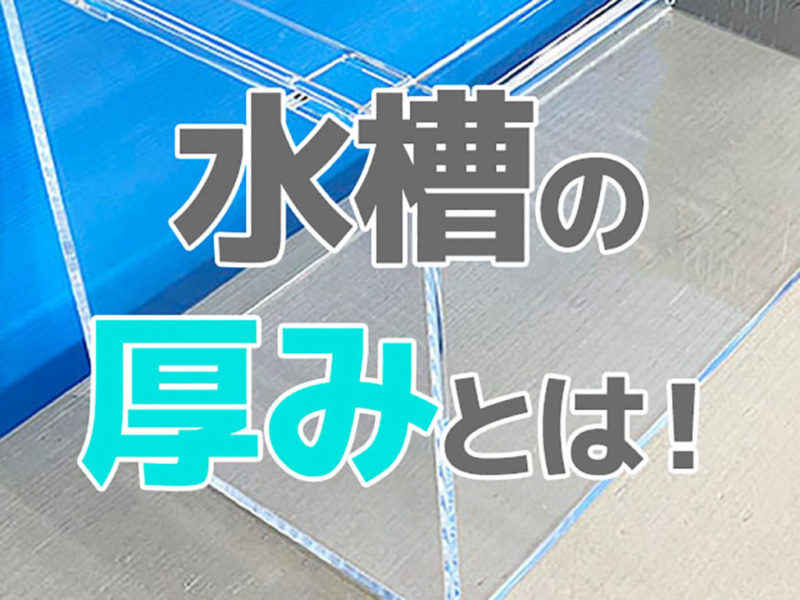水槽が四角い理由!飼育容器は魚の健康に影響する?四角が多いのはなぜか

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
「水槽はどうして四角い形ばかりなのか?」と疑問に思ったことはありませんか。
他の形の水槽はあまり見かけないけれど、それは何故なのか。
今回は、水槽が四角い理由と、丸い形の容器で魚を飼育したら、どんな影響があるのかについてをご紹介します。
通常通りに飼育できる場合や、形状や魚種によっては最適ではなく、良くない場合もあるので注意が必要です。
変わった形の容器で魚を飼育してみたい方は、ぜひ参考になさってください。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとに水槽は四角がおすすめな理由を解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
世の中にはいろいろな容器があるものの、水槽というと、イメージするのはたいてい四角い形状のものです。
しかし、四角い形状には、魚たちを飼育しやすいという理由があります。
飼育環境を整えるうえで、四角が最も効率的だからです。
ここでは、実務経験から得た知識をもとに、水槽が四角い理由と丸い水槽についてを解説します。
水槽が四角い理由

アクアリウムの水槽は『規格水槽』とよばれる横幅15~30cmきざみの四角い形状が一般的です。
ここでは、四角い水槽のメリットから水槽が四角い理由を解説します。
四角い水槽は魚の遊泳スペース・水量を確保しやすい

四角い規格水槽は、魚の遊泳スペースを確保しやすい形状です。
また、丸い容器よりも水量を多く確保しやすく、魚飼育に最適と言えるでしょう。
魚は、泳ぎにくい容器で飼育するとストレスがかかってしまいます。
魚の寿命を縮めてしまう一番の要因は「ストレス」です。
できればストレスのかからない、魚の遊泳スペースが広めに確保できる容器での飼育が望ましく、四角い容器のほうがその条件をクリアしやすいでしょう。
ネオンテトラやメダカなどの小型魚であれば、四角以外の容器でも泳ぎ回れますが、大きめの魚の飼育の時は注意が必要です。
製造・販売しやすい

水槽を作成するときに必ず使用するのが、ガラス板やアクリル板など、板状の材料です。
この板には製造上の規格があり、それにあわせて無駄が出ないようにカットしていきます。そのなかで効率よく製造できるのが規格サイズのもとになっています。
そうした材料の条件に加えて、管理・維持しやすい水量になるように設計されているのが、流通している規格水槽です。
多面的にカットするほど水圧にも弱くなりがちですし、製造や梱包コストも上がり販売価格も高くなってしまいます。
価格や安全性の観点から、製造されている水槽の多くが四角い形状になっているといえます。
細い容器は扱いが難しい

細長い容器はどうだろう、とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、細長い容器だと水の中の酸素量が不足しがちです。
水槽内へはエアーポンプなどで酸素を送るのですが、水面から溶け込む酸素量もけっこう多くあります。
細長い容器だと、水面の面積が小さいわりに全体の水の量が多いことになるので、全体の酸素量が不足してしまう、というわけです。
また、開口部が狭いと水槽内に手が物理的に入りにくく、メンテナンスが大変というデメリットもあります。
このことを踏まえても、開口部が広い四角水槽は理にかなっているといえるでしょう。
魚の体長ギリギリサイズの容器だと運動量が減る

満足に泳ぎ回れるスペースが確保できないと、どうしても魚たちの運動量が減ってしまいます。
例えば、金魚が成長して、水槽が狭くなってきた・・・という場合や、メダカが想定以上に繁殖してしまった・・・という場合に起こりがちな問題です。
その結果、ストレスがたまり消化不良を起こすこともありますし、肥満にもなりやすくなります。
狭すぎると発育にも影響がありますので、自由に泳ぎ回れるだけのサイズは確保してあげたいところです。
また、水量に対して生体が大きい・匹数が多すぎると、水量に合わせて魚の数が減ることがあります。
その点、四角い規格水槽なら遊泳スペースと水量を効率よく確保できます。
規格水槽でないと機材の効果が発揮しにくい
アクアリウムの機材は基本的に30cm~150cmなどの規格水槽用に作られています。
そのため、規格水槽以外で使用すると、設備の効果が十分に発揮できなくなる可能性があるのです。
例えば、水槽用照明は水槽全体をまんべんなく照らすように設計されている機材です。
しかし、縦長すぎる容器だと、水槽の底面まで水槽用照明の光が届かない場合もあります。
一部だけに光が当たり、一部には当たらないとなると、水草は育ちにくいです。
また、一般に水槽内にはろ過フィルターによって、水流ができますので水温や水質が一定です。
しかし、ろ過フィルターの水流が巡りにくい形状だと、水の循環がうまくいかず淀むことがあります。
淀みができると環境が悪化しやすく、生き物たちはストレスを抱えやすくなり病気になることも。
機材にあった形状の飼育容器を用意するのが望ましいため、必然的に四角い規格水槽を使用することになります。
丸い容器が魚に与える影響

日本では昔から、丸いガラス製の金魚鉢などをよく目にします。
しかし、丸い容器は魚によくないという意見もあるのです。それはなぜかを解説します。
丸い容器は海外では使用禁止?!
フランスなど、他のヨーロッパ諸国でも虐待とみなされることもあるのです。
丸いガラス製の容器に水を入れた状態だと、容器内からは外の景色がゆがんで見えてしまい、魚にとってストレスになるから、というのがその理由です。
人が覗き込んだ時にレンズ効果により、通常よりも巨大に見えて魚がビックリするということもあります。
また、一般的にそういった容器は水量が少なくなりがちな上に、ろ過フィルターなどをつけにくく、それも魚にとって望ましい環境とは言えません。
ちなみに、丸い容器は外から見ても、若干魚が歪んで見えます。
鑑賞性の点からも、ストレートなガラスを使用している規格水槽のほうがおすすめなのです。
丸い容器でも飼育は可能

とはいえ、丸い容器でも魚の種類によっては問題なく飼育できる場合もあります。
金魚のように「フンが多くて水を汚しやすい、大きく成長しやすい」種類の魚ですと、水量が少なめな丸い容器では頻繁な水換えが必要になるなど、飼育しにくいです。
しかし、身体が小さくて、静かな環境での飼育に向いているベタやアカヒレ、メダカなどであれば問題はあまり起こりません。
どういった魚なら問題ないんだろうと気になった場合は、ボトルで飼育できる生体かどうかを調べましょう。
ボトルで飼育出来る魚種は丈夫で小型の魚が多いので、丸いガラス製の容器でもあまり悪影響を受けずに済みます。
また、最近では、丸形容器用のろ過フィルターも登場しています。

ろ過装置をつける場合には、こうした製品を選ぶようにしましょう。
しかし、水槽用ヒーターなど保温器具をつける場合は規格水槽を用意することになります。
また、アクアリウム用に設計された『円柱水槽』は丸い水槽の中でも管理しやすく、長期飼育が可能です。
円柱水槽は、ろ過システムを一体化させて設計するため、水質の問題をクリアできます。
東京アクアガーデンでも数多くの円柱水槽を管理しています。
開口部の広い容器がおすすめ

変わった形の容器での飼育についてご説明してきましたが、やはり一番のおすすめは「開口部が広い容器」です。
水温調節が必要ないメダカなどの魚種なら、睡蓮鉢のような間口の大きなもので問題なく飼育できます。
開口部が広い=水面が広い=酸素が多く溶け込む、光が均一に入る=水温が均一になる、魚が泳ぎやすい、といろいろなメリットがあります。
また、魚の種類によっては水圧が苦手な場合もあります。例えば高さがある容器だと、上と下で水圧が変化してしまい、その中を泳ぐことで転覆症状が出やすくなるので注意が必要です。
水圧が苦手な魚は、小型魚、ベタ、メダカ、金魚などです。
まとめ:水槽が四角い理由!飼育容器は魚の健康に影響する?四角が多いのはなぜか

魚を飼育する際に、四角い規格水槽がなぜ多いのかを解説しました。
水槽用ヒーターなどの保温機材や水槽用照明、そしてろ過フィルターも一般的には規格水槽用に設計されているため、それらを使用するには四角い規格水槽が望ましいです。
しかし、魚種によっては変わった形の容器でも飼育は可能ですので、飼育したい魚、使ってみたい容器など、場合に応じて上手に使い分けられると楽しみ方が広がります。
デメリットなどを念頭に、魚たちに合った飼育容器を選択していきましょう。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。



 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談
お悩み相談