潮干狩り・潮だまりでとれる生き物とは!採集の注意点・リリースについて

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
春から初夏にかけては潮干狩りや磯遊びで海を訪れる機会が増える季節。
一般的にはアサリやハマグリといった二枚貝を目当てにしますが、その足元に目を向けてみると、カニやヤドカリといった様々な生き物が潜んでいることに気づきます。
また潮が引いたあとの岩場にできる潮だまり(タイドプール)は、幼魚や甲殻類、小型のヒトデや貝など、多彩な生き物の観察や採集が楽しめる絶好のフィールドです。
しかし、こうしたフィールドで生き物を採集するには、事前に知っておくべきルールやマナー、注意点があります。
ルールを守らないと、大きなケガやトラブルに繋がることもあるのでしっかり確認しておきましょう。
この記事では、潮干狩り・潮だまりで出会える代表的な生き物や採集の注意点、リリースに関するマナーまで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとに潮干狩り・潮だまりにいる生き物と採取のマナーを解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
潮干狩りで海を訪れた際は、ぜひ貝だけでなく、砂浜や岩場、潮だまりにいる生き物にも目を向けてみましょう。
小さなカニや魚からヒトデやアメフラシといったちょっと変わった生き物まで、様々な海の仲間に出会えます。
ここでは、実務経験から得た知識をもとに、潮干狩り・潮だまりにいる生き物と採取のマナーを解説します。
潮干狩り・潮だまりでとれる生き物

海の生き物を観察すると言われると、海中深くに潜るダイビングを想起される方もいるかもしれませんが、実は砂浜や岩場、潮だまりなどでもたくさんの生き物を見つけることができます。
ここでは、潮干狩りや潮だまりで捕まえることができる代表的な生き物をご紹介します。
潮干狩りに訪れた際は、ぜひ図鑑をみながらどんな生き物がいるかをチェックしてみてください。
ハゼの若魚

波が引いた後の潮だまりでは、様々な小魚を目にすることができます。
本州付近でよく見かけるのは、アゴハゼやドロメといったハゼの若魚です。
河口に近い地域ではマハゼが群れで泳いでいることもあります。
ハゼの仲間は底の付近でじっとしていることが多く、逃げ足もさほど早くないのでお子様が採取するのにも向いています。上手に網を使えば、何匹かを一気に捕まえることも可能です。
ただし、体長数cm程度の小さな稚魚は非常にデリケートなため、捕獲する際は負担を掛けないように優しく扱ってあげてください。
カレイの稚魚

砂地や砂地に近い潮だまりでは、カレイの稚魚もよく見かけます。多くはイシガレイの稚魚で、体の模様や色が周囲と同化しており、見つけるのが難しいです。
その反面、見つけられたときの達成感は格別でしょう。
発見のポイントは砂地や海底を注意深く観察することです。カレイが隠れている場所の砂の盛り上がりやわずかに動く体や目で発見できますし、網を海底で少しずつ動かしていくと、驚いたカレイが急に動き出すこともあります。
また、カレイは底面積の広い水槽に、細かな砂を敷けば比較的簡単に飼育が可能です。
ボラの稚魚

河口を群れで泳ぐ姿が有名なボラですが、潮だまりでは体長3〜5cm程度の稚魚が群れで泳いでいることがあります。
水面付近にいることが多いので見つけやすいですが、泳ぎが素早いので捕まえるのには少々苦労するかもしれません。
ただ、非常に環境適応力が高い魚なので、採取ができたら連れ帰って飼育にチャレンジしてみるのもおすすめです。
輸送中のストレスには弱いので、飼育を考えているときは携帯型のエアレーションを持参して準備を整えた上で、採取しましょう。
ヒトデ
海底や岩に貼りついているイメージの強いヒトデですが、実は波打ち際に近い砂地や潮だまりでも良く見かける生き物の一つです。
星のようにも見える形にカラフルな体色がユニークで、お子様の観察対象にもぴったり。モミジガイやイトマキヒトデなど種類によって色や形が異なるので、図鑑と照らし合わせてみていくのも面白いです。
ヒトデは管足(かんそく)という足で、岩場などに貼りついています。無理に剥がすと管足を痛める可能性があるため、採取の時やバケツから取り出すときは、力加減に注意してください。
ちなみにヒトデは、水質悪化やストレスに弱い面があることから、飼育が困難な生き物として知られています。
弱った時に体内から放出する”サポニン”という物質が、同じ水槽で飼育している生き物に悪影響を与える可能性点も厄介です。
鮮やかな品種が多く水槽にいれると華やかですが、このことような特徴からあまり飼育はおすすめできません。
カニの仲間

砂浜や岩陰など様々な場所に潜むカニは、イソガニやアカテガニなどの小型種で俊敏に動く種類が多いです。
特に水上にいる個体は、人の気配を感じるとすぐに岩陰に隠れたり逃げ出したりしてしまうため、網を構えて素早く捕獲しましょう。
水中にいる個体はそれと比べると動きもゆっくりなので、比較的捕まえやすいです。
捕まえる際は、ハサミに挟まれないように注意してください。小さな個体でも意外に力が強く、挟まれると痛みを感じるほどです。
またこちらが挟まれなまくても、力がかかるとハサミがとれてしまう可能性もあります。いずれにしても、ハサミに注意して優しく取り扱いましょう。
飼育する際は身体が浸るくらいの水位にして、石などで陸地を作ってあげると長く楽しめます。
ヤドカリ

ホンヤドカリやイソヨコバサミなどのヤドカリの仲間は、浜辺や岩場で良く見かける代表的な生き物です。
殻に隠れるユニークな姿が可愛らしく、簡単に捕まえられるので磯遊びでも人気があります。
捕まえた直後は殻の中に隠れてしまいがちですが、容器に入れて落ち着いてくると殻から出てきて活発に動き回る姿を観察できるでしょう。
飼育も簡単で、一般的な海水魚水槽はもちろん、プラケースに少し水を張って陸地を作ったような簡易的な環境にも適応できます。餌も様々なものを食べるので、初心者の方でも挑戦しやすい生き物です。
ただし、成長すると大きな殻に引っ越す必要があるので、適当な大きさの貝殻を用意しなくてはいけません。
季節来遊漁
近年は温暖化の影響もあり、本州でも以前は見られなかった季節来遊魚を見かける機会が増えています。
季節来遊漁は本来は南方の温暖な海に棲む魚ですが、黒潮の流れに乗って夏から秋にかけて本州沿岸に流れ着く魚たちです。
チョウチョウウオやスズメダイの仲間など、美しい体色や優雅な見た目が魅力的なアクアリウムでも人気の魚たちが多いので、マリンアクアリウムを管理できる環境があるならば、採集して連れて帰るのもおすすめ。
自分で採集した魚を飼育するのは、購入した魚を飼育するのとはまた違った楽しさがあるでしょう。
しっかりとした環境を整えれば、流通している個体と大差なく飼育が可能です。
海の生き物を採集する際の注意点

磯遊びや潮干狩りで生き物を採取するには、いくつか注意点があります。
条例や法律で採取が禁止されている生き物についてや、安全に関することなど重要な内容ですので、海に行く前に必ず確認しましょう。
法律や条例で採取が禁止されている生き物がいる
海の生き物には漁業権が設定されており、一般人は捕獲するのが禁止されているものが少なくありません。
代表的な例では、ウニやナマコ、サザエ、タコなどです。これらは採集するといわゆる密漁になります。
特にウニやナマコは逃げることもないので簡単に捕獲できてしまいますが、密漁すれば罰金刑や懲役刑が科されるため絶対に止めましょう。
地域によって漁業権が設定されている生き物が異なるので、採集前にその地域の漁協や自治体のホームページで情報を確認しておくことを強くおすすめします。
飼育可能かを考える
採集可能な生き物であれば、採集後は自宅に持ち帰って飼育することが可能です。
ただ、海水魚は淡水魚に比べて飼育が難しい魚種が多く、海水魚飼育のノウハウやしっかりとした設備がないとすぐに残念な結果になりかねません。
家に連れ帰るまでに弱ってしまうことも多いので、もし飼育を目的にするのであれば、
- 飼育設備を用意し水槽を立ち上げておく
- 家まで輸送するためのエアレーションなどを用意する
といった準備を整えてから採取にチャレンジしてみてください。
また、海の生き物の中には飼育難易度が高いものや思った以上の大きく成長するものもいます。採取した時点で魚種の特徴を確認し、本当に飼育できるのか検討してから持ち帰るようにしましょう。
岩場や毒のある生き物に気を付ける
潮だまりは岩場が多く、転倒や擦り傷の危険があります。
遊びに行く際はビーチサンダルや裸足ではなく、必ずマリンシューズなどの滑りにくい靴を選びましょう。
一見安全そうに見えても濡れた岩は非常に滑りやすく、転倒事故も多発しています。水深がある場合は、ライフジャケットも着用すると安全です。
また海にはゴンズイやハオコゼなどの毒のあるものや、鋭いトゲを持つ生き物も多く生息しています。
生き物を見つけてもすぐに素手では触らずに、まずどんな生き物なのか確認してから採集をするようにしてください。
海の生き物のリリースについて

潮だまりでの観察や採集は、自然とのふれあいを楽しめる素晴らしい体験です。
禁止されていない限り捕まえて楽しむことができますが、飼育の予定がない場合や、飼育環境が整っていない場合は、観察後に必ず元の場所に生き物を戻してください。
採った場所に戻すことはリリースの基本的なマナーです。 潮だまりで採った生き物を、すぐ近くだからといって砂浜に逃がすのはよくありません。
生き物ごとに適した環境もありますので、必ず元の場所に戻しましょう。
また丁寧に扱い、生き物を弱らせないようにしてください。甲殻類はハサミや脚が取れやすいで注意しましょう。
まとめ:潮干狩り・潮だまりでとれる生き物とは!採集の注意点・リリースについて

潮干狩りや潮だまりで採取できる生き物についてご紹介しました。
潮干狩りや潮だまりは、大人も子どもも楽しめる天然の学び場です。
ハゼやヤドカリといった身近な生き物との出会いは、生き物への興味や命の大切さを実感できる貴重な機会になるでしょう。
一方、無闇に採取をするのは良くありません。海の生き物の中には条例で採取が禁止されているものもいますし、毒やトゲを持つ生き物も多いです。
また飼育できる環境が整っていないにもかかわらず、思い付きで持ち帰っても魚がかわいそうな結果になってしまいます。
末永く自然を楽しむためにも、ご紹介した注意事項を守りましょう。
楽しく、安全に、そして思いやりをもって、潮干狩りと潮だまりで楽しい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。



 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談
お悩み相談

























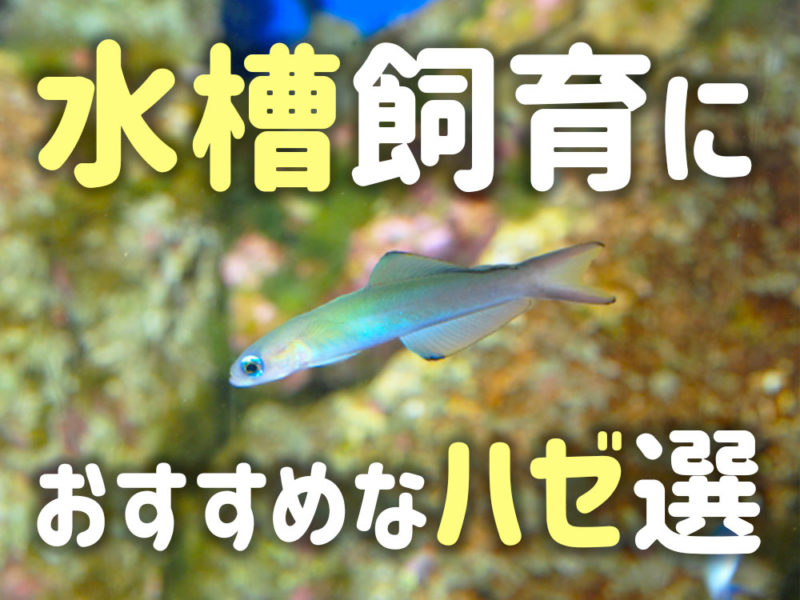




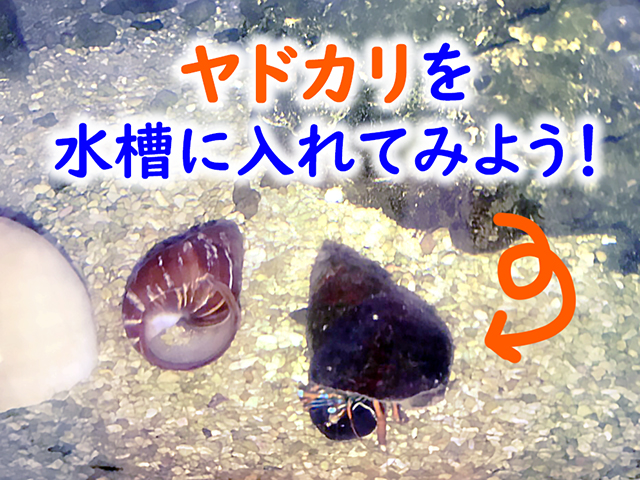

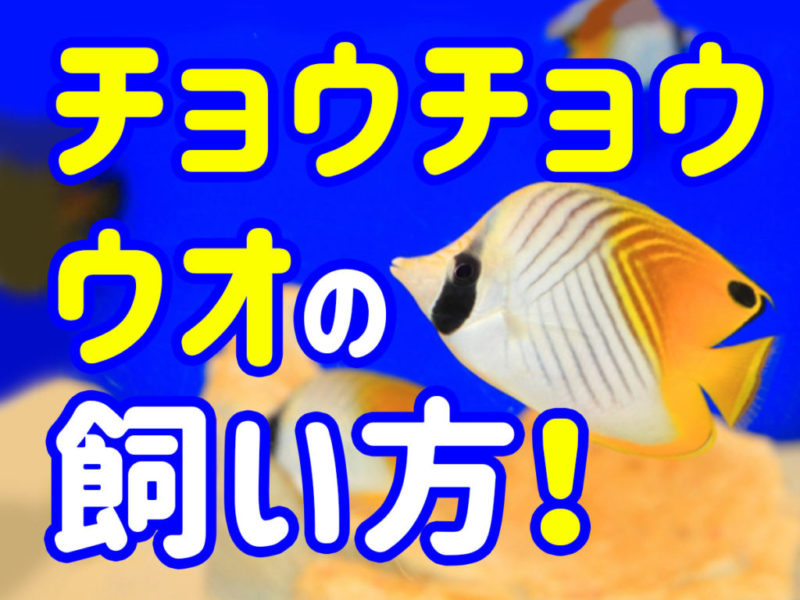








![[リーフツアラー] 【Amazon.co.jp 限定】 (REEF TOURER) シュノーケリングにも フィンガード付 マリンシューズ 大人用 26cm ブラック RBW3041P](https://m.media-amazon.com/images/I/314TT2qku0S._SL500_.jpg)







