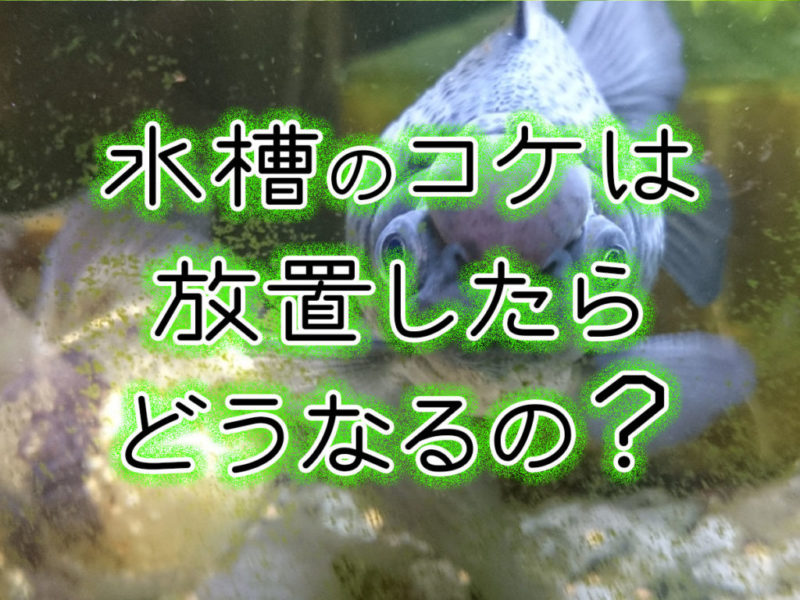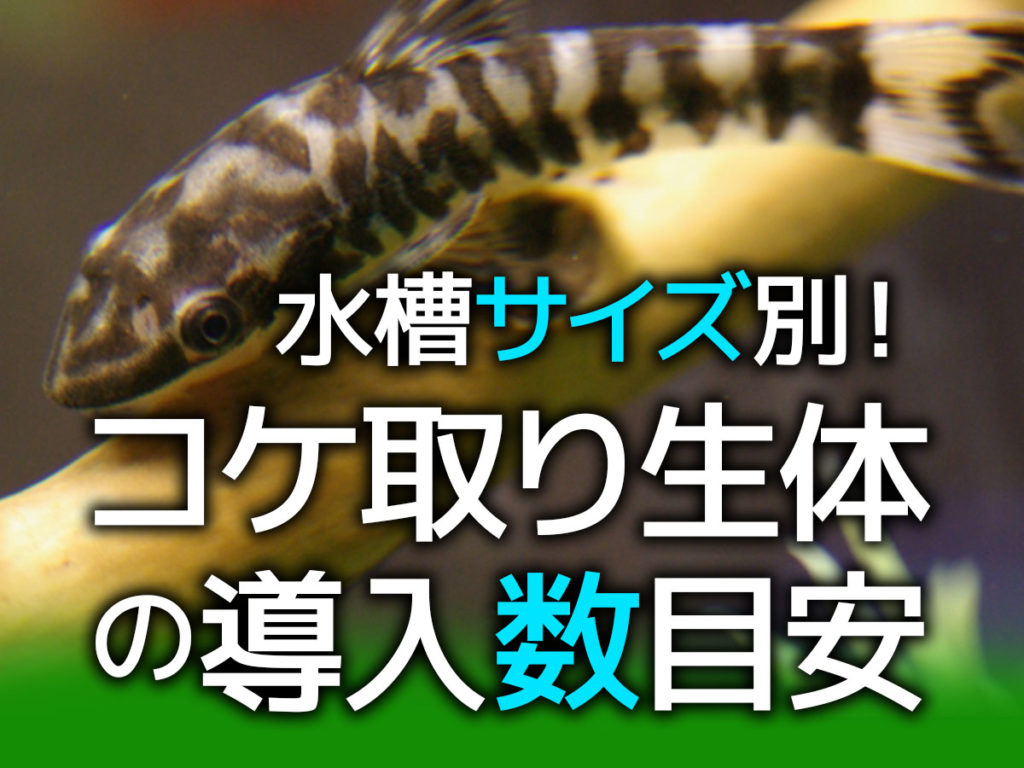弱アルカリ性水槽のコケ取り生体8選!pHが高い水槽におすすめの対策!

投稿日:2025.03.18|
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
アクアリウムにコケはつきもの。どんなにこまめに手入れをしていてもいつの間にか生えてくるコケの対処に、お悩みの方も多いのではないでしょうか。
特に水質をpH7.5程度のアルカリ傾向に維持している水槽では、通常よりもコケが生えやすい上に、一般的なコケ取り生体が飼育できないなどの制限がつくことから、コケ対策に苦慮することも少なくありません。
また、弱アルカリ性の環境は、コケの中でも毒性が強く厄介な藍藻の原因となるシノアバクテリアが活発になりやすい、というのも問題です。
今回のコラムでは、そんな弱アルカリ性の水槽でできるコケ対策に焦点を当てて、飼育できるコケ取り生体やコケ対策について解説します。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとに弱アルカリ性で活躍するコケ取り生体とコケ対策を解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
水草や多くの熱帯魚が苦手とする弱アルカリ性の環境では、コケが活発になりやすいです。
厄介なコケが繁茂すると水槽全体に影響が出てしまいますので、しっかり対策をしましょう。
ここでは、実務経験から得た知識をもとに、弱アルカリ性で活躍するコケ取り生体とコケ対策を解説します。
アルカリ性傾向はコケが生えやすい?

アクアリウムの世界では、水質がアルカリ性に傾くとコケが繁茂しやすいという通説があります。
アフリカンシクリッドやミドリフグなどを飼育するために水質を弱アルカリ傾向に維持している水槽はもちろん、普段は弱酸性の水槽でも何らかの原因で水質が変化すると、コケが勢いづくことがあるのです。
では、なぜアルカリ性の水槽ではコケが生えやすくなるのでしょうか。
ここではアルカリ性でコケが生えやすくなるメカニズムについて解説します。
水草が弱るとコケに栄養が回りやすい
水草は弱酸性の水質を得意とする品種が多く、クリプトコリネなどの一部の種類は、水質がアルカリ性に傾くと調子を崩しやすいです。
その点コケは、水質に関わらずどんな環境でも成長することができるため、水草が弱ってしまった水槽では、余った栄養分をコケがすべて吸収して繁茂しやすくなります。
コケ取り生体は弱アルカリ性が苦手

コケを食べてきれいにしてくれるコケ取り生体にアルカリ性の水質が苦手な種が多い、というのもコケが繁茂しやすい理由です。
幅広い種類のコケを食べてくれるミナミヌマエビやオトシンクルス、髭状コケを食べるフライングフォックスなど、一般的な水槽で主力となるようなコケ取り生体はpH7.5以上である弱アルカリ性の水質が苦手で、長期飼育には向きません。
水草などのライバルとなる植物やコケを食べてしまう敵の生体がいない弱アルカリ性の環境は、コケにとって最も繁殖しやすく環境と言えるのです。
藍藻は弱アルカリ性が得意
pH7.5以上の弱アルカリ性環境では、コケの中でも特に厄介な藍藻が活性化しやすいです。
藍藻はシアノバクテリアという細菌で、見た目は緑や茶色、赤紫色のドロッとした形状をしています。
砂利やレイアウトなどに絡みつくように増殖していくことから景観を著しく損なう上に、放っておくと悪臭や毒素を放つため、発生したら早急に除去するのが基本です。
アルカリ傾向の水槽では、通常よりも繁殖スピードが上がりやすいので、しっかり対処法を学んでおくことをおすすめします。
pHが高い水槽におすすめのコケ取り生体8選

ここからは、pHが高めの水槽でも飼育ができるコケ取り生体を8種ご紹介します。
弱アルカリ性の水質では飼育できる生体が限られるというお話をしましたが、もう一つコケ取り生体が導入しづらい理由として、弱アルカリ性の水槽で飼育されるシクリッドの仲間や淡水フグがとても気性が荒い魚種であるということがあります。
今回は、これらの魚種とでも比較的混泳が成り立ちやすい生き物を厳選しましたので、混泳魚に合わせて選定してみてください。
ブッシープレコ
黒いベースに白のスポット模様が入る、見応えのある小型のプレコです。茶ゴケや緑ゴケなどの柔らかいコケを食べてくれます。
最大体長が15~20cm程と比較的大きめの体型で食欲が旺盛なので、一匹でもコケ取り生体としてしっかり活躍してくれるでしょう。
プレコの仲間は中層~低層を泳ぐ性質から、アフリカンシクリッドと生活圏が被らず、混泳が成り立ちやすいのもポイントです。
セルフィンプレコ
大きく立派な背びれが印象的な大型のプレコです。プレコの中でも特に流通量が多く人気の品種なので、見かける機会も多いのではないでしょうか。
体長は最大で30cm程度まで成長するので、中型~大型水槽のコケ取り役としておすすめです。
こちらも食欲が旺盛でコケを数日で食べつくしてしまうことがあるため、コケが不足してきたらプレコ用の餌を与えて餓死を予防しましょう。
ブラックモーリー
漆黒の体色がクールなブラックモーリーもコケ取り生体として人気です。
藍藻を食べてくれる数少ない生体として知られいるほか、糸状ゴケや油膜といった他の魚が食べないコケを積極的に食べてくれることから、水槽内の様々なお悩み解決に役立ちます。
弱アルカリ性の水質でも問題なく飼育できるなど飼育条件はぴったりですが、一方性格が温和で気性の荒い魚種と混泳するといじめられてしまう危険があるめ、混泳魚の選定は慎重に行いましょう。
ラムズホーン
東南アジア原産の淡水性巻貝の仲間です。角を出したカタツムリのような可愛らしいフォルムと、ピンクや赤、ブルーなどの豊富なカラーバリエーションから、鑑賞用としても人気があります。
体長2cm程度とかなり小さな貝なので、小型水槽にも導入しやすいでしょう。
単体での能力は控えめなので、水槽の大きさに合わせて複数匹導入するのがおすすめです。
雑食性で餌の食べ残しなども食べてきれいにしてくれるので、コケの除去や予防に力を発揮します。
ただし、繁殖力が高く環境が良いとあっという間に数を増やしていくため、増え過ぎに注意したい品種でもあります。
イシマキガイ
コケ取り生体の代表種であるイシマキガイも、アルカリ傾向の水槽で飼育が可能です。
安価で流通量が多くコケ取り能力も高いので、コケにお困りならばとりあえずイシマキガイを入れておけば間違いありません。
また、イシマキガイは汽水域でしか繁殖しないという特性を持っており、淡水水槽で増えることが無いのも導入しやすいポイントです。
シマカノコ貝
黄色ベースの殻に黒の縞模様が美しい、体長2~3cmほどの巻貝の仲間です。
コケ取り能力がかなり高く、水槽内を縦横無尽に移動しながら壁面や水草、レイアウトに付着したコケを食べてあっという間にきれいにしてくれます。
調度よいサイズ感と可愛らしい柄で複数匹導入しても鑑賞性を損なうことがない点もポイント。さらにシマカノコガイも淡水水槽では繁殖しないため、飼育数を管理しやすいのもメリットです。
フネアマ貝
汽水域に暮らす夜行性の貝類です。
平べったいアワビのような褐色の貝殻を持っていて、明るいうちはあまり活動しないため、貝を目立たせたくないレイアウト水槽などで重宝します。
コケ取り能力についても申し分なく、特に水槽の壁面に付着したコケの除去に力を発揮するでしょう。
様々な水質、水温に適応できる丈夫さを備えているため弱アルカリ性の水槽でも飼育が可能ですが、肉食性の強いミドリフグなどには食べられてしまう危険があるため、混泳の際はご注意ください。
ヤマトヌマエビ
ヤマトヌマエビは、エビ類の中ではpH7.5程度の弱アルカリ性でも飼育可能な種類です。
汽水域で繁殖するため、アルカリ性傾向に強く弱アルカリ性水槽のコケ取り生体としても採用できるでしょう。
しかし、注意したいのは弱アルカリ性を好む魚種たちの食性です。
シクリッドや金魚、フグの仲間はもちろん、グラミーやベタもエビを好んで食べるため、そうした魚種の水槽には導入が難しいと言えます。
グッピーやモーリーの小型魚ならヤマトヌマエビが口に入らないため混泳可能です。
弱アルカリ性の水槽でできるコケ対策

掃除をしてもまたすぐにコケが生えてきてしまうような水槽は、飼育環境に何らかの問題が生じている可能性が高く、根本を解決しないとコケの繁茂を防ぐことができません。
ここでは、コケを減らす対策をご紹介しますので、一つずつ確認をしてみてください。
照明の点灯時間を短くする

コケが生えやすいと感じるときは、照明の点灯時間を見直してみましょう。
コケも植物の一種なので光が豊富な環境では光合成をしてどんどん成長してしまいます。
また、照明の点灯時間は1日8時間程度が目安ですが、太陽光や部屋の明かりが差し込みやすい環境に水槽を設置している場合は、点灯時間外に水槽に光が当たっていないかを確認してみてください。
外部から光が差し込む時は、照明の時間を短くしたり少し光量を抑えたりといった工夫をするのがおすすめです。
餌を控える
餌の食べ残しが多い水槽は、コケが生えやすい傾向があります。
餌から水中に溶け出す養分がコケの栄養になってしまうからです。
また、餌をたくさん食べて魚のフンが増えると、これもコケの肥料になって成長を促進させる可能性があります。
熱帯魚の餌は1日1~2回、5分程度で食べきれる量が目安です。また食べ残しに気づいたら、その都度網ですくうとコケに回る養分を減らすことができます。
水槽用のコケ抑制剤を使う
水槽用のコケ抑制剤を使うのも方法です。
コケ抑制剤には、飼育水に直接添加するタイプやろ過フィルターに仕込むタイプなど様々な種類が販売されており、製品によって効果が出やすいコケの種類が異なりますので、水槽の状態に合わせて適切な抑制剤を選びましょう。
ただし、コケ抑制剤の中には水草や水質に影響が出るものがありますので、使用前に注意書きをよく確認してください。
最近はベルテックジャパンの『Bioコケクリア』のような、コケ以外のものへの影響が少ないタイプの抑制剤が登場しており、以前よりも活用できる水槽の幅が広がっています。
藍藻は直接手で取り除く
弱アルカリ性の水槽で藍藻が発生した時は、手や網ですくって取り除くことをおすすめします。
藍藻は食べてくれる生体が少ない上に完全に除去するのが難しく、一度取り除いても繰り返し発生するケースが少なくありません。
繁茂が進むと水槽をリセットしなければならない状況に追い込まれる可能性もあるため、早い段階で対処しましょう。
まとめ:弱アルカリ性水槽のコケ取り生体8選!pHが高い水槽におすすめの対策!

弱アルカリ性の水槽でも活躍するコケ取り生体と、コケを抑制する対策について解説しました。
水質がアルカリ性に傾くと水草やコケ取り生体が調子を崩して、コケが繁茂しやすくなります。また、弱アルカリ性の水質では藍藻を発生させるシアノバクテリアが活発になりやすいのも問題です。
コケの除去や抑制にはプレコや貝類などのコケ取り生体を導入しましょう。特に貝類は酸性の水質だと貝殻が傷んで短命になりやすいため、アルカリ傾向の水質でこそ活躍する品種も多いです。
pHが高めの水槽でも、コケ取り生体を飼育して美しいアクアリウムを維持しましょう。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。


 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談
お悩み相談


























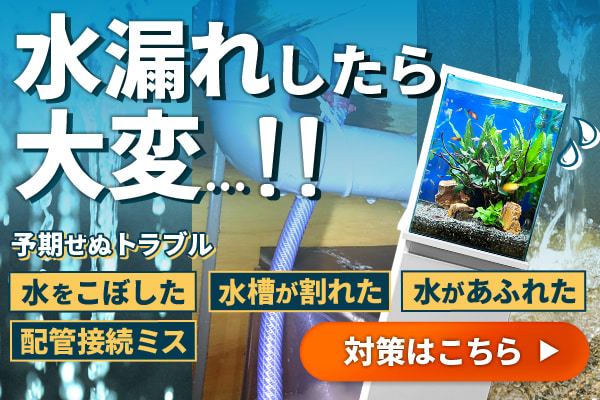
![(熱帯魚)ミニブッシープレコ (約3-5cm)<2匹>[生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/516sTABy2kL._SL500_.jpg)

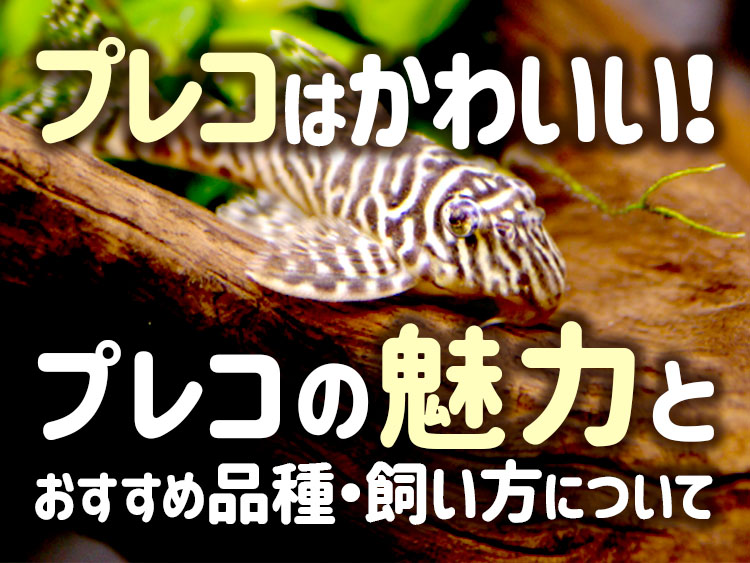




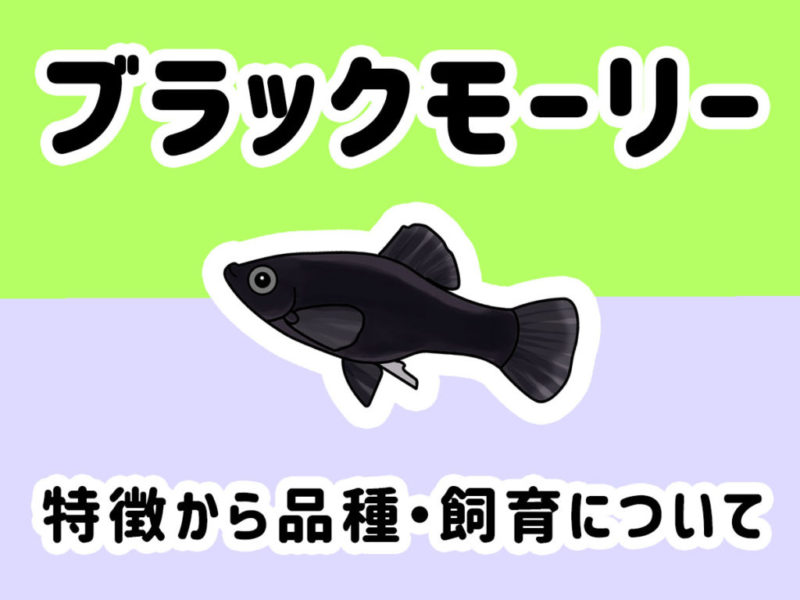




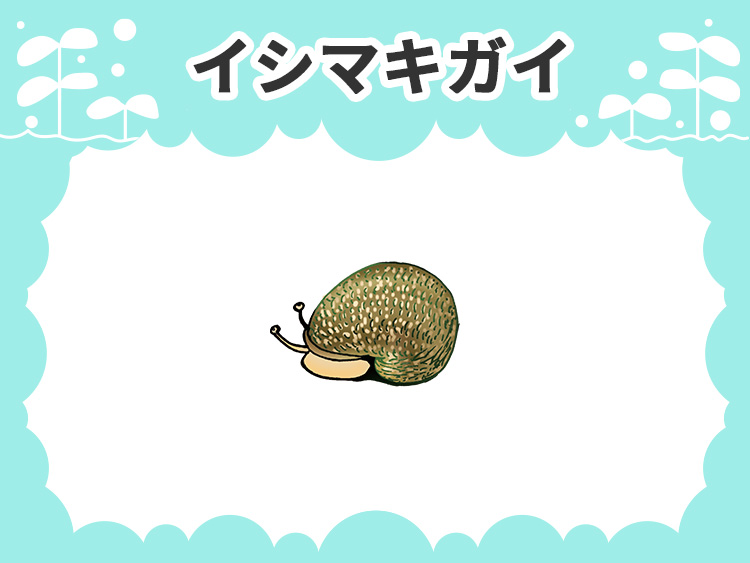



![(貝)フネアマ貝 (約2cm)<1匹>[生体]](https://m.media-amazon.com/images/I/51M-yYxJlRL._SL500_.jpg)