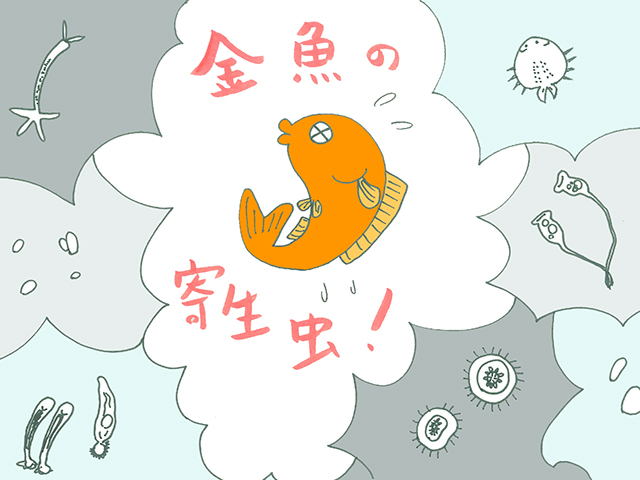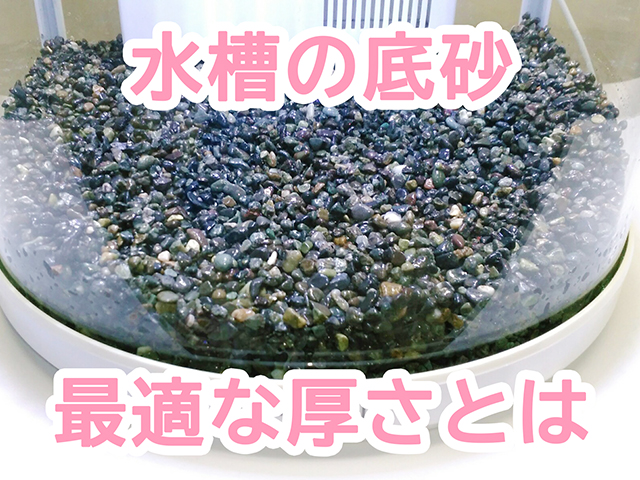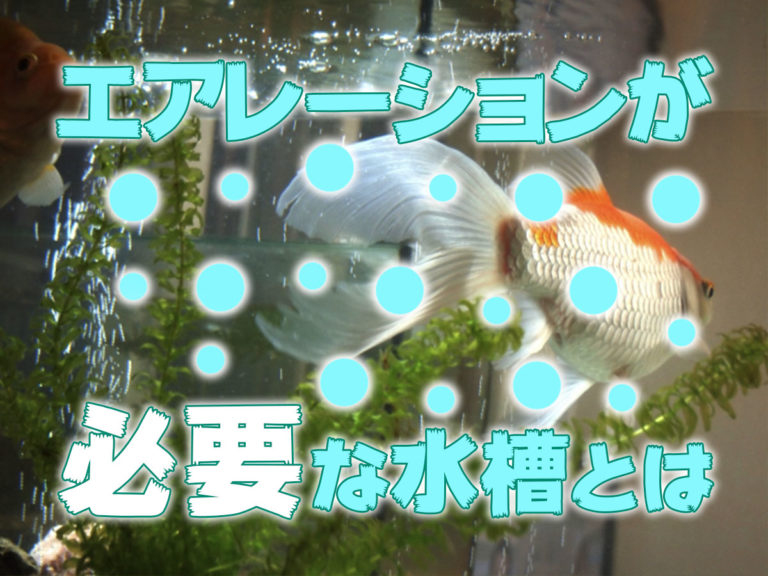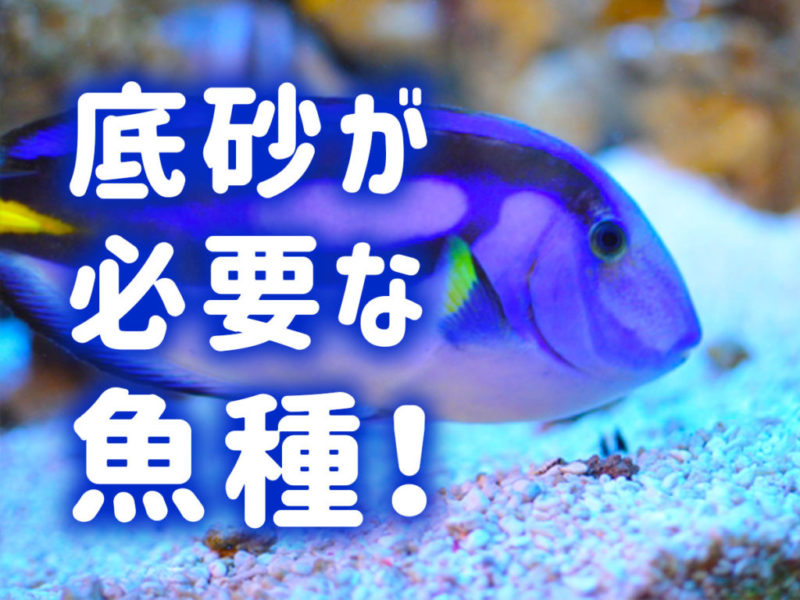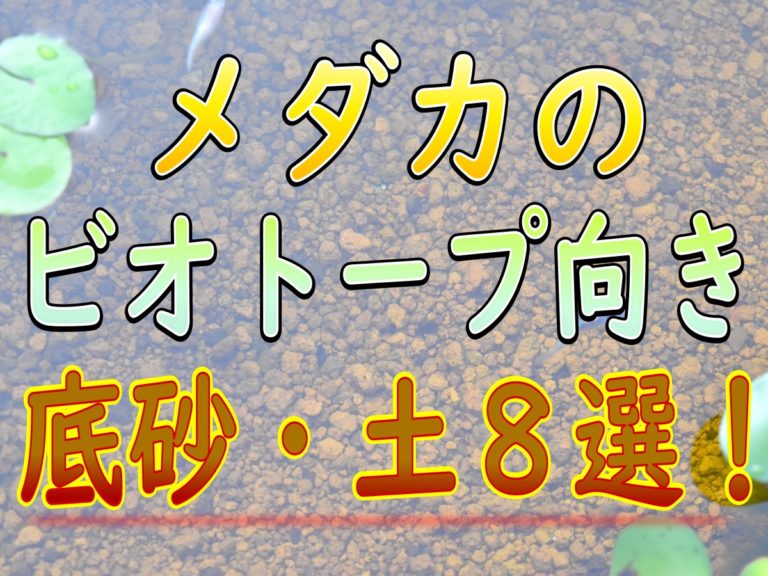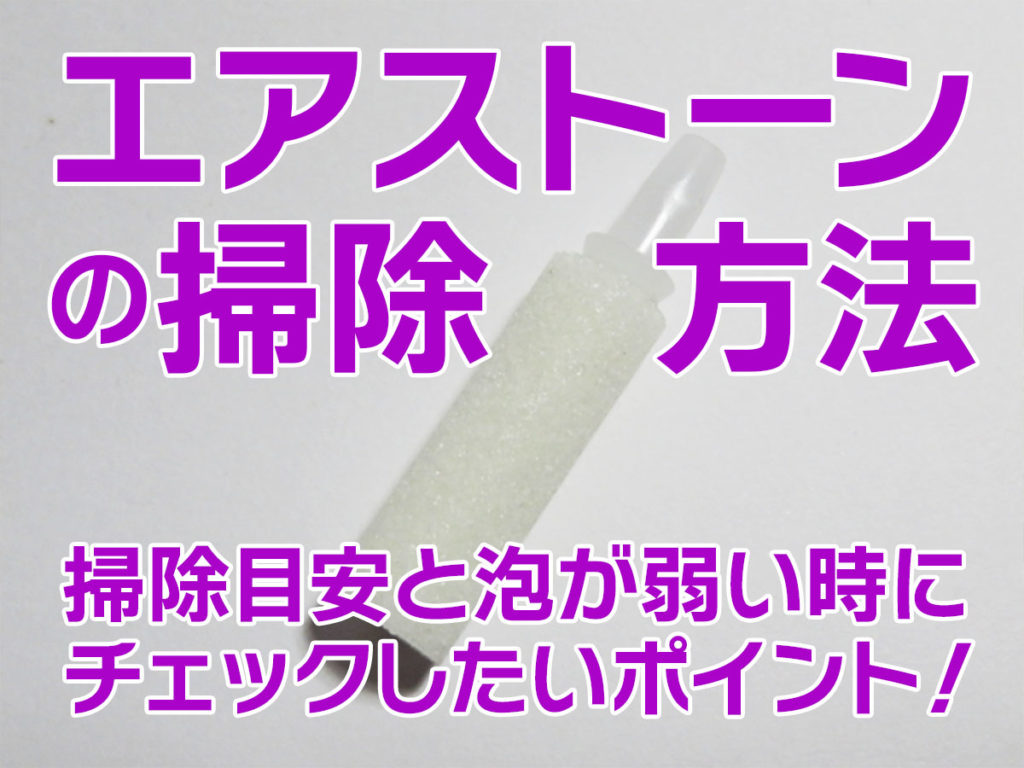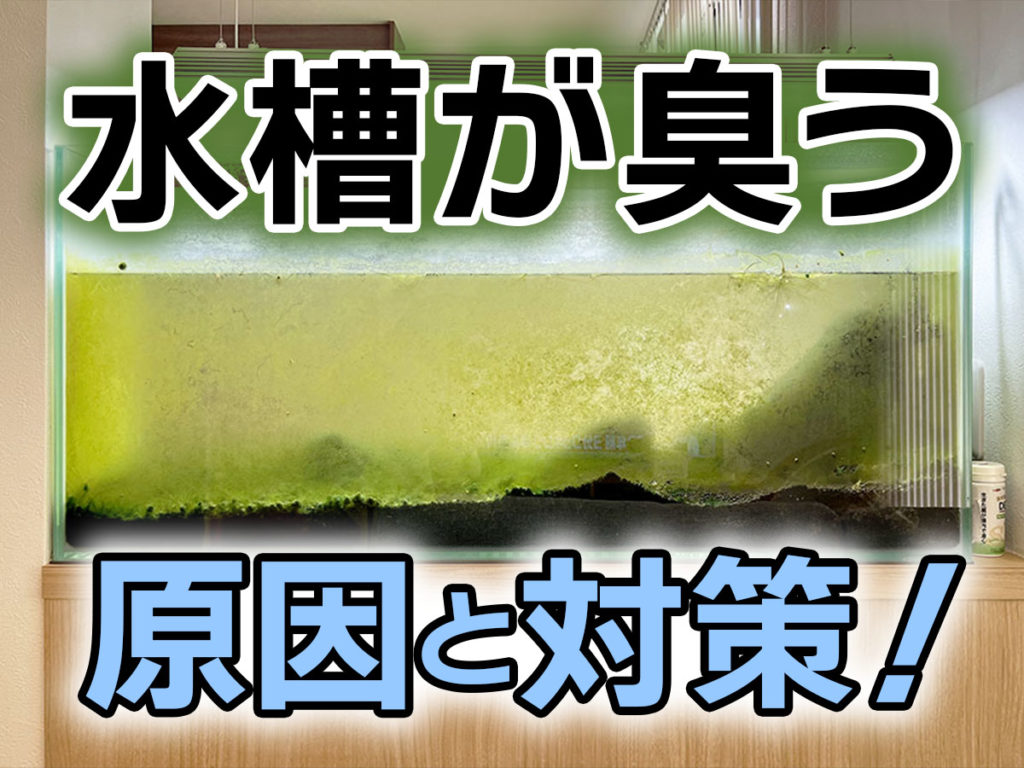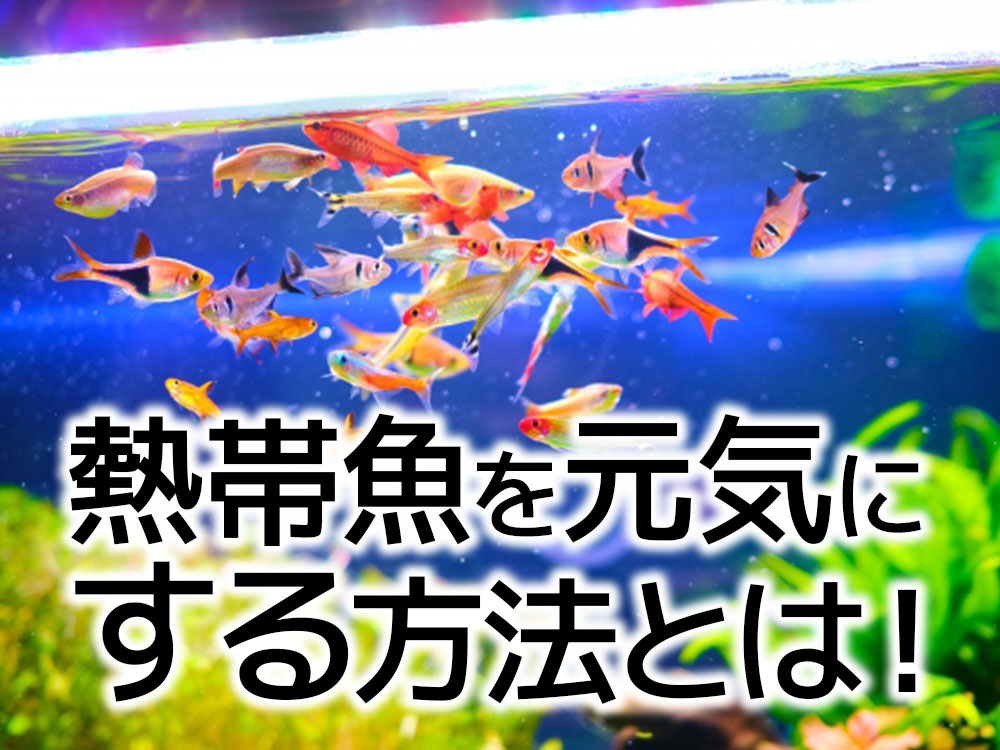魚が病気になった水槽の底砂メンテナンス法!水質を改善する方法を解説

投稿日:2025.07.02|
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
病気が発生した水槽は、多くの場合水槽内の環境に問題を抱えている可能性が高いです。
水換えやメンテナンスが足りていなかったり、水質や水温が変化してしまっていたりといったことから、水中の雑菌が繁殖するとストレスで弱っている個体が病気にかかりやすくなります。
特に水槽の底砂は汚れが溜まりやすく病原菌の温床になることも多いので、水槽内で病気が発生したら、病魚の治療と並行して底砂のメンテナンスを徹底的に行い、水槽環境を改善しましょう。
今回のコラムでは、魚が病気になった水槽の底砂メンテナンスが大切な理由と、水質改善に繋がるメンテナンスの方法について解説します。
底砂の定期的な掃除は病気予防にも最適です。効果的な底砂のメンテナンス方法をマスターして、魚が病気になりにくい水槽を作りましょう。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとに病気が発生した水槽の底砂メンテナンスを解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
病気が発生した水槽は、水槽内の特に底砂に菌や汚れが溜まっている可能性が高く、放っておくとどんどん病気が広まっていってしまいます。
病魚の治療と合わせて、本水槽の環境改善に取り組み、病気の連鎖を食い止めましょう。
ここでは、実務経験から得た知識をもとに、病気が発生した水槽の底砂メンテナンスを解説します。
魚の病気は底砂に原因がある?

魚の病気が発生する原因は様々ありますが、大きな要因となる可能性が高いのが底砂です。
そこでまずは、底砂が病気の原因となると言われる理由と、底砂掃除の重要性について解説します。
病気の原因が潜んでいる可能性がある
硝化バクテリアの住処になることからもわかる通り、水槽の底砂は微生物が定着しやすい条件を備えています。
しかしこれは良いバクテリアに限った話ではなく、管理を怠ると水槽に悪さをする病原菌や雑菌の温床になってしまうことがあるのです。
底砂は魚の排泄物や餌の食べ残しなどの有機的な汚れが沈殿しやすく、掃除をしていないと溜まった汚れを養分として菌類が増殖していきます。
また、稀に水槽内に持ち込まれた寄生虫が底砂内に潜んでいて弱った魚に感染することも。
このように魚が病気になってしまった水槽は底砂に何かしらの原因がある可能性が高いことから、水換えと同時に底砂メンテナンスを徹底するのがおすすめです。
病気にならない清潔な底砂を目指そう
病気や水質の悪化を予防するには、底砂を定期的に掃除して清潔に保つことがとても重要です。
そもそも底砂は、pHを安定させたり水の臭いや汚れを吸着したりといった水槽に良い効果をもたらしてくれるアイテム。しかし、汚れが溜まると底砂が本来持っている効果も十分に発揮できなくなってしまいます。
ビオトープなど自然なサイクルの再現度が高い飼育環境では状況が異なりますが、室内水槽の場合は、水換えと合わせて優先的にメンテナンスを行いたい箇所です。
しっかり掃除をして底砂を清潔に保つことが、健全な飼育を続けるコツと言えるでしょう。
病気が発生した水槽の底砂掃除法

ここからは、魚が病気になった水槽の具体的な底砂メンテナンス方法をご紹介します。
水槽内で病気が発生したら、通常の底砂メンテナンス以上に徹底的な掃除が必要です。
また底砂の敷き方や扱いを見直すことで、雑菌や汚れが溜まりづらい病気を予防できる底砂に改善できます。
底砂をしっかり掃除して、病気の原因となる菌類を効果的に取り除きを水槽環境を整えましょう。
クリーナーで汚れを吸い出す
まず、底砂の中に溜まった汚れを排出するため、クリーナーポンプを使って全体を丁寧に掃除します。
クリーナーポンプは、底砂内に溜まった汚れや細菌を水と一緒にダイレクトに吸い出すことができるため、見た目から明確な効果を実感できますし、汚れた水も捨てられて一石二鳥です。
普段から水換えの時にクリーナーポンプを使って掃除をしておけば、病気が発生しにくい環境に近づけることもできるでしょう。
ただし、クリーナーポンプを使った掃除法は溜まった汚れを吸い出すものであり、底砂が汚れるのを防ぐような根本的な解決には至りません。
汚れの原因を見つけて解消しないことには、いくら掃除をしてもすぐに元の状態に戻ってしまう可能性があることを頭に入れておいてください。
底砂の厚さを調整する
同じ水槽で病気が繰り返し発生するときや、飼育水に嫌な臭い・濁りなどのトラブルが頻発するときは、底砂の厚みを見直してみてください。
底砂を厚く敷きすぎていると通水性が低下し、汚れや菌が溜まりやすくなりますし、底砂の中が酸欠状態になるとエロモナスなどの嫌気性細菌の増殖に繋がります。
底砂の厚みを決めるときは、砂の内部に飼育水が行き届くように調整するのがポイントです。
水草を植えている場合は、水草の根張りに合わせて3~5cm以上の厚みが必要ですが、水草を植えておらず砂に潜る魚も飼育していないならば、底砂は1cm程度の厚みでも問題ありません。
フンが多い金魚やアロワナ、水質に敏感なディスカスなどの熱帯魚は、底砂を敷かないベアタンクで飼育する方が水質が安定しやすくなることもあります。
海水魚水槽の場合は、ライブロックによる水槽底面への負担を減らすために3~10cmほどの厚みで敷くのがおすすめですが、メンテナンスの際に底砂を巻き上げない=底砂内の菌を水槽内に拡散しないよう、作業の仕方には注意が必要です。
天日干しする
水槽内で寄生虫や藍藻が蔓延してしまったときは、底砂を一度取り出して水道水で良く洗浄した後に、天日干しをして殺菌するのがベストです。
底砂のリセットともいえるこの方法では、底砂の中で活動していた良いバクテリアも一緒に死滅してしまいますが、硝化バクテリアはろ過フィルターなどにも定着していますので、水槽全体をリセットするよりは影響を抑えられるでしょう。
底砂の状態をクリアにできるため、病気の再発を抑えて安全性を高める効果は非常に高いです。
エアレーションをする
底砂の状態改善にはエアレーションが有効です。
水中の溶存酸素量が増えることで、酸素を嫌う底砂の中の嫌気性菌の勢力を弱めることができます。
また、エアーポンプに接続して使用する底面式フィルターや投げ込み式フィルターも非常に効果的。エアレーションと同等の酸素供給力が見込める上に、水流で底砂を適度にかき混ぜることができるため、通水性も大きく向上します。
お掃除生体を導入する
底砂についたコケや汚れは、エビや貝類、ドジョウなどのお掃除生体の良い餌になります。
特に底砂を掘り返して餌を探す習性を持つドジョウやナマズの仲間は、定期的に砂を掘って撹拌してくれるため、通水性が上がって汚れが溜まりづらい清潔な底砂を保つのに一役買ってくれるでしょう。
ただしこのような底物の生体は、汚れた底砂の悪い影響をダイレクトに受けてしまうため、病気が発生してすぐの水槽では体調に十分に注意してください。
また、水質が悪化するほど状況が悪化している底砂をお掃除生体だけで改善するのは不可能ですので、掃除やメンテナンスのサポート役と考えるのが適切です。
底砂を変更したほうがいい状態とは

水槽の状態によっては、底砂のメンテナンスをしながら時間をかけて状態を改善していくよりも、底砂を取り換えてしまったほうが良い場面があります。
ただ、底砂をすべて取り換えるということは底砂に付着した硝化バクテリアをすべて失うことと同意義のため、メンテンナンスで改善が可能なのか交換が必要なのかを慎重に判断することが大切です。
ここでは、底砂を交換するべきと考えられる水槽の状態を解説します。
ソイルが崩れて通水性が悪いとき
水槽に敷くだけで水草やカラシン類に適した弱酸性の水質を作ることができるソイルですが、使用期間が長くなると粒が崩れてしまうというデメリットがあります。
ソイルの粒が崩れると底砂内の通水性が低下して、水草の根張りも悪くなるため交換が必要です。
粒が大きめのソイルを上に載せることで継続使用も可能ですが、厚みが増して崩れた部分に嫌気性菌の増殖が懸念されるため、長期的な使用は避けてください。
粒が崩れていくソイルは1年ほどでの交換が推奨されており、定期的な入れ換えが必要であることを覚えておきましょう。
藍藻が生えたとき
底砂に藍藻が生えてしまったときも交換を検討するタイミングです。
金魚やお掃除生体を飼育している場合は、食べてきれいにしてくれる可能性もありますが、繁殖のスピードが速いと処理が追い付かず、繁茂した藍藻から異臭や毒素が発生する危険があるため、交換してしまったほうが安全でしょう。
ちなみに、先程も触れた通り、藍藻が生えた底砂は良く洗浄して天日干しすることで再利用が可能ですので、余裕があれば挑戦してみてください。
レイアウトや飼育生体を変更するとき
病気とは直接関係ありませんが、レイアウトや飼育生体を変更するときにも底砂の交換が必要になります。
鑑賞面において底砂は全体の印象を決定づける重要な要素となるため、なんとなく水槽に飽きてきたといったときは底砂の色を変えてみると、ガラッと雰囲気が変わって新鮮です。
また、底砂にはpHをコントロールする効果があるため、飼育生体を変更・追加する場合は、生体に合わせて底砂の変更が必要になる可能性があります。
淡水→海水のような大きな仕様変更はもちろんですが、同じ淡水でも弱酸性~中性を好む熱帯魚と中性~弱アルカリ性よりの魚を混泳させたいときなどは、底砂を変更してpHを調整する工夫が必要になるでしょう。
底砂の変更はそれなりに労力がかかる作業ですので、飼育計画をしっかり立てて水槽を管理していくことが大切です。
まとめ:魚が病気になった水槽の底砂メンテナンス法!水質を改善する方法を解説

魚が病気になってしまった水槽の底砂には、病気の原因となる菌や汚れが蓄積している可能性が高いです。
そのため、病気が発生したら魚の治療と並行して、本水槽の底砂のメンテナンスに取り組みましょう。
まず、基本の掃除としてクリーナーポンプを使って底砂の汚れを徹底的に吸い出します。
底砂を厚く敷きすぎていると汚れが溜まりやすくなるため量を調整したり、エアレーションやお掃除生体を取り入れて底砂の通水性を良くしたりといった方法も、状態改善に有効です。
寄生虫や藍藻が蔓延してしまった場合は、底砂を取り出してよく洗ってから天日干しをしてください。
底砂は鑑賞面でも飼育面でも役立つ便利なアイテムですが、清潔に管理していないと逆効果になることも少なくありません。
底砂のメンテナンスを徹底して、魚が病気になりにくい飼育環境を整えましょう。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。



 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談
お悩み相談