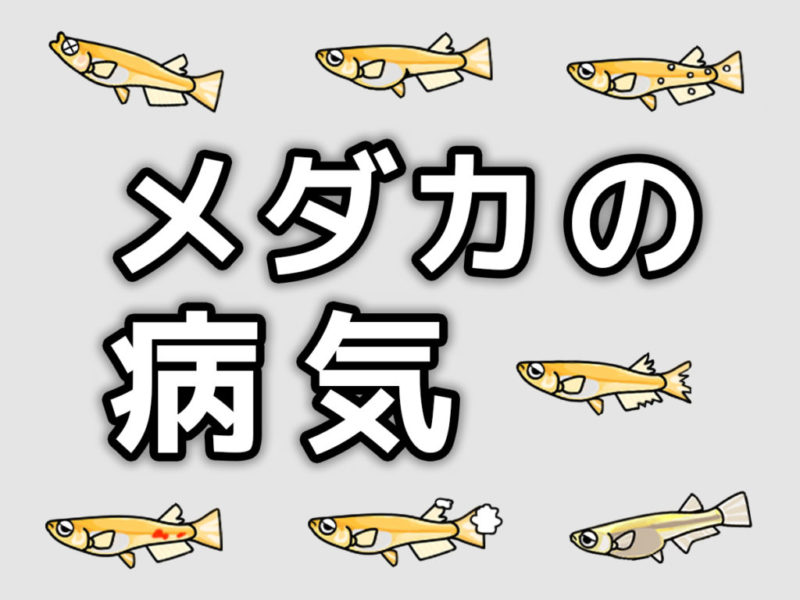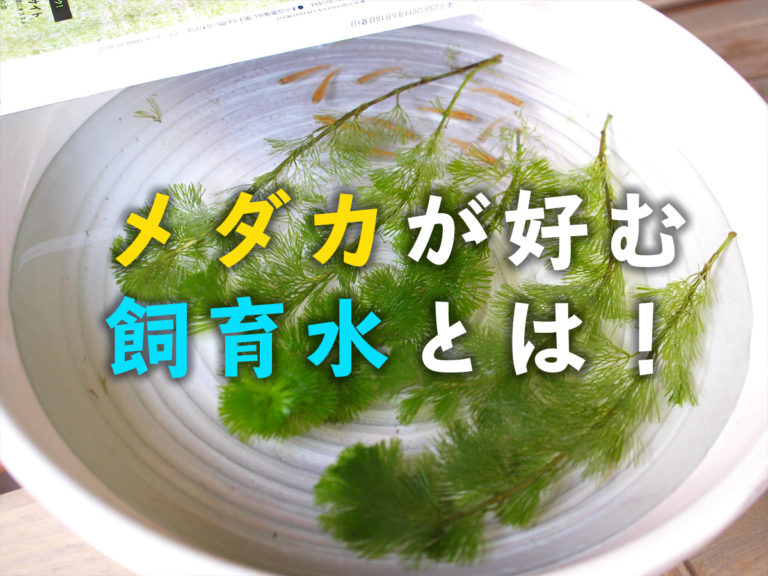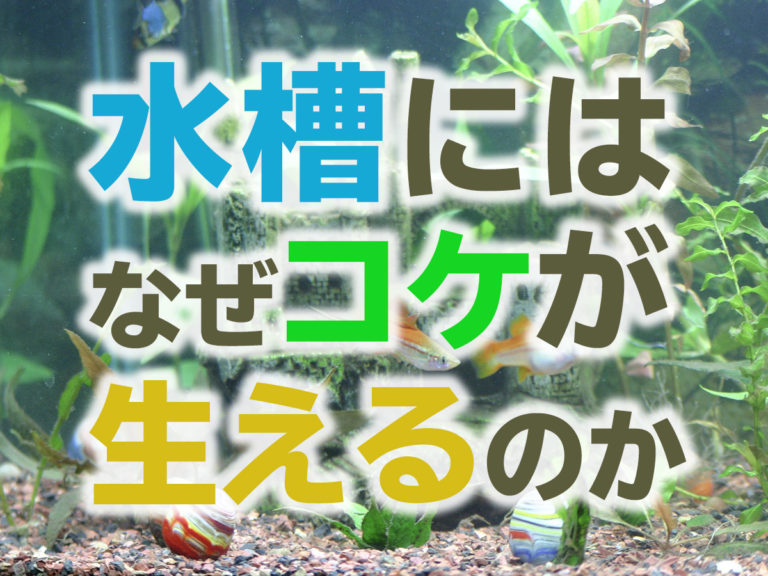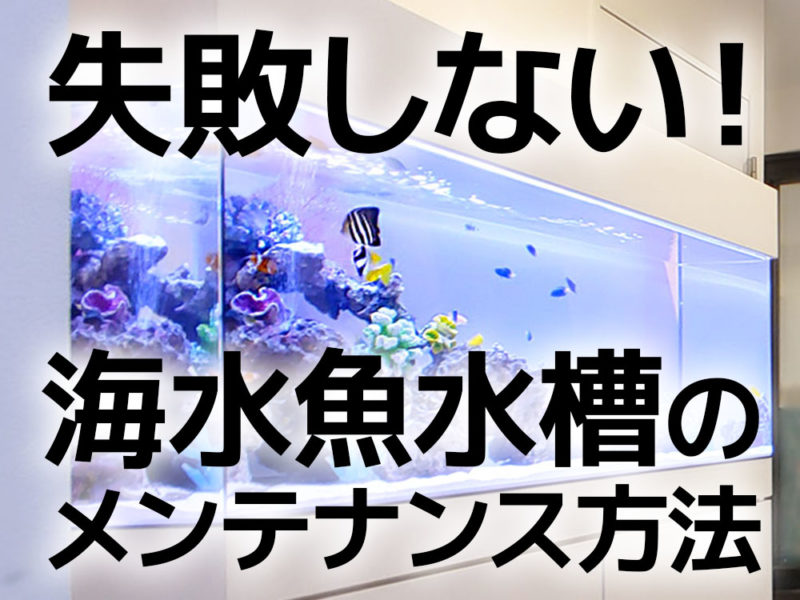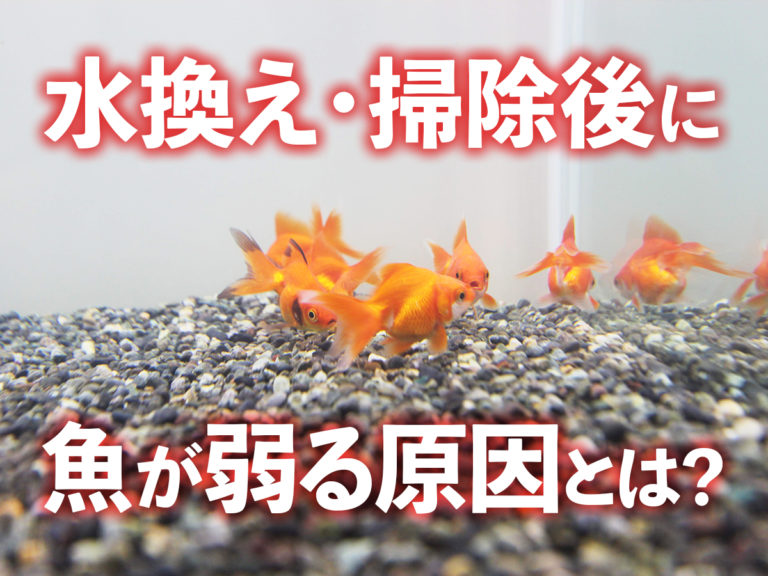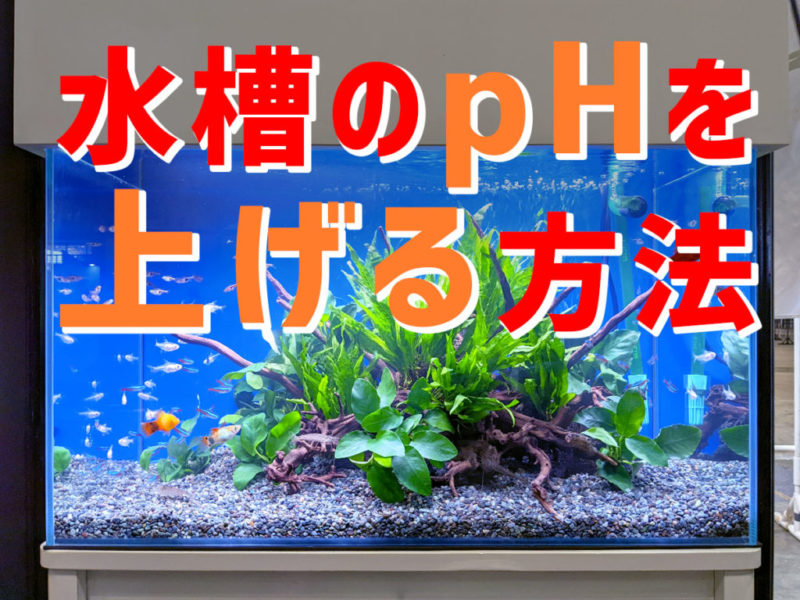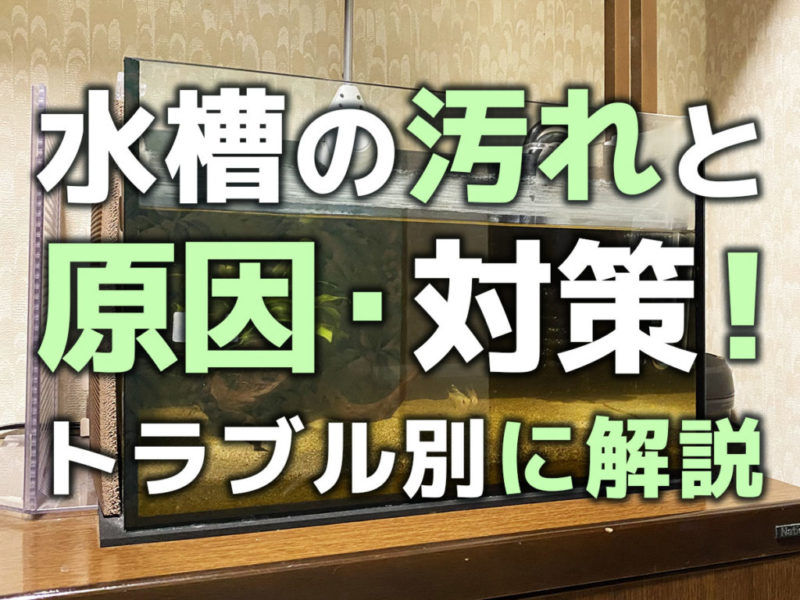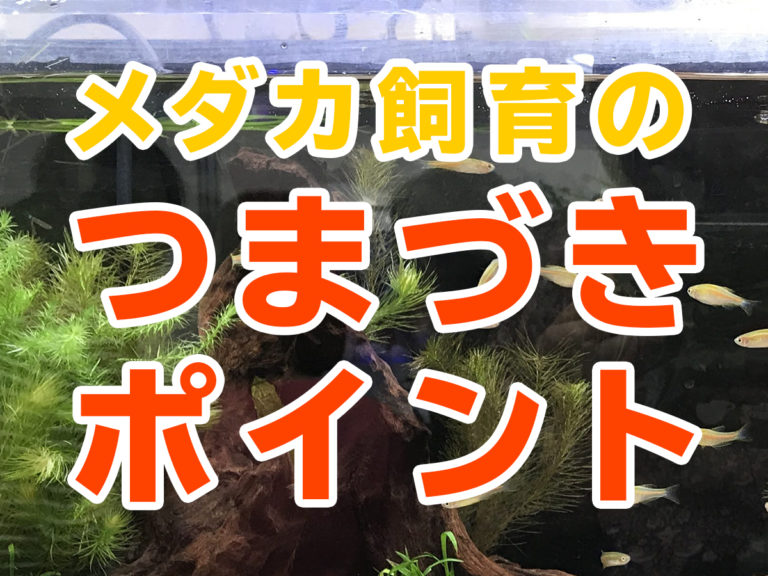硝酸塩から魚を守れ!硝酸塩の魚への影響・症状と、対策を解説します!

投稿日:2023.04.24|
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
アクアリウムを管理していると、硝酸塩という言葉を聞くことがあります。
「汚れた水には硝酸塩が溜まっている」
「硝酸塩の値が高いと魚が体調を崩す」
など、何となく熱帯魚に悪いものというイメージがある方は多いと思いますが、では、硝酸塩がどうして水中に溜まるのか、生き物にどの様な影響を与えるのかと聞かれると具体的に説明するのは意外と難しいものです。
そこで今回は硝酸塩について、水中に溜まる理由や生き物に与える影響、減らす対策などをご紹介します。
硝酸塩を正しく知ることで、きれいなアクアリウムを維持しやすくなります。魚達の健康管理にも役立ちますので、ぜひご覧ください。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとに硝酸塩が魚に与える影響と対策を解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
- 硝酸塩とは、バクテリアがフンなどから出るアンモニアを分解して、最後に残る成分!生き物を飼育すると水槽にたまっていくよ
- 硝酸塩はアンモニアより低毒性だけど、無害ではない!コケが増えたり魚のヒレに穴が開くなど、長期的にみるとコンディションを損なうことがある
- 水換えは硝酸塩を排出する、効果的なメンテナンス法!新しい水を加えることで飼育水のバランスもとりやすくなるよ
- 水換え以外もある!硝酸塩を減らす方法水草は硝酸塩を吸収することができるよ!
水の汚れとも表現される硝酸塩は、生き物を飼育していると水中に自然と蓄積していきます。
毒性は低いですが、硝酸塩の濃度が高い水は生体に悪影響を及ぼすこともあるため、水換えなどで濃度をコントロールしましょう。
ここでは、実務経験から得た知識をもとに、硝酸塩が魚に与える影響と対策を解説します。
硝酸塩とは

硝酸塩は硝酸イオンと金属イオンから成る化学物質の総称で、アクアリウムでは、水を綺麗にしてくれる硝化バクテリアが生成する最終成果物のことを指します。
ろ過バクテリアの働きと硝酸塩
硝化バクテリアは、水の汚れを分解してきれいにしてくれる、水槽を管理する上で欠かせない心強い存在です。
水槽で魚を飼育していると、フンや餌の食べ残し、傷んだ水草などで水が汚れていきます。この汚れの主な成分はアンモニアという、非常に毒性の強いものです。
アンモニアが水中に溜まってしまうと、とても生き物が住めるような環境ではなくなってしまいますので、どうにか毒素を薄めなければなりません。そこで頼りになるのが生物ろ過、つまり硝化バクテリアの働きです。
硝化バクテリアは水中に溜まるアンモニアを餌として吸収して分解し、亜硝酸塩に変えてくれます。この亜硝酸塩を更に別の硝化バクテリアが分解して硝酸塩に変換、硝酸塩を分解してくれるバクテリアはいないので、最終的に水槽には硝酸塩が残ります。
最終成果物である硝酸塩は、アンモニアに比べれば毒性がかなり低いものの、全く無害というわけではありません。
濃度が濃くなると魚が体調を崩してしまいますので、何らかの方法で排出する必要があります。
硝酸塩が水槽に及ぼす影響

アンモニアに比べれば毒性が低いとされる硝酸塩ですが、濃度が高くなると水槽環境や飼育している生体に悪い影響が出てきます。
- ヒレにピンホールができやすくなる
- 病気になりやすくなる
- 寿命が短くなる
- コケが生えやすくなる
などは硝酸塩が原因となるトラブルの最もたる例です。硝酸塩が水槽に及ぼす影響を知っておきましょう。
ヒレにピンホールができやすくなる

金魚やグッピーなど、ヒレの大きな魚に良く見られる症状で、ヒレに針でつついたような小さな穴…ピンホールができることがあります。
ごく小さな穴ですので、すぐに命に関わるというわけではありませんが、ピンホールを放っておくと穴が広がって、尾ぐされ病などの重篤な病気に進行することもあるため、対処が必要です。
ピンホールができる原因ははっきり解明されていないのですが、硝酸塩の濃度との関係が指摘されており、硝酸塩が溜まり水質が悪化した環境では、ピンホールができやすいと言われています。
病気になりやすくなる
硝酸塩は生体にとって微弱ながら毒物であり、それが蓄積した環境が続くことは、少なからずストレスになります。
ストレスは体調不良の元、それは人間も魚も同じです。
ストレスが掛かった魚は免疫力が下がり、健康であれば問題ないような水中の常在菌にも感染して病気を発症してしまうようになります。
そのような状態の魚は回復力も落ちており、より重篤な症状に陥りやすくなるのです。
水質が変わってしまう
硝酸塩はその名の通り酸性の性質を持ちますので、量が多いとpHを低下させて水質を酸性に傾けます。
一般的に熱帯魚は弱酸性、メダカは中性~弱酸性、金魚は中性~弱アルカリ性を好むとされており、極端な酸性を好む魚はかなり少数派です。
生き物に合わせた水質を保つことは健康を守る上でとても大切で、合わない水で飼育を続けると、体に負担がかかって、体調不良につながることも。
硝酸塩が溜まるとpHはどんどん低下していき、気づいたときには理想とは全く違う水質になっていたということも少なくありませんので、常に硝酸塩の濃度と水質に気を配りましょう。
コケが生えやすくなる

詳しくは後述しますが、硝酸塩は植物の養分となります。そのため、水草の成長には適度な硝酸塩が必要なのですが、これは厄介なコケにも同じこと。
硝酸塩が多い環境はコケが繁茂しやすくなるのです。
一般的に、硝酸塩濃度が25mg/Lを超えるとコケが発生しやすくなると言われています。
コケが増えてしまうと除去するのにかなりの手間がかかりますので、硝酸塩の管理して、コケが繁茂しない環境を作ることが重要です。
硝酸塩を減らすには?

自然環境であれば、水中に硝酸塩が発生してもすぐに流されて、一か所にとどまることはありません。そもそも川や池は水の量が莫大ですので、生体に影響を及ぼすほど硝酸塩の濃度が高くなること自体がほぼないでしょう。
一方、閉じられた水槽内では、放っておくと硝酸塩がどんどん溜まっていきますので、魚に影響が出る前に何らかの方法で排出するか、発生量を抑える必要があります。
水槽内の硝酸塩を減らすには、以下の4つの方法が効果的です。
- 水換えを行う
- 水槽内に水草を植える
- 海水水槽はろ過を強化する
- 水槽内の生体数を減らす
水換えを行う
硝酸塩を減らす方法で、一番即効性があるのが水換えです。
硝酸塩が蓄積した水を捨てて新しい水を入れることで濃度を薄める、という実に単純な図式ですが、何より高い効果が得られます。
定期的に水換えをしていれば、基本的に硝酸塩が溜まり過ぎてしまうようなことはありませんので、面倒でも欠かさず行うようにしてください。
水換えの適切な頻度は、1~2週間に1度、全体の1/3の水量を交換するのが一つの目安です。
ただ、飼育している生体の数や水槽のサイズによって最適な頻度は異なりますので、最初は水質検査薬で硝酸塩を測定して、水換えのタイミングを見極めると良いでしょう。
何度か繰り返していれば硝酸塩が溜まるペースが掴めてきます。
水槽内に水草を植える
先ほど軽く触れましたが、植物は硝酸塩を養分として吸収してくれますので、水槽に水草を入れることで硝酸塩を減らすことができます。
硝酸塩を完全に無くすことはできませんが、硝酸塩が溜まりづらい環境になり、水換えの頻度を減らすことが可能です。
そもそも水草が水槽にもたらす効果は多く、水質浄化作用(硝酸塩の吸収)以外にも、
- アクアリウムの鑑賞性が上がる
- 生体の隠れ家や産卵床になる
- 生体のおやつになる
など様々なメリットがあります。水草を上手に活用して、きれいなアクアリウムを無理なく維持していきましょう。
海水水槽はろ過を強化する
海水水槽には水草を植えることができませんので、基本的には水換えで硝酸塩に対応していくことになります。
しかし、それでは水質が安定しない場合やあまりに頻回な水換えが求められるようなときは、水槽のろ過を一度見直してみましょう。
ろ過フィルターのスペックを上げたり、プロテインスキマーを取り付けたりなどして、ろ過システムを強化します。
また、サンゴなどの硝酸塩に特に敏感な生体を飼育している水槽では、硝酸塩除去剤を使って硝酸塩を無くすのも一つの方法です。
水槽内の生体数を減らす
あまりに硝酸塩が溜まりやすいと感じるときは、飼育している生体の数を見直してみましょう。
硝酸塩の発生原因は生体の排泄物や餌の食べ残しなどですので、魚の数が多いと硝酸塩が溜まるスピードが速くなります。
硝酸塩が溜まりやすく水換えを頻繁に行う必要がある場合は、水槽を分けたりサイズアップをしたりして、水量に余裕を持たせると状況を改善できることが多いです。
また、水槽の総水量に対して生体の数が多すぎることを過密飼育と言いますが、過密気味の水槽は、水が汚れやすいだけでなく、酸欠や体調不良、魚同士の小競り合いなどのトラブルが起こりやすいです。
魚の飼育数は、 魚の体長1cmにつき水が1Lが目安とされていますので、新しい生体を迎える前に確認するようにしましょう。
まとめ:硝酸塩から魚を守れ!硝酸塩の魚への影響・症状と、対策を解説します!

今回は硝酸塩が水中に溜まる理由や生き物に与える影響、減らす対策などを解説しました。
硝酸塩はバクテリアが水中の有機物を分解した際に発生するもので、毒性は低いですが水中に蓄積すると、生体に悪影響が出ることがあります。
排出するには、水換えをして水中の硝酸塩の濃度を下げるのが一番効果的ですが、他にも水草を植えたり生体数を見直したりして、硝酸塩が溜まりづらい環境作りを心がけることが大切です。
硝酸塩の濃度をしっかりコントロールしながら、熱帯魚の長期飼育を目指しましょう。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。



 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談
お悩み相談