
金魚の松かさ病は不治の病なのか?原因と対策・治療方法!薬餌の有効性も解説

コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
金魚が発症する重大な病気として、松ぼっくり(=松かさ)状に鱗が開いてしまう『松かさ病(立鱗病)』が挙げられます。
確実な治療法が現在も見つかっておらず、症状が進行すると治すことのできない不治の病としても知られている病気です。
主な原因は水質悪化や消化不良などですが、飼育環境が悪化することで発症しやすくなります。
日頃から水槽をきれいに保ち餌を与えすぎないことで予防が可能です。
松かさ病の症状・予防についてや、少しでも快方に近づけるための治療方法を解説します。
目次
このコラムのポイントとプロアクアリストによる松かさ病の解説

このコラムは、東京アクアガーデンに在籍するアクアリストたちの経験・意見をもとに作成しています。
- 松かさ病は、鱗が立ち上がってしまう病気!細菌感染(運動性エロモナス)が原因松かさ病は、金魚だけでなく熱帯魚が罹ることもあるよ
- 松かさ病の治療は難しい。薬浴や塩水浴、そしてこまめな水換えで症状を抑えられるよ発症しないように予防することが大切!
- 松かさ病は適切にメンテナンスを行い、清潔な飼育環境を維持すれば予防が可能!水槽の掃除不足、消化不良、古くなった餌などで発症の確率が上がる!
- 松かさ病の詳しい症状を解説症状を知って予防しよう!
東京アクアガーデンでは、水槽設置・メンテナンス業務の中で、さまざまな生体を取り扱っています。
そのなかで、体調を崩したり病気を発症してしまう生体もいます。
松かさ病は魚の病気のなかでも大変重症ですので、予防が肝心です。
このコラムでは実務経験をふまえて松かさ病の対策・予防方法をご紹介していきます。
松かさ病とは
松かさ病は痛々しい見た目と症状の深刻さから、金魚飼育者の間では不治の病とされている病気です。
ここでは松かさ病の症状や原因などについて解説していきます。
症状と経過
重症化すると鱗が逆立ち、カサが開いた松ぼっくりのような見た目になります。『運動性エロモナス症』に含まれる病気です。
初期症状としては、鱗の一部が若干逆立ちます。体に内出血のような赤い斑点が見られることもあり、この状態を『赤斑病』と呼びます。
この段階では、餌食いや泳ぎには支障をきたさず、元気なことが多いです。
松かさ病の最初期は、体のラインが上から見て「すこしギザギザしているな」、と感じる程度です。
症状が進行すると炎症が悪化して便秘をするようになり、次第に鱗の開きも悪化します。
これは、腎機能に障害が出ているためとされており、エロモナスの感染によって内臓にダメージが出た状態と考えられています。
末期症状では水槽の底でじっとしていることが多くなり、個体によっては目が腫れあがる『ポップアイ』や皮膚炎などの松かさ以外の細菌感染症状が出てきます。
やがて鱗が開ききると、エラ機能などに不調が起こり息を引き取ってしまいます。
フンが排出できなくなると体内で腐敗が起きてさらに内臓へのダメージが加わり、回復不能になってしまいます。
現在では治療法がないため、予防が大切な病気です、
松かさ病の原因と要因

痛々しい姿で症状が進行する松かさ病ですが、原因は1つですが要因は複数あると考えられています。
この細菌は川や土壌、一般的な淡水水槽にも生息している常在菌のため、元気で正常な個体に悪影響をおよぼすことはまずありません。
魚たちがエロモナス菌に感染してしまう理由は、ストレスなどによる免疫低下が大きく関わっています。
免疫低下を引き起こす要因として考えられるのが、水質の悪化や餌の消化不良、混泳の失敗です。
水換え不足やフィルターの目詰まり、底砂を長期間掃除しないことでも起こります。汚れ(=過剰な養分)がたまれば菌も増えていきます。
消化不良は餌の与えすぎや古くなった餌を与え続けること、混泳の失敗は魚同士の相性が悪いことによるケンカやいじめが原因です。
こうした要因が総じて魚にストレスを与え免疫力が低下し、エロモナス・ハイドロフィラに感染しやすくなり、松かさ病を引き起こしてしまうのです。
しかし、運動性エロモナスの初期症状である『赤斑』を発見した段階で、適切なメンテナンスや薬浴を行えば防ぐことも可能です。
飼育生体の様子は常に観察し、おかしいと感じたらすぐに水槽掃除を行いましょう。
松かさ病はうつるのか?
結論から言うと、松かさ病はうつらないけれど、同じ飼育環境では他の個体も発症する可能性があります。
松かさ病の原因菌『エロモナス・ハイドロフィラ(運動性エロモナス)』は飼育環境が悪化したことで増えます。
つまり、免疫力が低い個体から発症しているだけで、すべての生き物がこの菌にさらされている状態と言えるでしょう。
松かさ病の治療方法
松かさ病は不治の病とも言われていますが、初期症状の段階で適切な治療をすれば回復する可能性もあります。
実際、東京アクアガーデンのスタッフの1人に、松かさ病の金魚を完治させた経験があります。ここでは、経験談をもとに治療方法を考えていきます。
塩浴とこまめな水換えが基本
松かさ病に見られる鱗の逆立ちや体のむくみは、エロモナス菌などが体内に感染し、水分代謝がうまくできなくなることによって起こると考えられます。
そのため鱗の一部が盛り上がっている程度の初期症状であれば、塩水浴で浸透圧を調整し、水分代謝をサポートしつつ、こまめな水換えで自己治癒力を高めてやれば、快方に向かうことが多いです。
塩水の濃度は0.5%(水1Lに対して塩5g)で、2日に1回水換え(全換水)をしながら様子を見ましょう。
使用は自己責任になりますが、最近ではエプソムソルトという入浴剤としても使われるバスソルトも、初期の松かさ病に効果があることが確認されてきました。
こちらの濃度は0.03%(水10Lに対してエプソムソルト3g)に調節し、通常の塩水浴と同じように2日に1回水換えをします。
エプソムソルト浴をさせる場合は、成分が100%硫化マグネシウムのものを使用しましょう。
塩水浴もエプソムソルト浴も、濃度を守ってこまめに水換えすることが大切です。
ただし、鱗が開ききっている重症の場合やポップアイを併発しているときは回復が難しいため、とにかく初期の段階で対処することが重要と言えます。
薬餌が効果的な場合もある
松かさ病は通常、エロモナス菌が体内(腸や筋肉など)に侵入することで発症します。
つまり薬の成分を腸まで届ける薬餌も、松かさ病に効果があるということです。
逆に言うと、薬浴など魚の体表を殺菌するような治療法では効果が薄く、回復しないことが多いので注意しましょう。
薬餌は作り方自体は簡単なのですが、薬の性質上、長期保存は難しいです。
だからといって薬餌を与えすぎると腸を傷めてしまいますし、症状が落ち着いてからも消化機能が回復せず餓死してしまうことも十分に考えられます。
薬餌は1日3粒を目安に与え、余った分は冷暗所で保存しつつ5日以内に使い切りましょう。
薬餌の詳しい作り方については以下の記事で解説しています。
松かさ病の予防方法

最後に松かさ病の予防方法ということで、
- 水槽を清潔に保つ
- 消化不良は慎重に治す
- 水温に気を付ける
という3つのポイントを解説していきます。
水槽を清潔に保つ
松かさ病を予防する上でもっとも大切なのは、水槽を清潔に保つということです。
特に金魚は底砂をつつく習性があるため、砂利の掃除は徹底的に行ないましょう。
ただし、注意したいのはろ過フィルターの掃除です。
ろ過フィルターは目詰まりを解消する程度のことであればこまめに実施するべきですが、ろ材を頻繁に洗ったりすると、生物ろ過に必要なバクテリアを減らしてしまいかねません。
ろ過装置のメンテナンスは2週間に1度くらいのペースにとどめておくのがおすすめです。
とはいえ、飼育水が臭ったり、病気が発生する飼育環境ではその限りではありません。
ろ材は良く洗浄し、飼育水も大幅に変えて環境を整えましょう。
消化不良は慎重に治す
金魚が白い糞やゼリー状の糞をする場合は、消化不良を起こし下痢をしています。
下痢の症状は松かさ病の原因菌でもあるエロモナス・ハイドロフィラが由来していることもあるため、早めに対処しましょう。
下痢症状が長く続く場合は、金魚の自己治癒力と抵抗力を高めつつじっくりと治す方法がおすすめです。
3日間ほどの絶食で糞を出し切らせてから1日1粒だけの給餌を開始し、確実に消化できるようになるまで粘りましょう。
こまめな水換えや生菌剤入りの餌を与えることも、消化不良を予防するのに効果的です。
水温に気を付ける
金魚の適水温は15~28℃とかなり幅広いのですが、高温すぎると酸素不足で金魚が疲弊し、低温すぎると消化機能が落ちてしまいます。
一方エロモナス菌は26~28℃で活性化する傾向にありますので、金魚水槽は24~25℃に保温しておくのがおすすめです。
まとめ:金魚の松かさ病は不治の病?原因と対策・治療方法!薬餌の有効性も解説

不治の病とも言われている松かさ病ですが、その原因は水槽のメンテナンス不足や極端な水温変動など、水質の悪化が大きく関係しています。
適度な水換えや掃除で水質を保ち、金魚の病気を予防しましょう。
また、松かさ病は重症化すると回復が難しいですが、初期の段階で気が付くことができれば完治が不可能ということはありません。
日頃からよく金魚を観察し、些細な変化を見逃さないことが大切です。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。


 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談
お悩み相談





























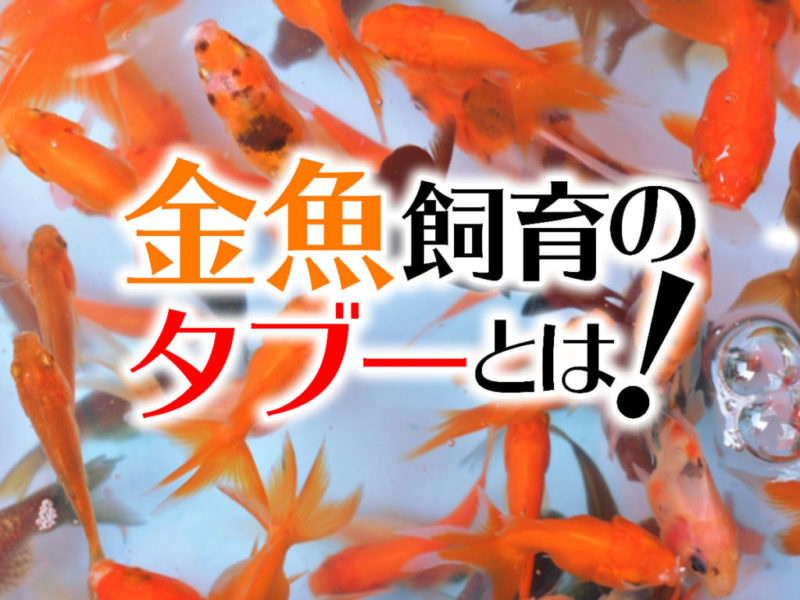

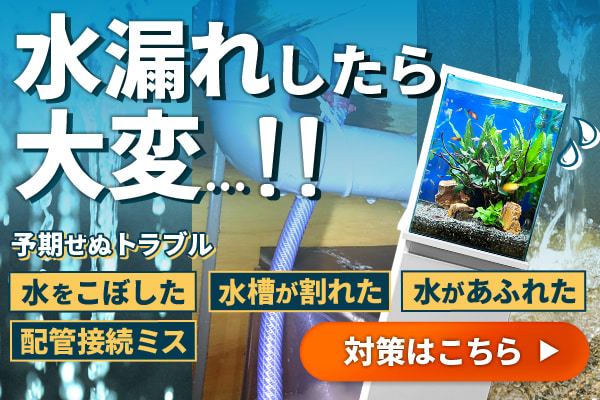





















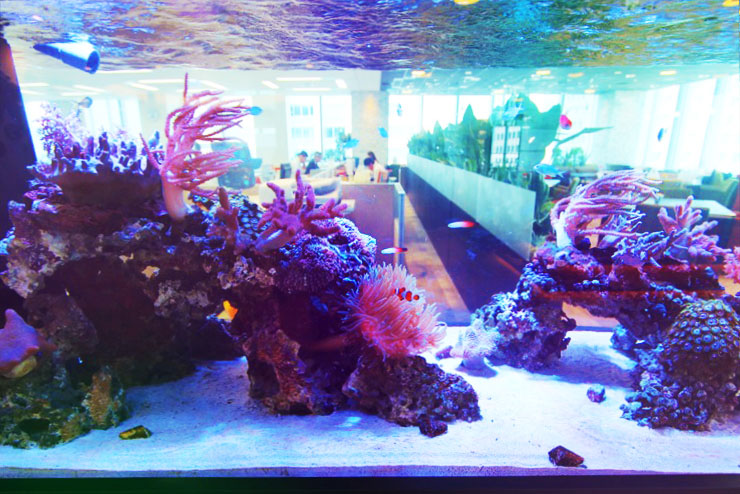

投稿されたコメントやご相談と回答
メダカがポップアイに罹ってしまいました。かなり目が腫れている感じです。取れそうです。重症ですよね?治療法を知りたいです。今は、塩水の中に移しています。他のメダカにも感染しますか?教えて下さい。
ポップアイは薬浴と薬餌で治療します。
症状が進んでいる場合は、観パラDかエルバージュエースでの薬浴を行いましょう。
原因菌であるエロモナスは水槽内に必ずいる常在菌です。水槽内が汚れていたり水質が悪化するとメダカの免疫力が負けて感染してしまいます。
まずは、水槽の底砂やフィルター掃除を徹底し、飼育水も一旦1/2程度換えると予防になります。
こちらのコラムもご参照ください。
・魚の目が飛び出た!ポップアイとは!厄介な病気の原因と対処法を考えます
https://t-aquagarden.com/column/pop_eye
よろしくお願いいたします。
松かさ病ですがグリーンFゴールドリキッドと塩浴で一週間様子を見てから今は塩浴だけにしましたがウロコは少しずつ閉じ始め赤虫とクロレラを食べた後6時間くらいして細かな糞が出始めてます。身体や顔は黒くなってますがこのまま塩浴だけで良いか?薬を使ったほうが良いか悩んでます。様子を見てると塩浴だけの方が泳げてますがグリーンゴールドFリキッドを使ってた時はエアーの側で眠ってました。それから薬餌はどのように作れば良いですか?
申し訳ございません。一つの症状に回答は1回までとさせていただいております。
5月15日に回答した際にご案内させていただいた、グリーンFゴールド顆粒のコラムの中で薬餌の作り方を解説しておりますので、ご参照ください。
グリーンFゴールドリキッドでも、同じ作り方です。
・幅広い病気に効く!グリーンFゴールド顆粒の効果と成分、使い方を解説
https://t-aquagarden.com/column/green_fg
何卒、よろしくお願いいたします。
松かさ病の治療について教えてください。
飼育環境は池(鯉共存)でした。
先日水面に浮かんだまま動かなかったので網で確保したところ生きていたので水槽に隔離。
鱗が毛羽立っていたのでネットで調べエルバージュエース+塩浴24時間
その後塩浴のみ(本日3日目)で様子を見ています。4日間絶食中です。
動いてはおりますが、鱗の改善はみられません。
薬浴は何日間隔でやって良いのでしょうか。
実際に拝見していないため、正確な回答ではないことをご了承ください。
薬浴は3日ほど間隔をあけて行います。
薬浴でおさまらない場合は、薬餌を与えるのが効果的です。
しかし与え続けると内臓にダメージがでやすいため、3回ほど与えて様子を見ましょう。
その際、水換えは毎日行います。それでも鱗が治まらない場合は、再び薬浴を行う、というように根気強く治療を続けます。
ただ、松かさ病は難治性であり、症状が軽くなるものの完治させるのは難しいです。
こまめな水換えで落ち着いた状態を維持しやすくなります。
薬餌については、こちらのコラムもご参照ください。
・幅広い病気に効く!グリーンFゴールド顆粒の効果と成分、使い方を解説
https://t-aquagarden.com/column/green_fg
・魚の休薬期間とは!魚病薬の切り替え方と薬浴を継続する方法
https://t-aquagarden.com/column/fish_intermission
よろしくお願いいたします。
お忙しい中、ご丁寧なお返事を有難うございました。
また、参照コラムまで教えて頂き感謝致します。
エルバージュエースは2度は使えないと、コラムに書かれていましたので
グリーンFゴールドに切り替えて投薬しようと思います。
今日の様子を見てみると少しですが鱗が寝ていました。
餌を試しに一粒(鯉用大粒タイプ)与えてみたところ食べてくれてました。
泳いではいるので、根気よく?付き合っていきたいと思います。
目指せ池戻し!です。
塩浴は2週間が限度ともネットで書かれていたので少々心配ですが
それまでに少しでも改善してもらえたらと思います。
有難うございました。