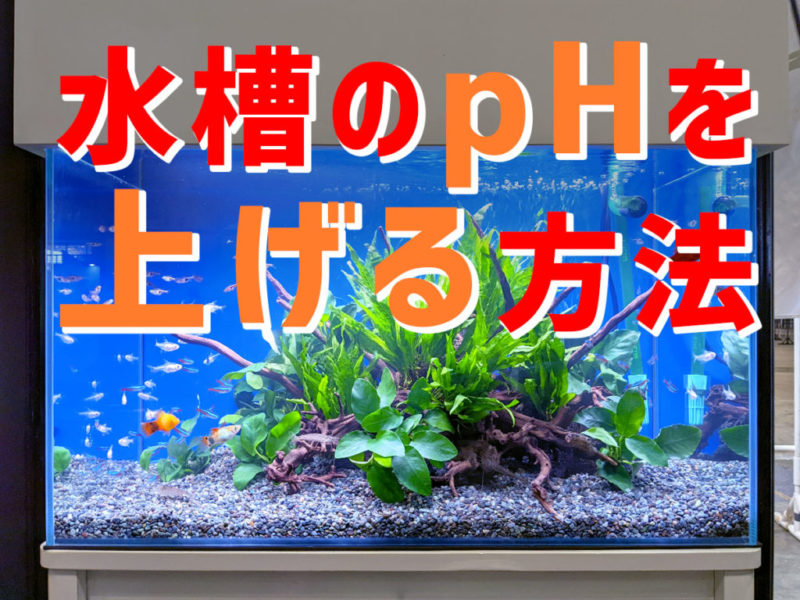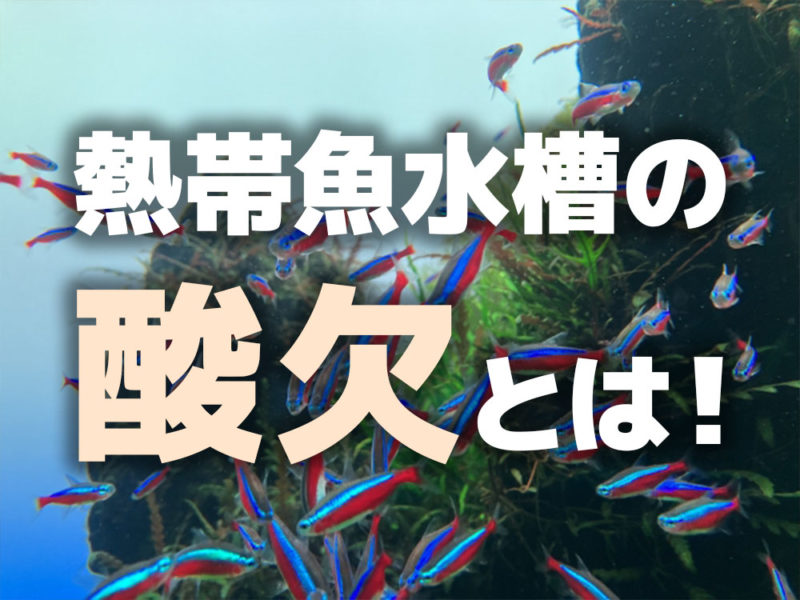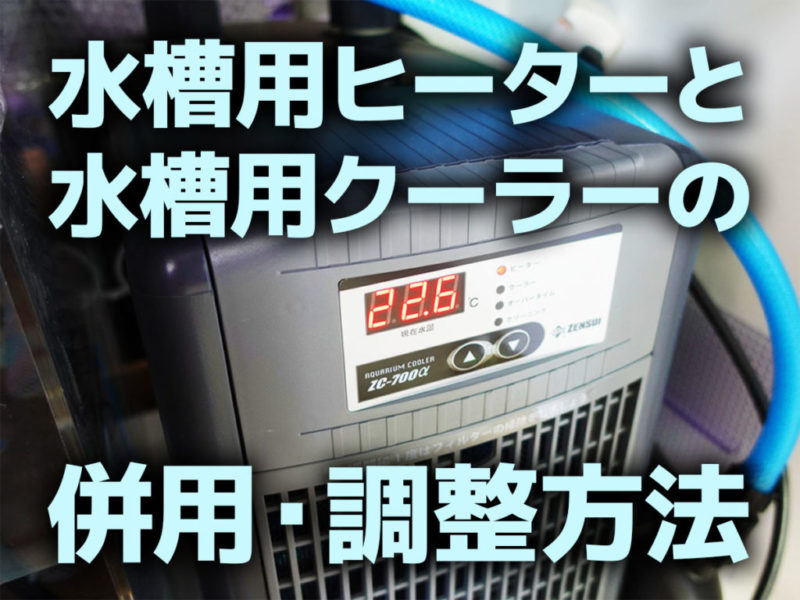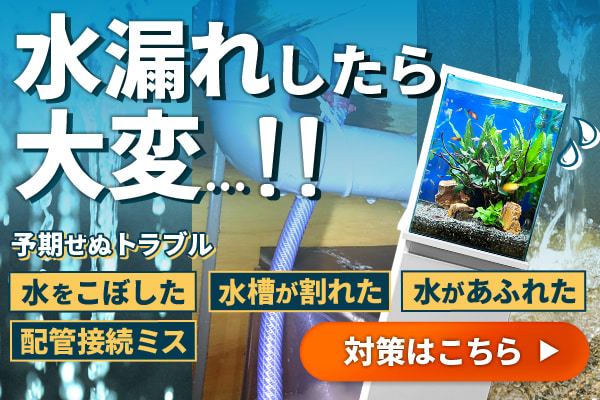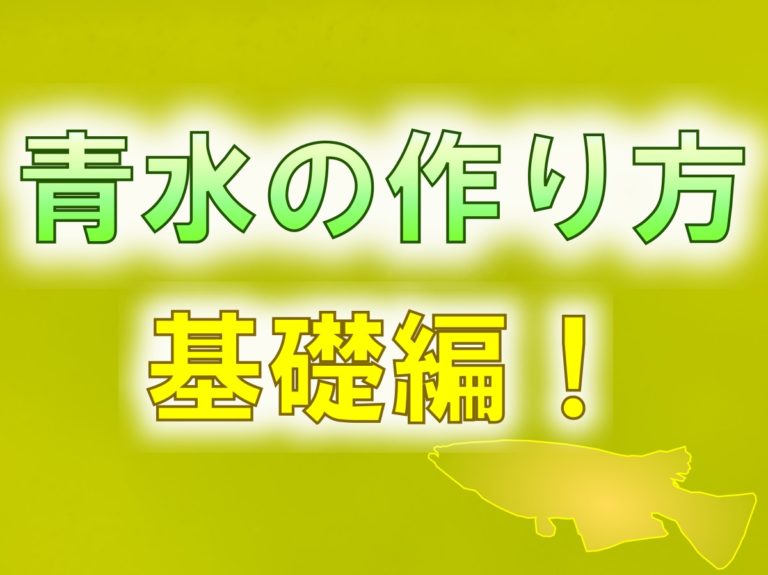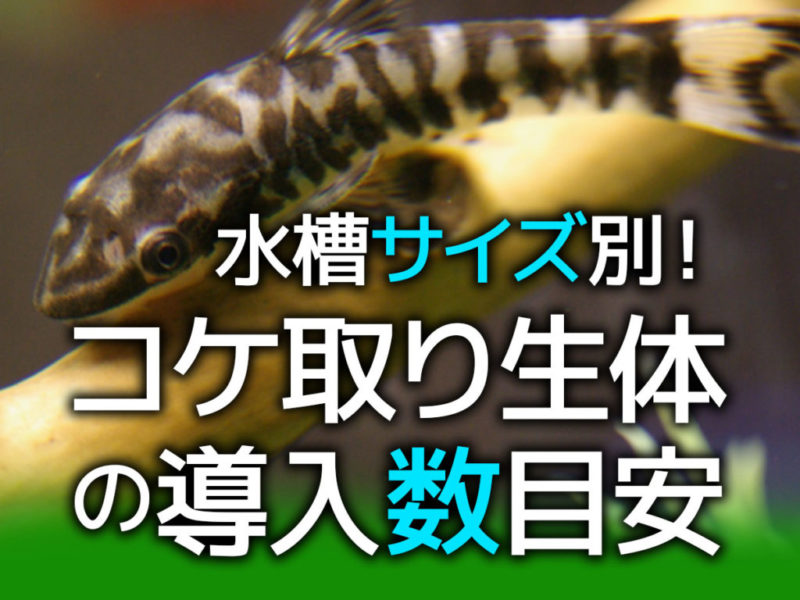貝が死ぬ原因とは!餓死する?アクアリウムで貝を長生きさせる方法

投稿日:2025.06.21|
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
石巻貝やヒメタニシ、フネアマ貝にピンクラムズホーンなどの貝類は、コケを食べてきれいにしてくれるお掃除能力はもちろん、見た目が個性的なことから低層の彩りとして取り入れる方も多い人気の生き物です。
しかし、水槽のサポート役であるがゆえにメインの生体に比べて管理がおろそかになりやすく、気づいたら死んでしまっていたという悲しい事態になってしまうことも少なくありません。
様々な水槽に導入されているため貝類は丈夫というイメージをお持ちかもしれませんが、実は繊細な面があり、長く飼育していくには相応の管理が必要です。
特に水温の変化や餌の不足で命を落としてしまうことが多いため、貝類にもしっかり気を配りましょう。
今回のコラムでは、貝が死んでしまう主な原因と、長生きさせるための具体的な飼育ポイントを解説します。
目次
プロアクアリストたちの意見をもとに貝が死ぬ原因と長生きのコツを解説

このコラムは、東京アクアガーデンスタッフであるプロのアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
水槽のお掃除役として様々な水槽で飼育されている貝類を長生きさせるには、餌や水質、水温などに気を配りましょう。
ここでは、実務経験から得た知識をもとに、貝が死ぬ原因と長生きのコツを解説します。
貝が死ぬ原因5つ

貝を入れてもすぐに死んでしまう、という時は水質や水温など水槽内の環境に何か原因があると考えられます。
ここでは、貝が死んでしまう主な原因を5つ解説します。
貝が長生きできる環境を整えるためには、まず原因を特定する必要があるでしょう。
ご自分の水槽で心当たりが無いか、照らし合わせながらご覧ください。
餓死
貝の死因で一番多いのが、餓死です。
コケ取り目的で貝類を導入していると、コケや魚の餌の食べ残しを積極的に食べてもらうために、貝用に餌を与えていないケースが見受けられます。
確かに水槽内にコケや汚れがある間は、餌やりをしなくても問題なことが多いですが、コケも無限に湧いてくるわけではないため、尽きてしまうと貝の餌が不足して死んでしまうことがあるのです。
特にコケ取り生体の数が多いと、コケが奪い合いになって小さな貝が命を落としてしまいやすくなります。
さらに貝が死んでしまったことにすぐに気が付いて取り除ければよいですが、レイアウトの陰などで死骸に気づかず放置してしまうと水質を悪化させる原因にもなるので注意しましょう。
水質が合っていない
特に水草水槽や熱帯魚水槽の貝類の死因に多いのが、水質です。
意外に思われるかもしれませんが貝類は魚よりも水質に敏感。巻貝は一般的に中性~弱アルカリ性の水質が得意なのですが、先にあげた水槽では弱酸性に水質を保っていることが多いため、水質が合わずに貝類が体調を崩してしまうのです。
また、貝は体の構造上、カルシウムなどのミネラルが不足すると殻が薄くなって、病気にかかりやすくなります。
水草水槽やビオトープはどうしてもミネラルが不足しがちで、貝類が長生きしづらいです。
他の生体に攻撃されている
貝は基本的に動きが遅く、防御力も高くありません。
そのため、金魚やベタなどの好奇心旺盛な魚につつかれたりちょっかいを掛けられたりすると、殻に閉じこもりっぱなしになって弱ってしまうことがあります。
巻貝の場合、体調を崩すと、
- 水面近くを漂うよう
- ガラス面に貼りつかなくなる
といった異変がみられることが多いので、怪しいと思ったらほかの生体との相性を見直し、状況によっては隔離することを検討しましょう。
酸欠
当然ですが、貝も酸素を必要とする生き物です。水槽に対して生き物の数が多すぎると、酸欠になり死んでしまう可能性があります。
特にマシジミなどの二枚貝は酸欠に弱い傾向があるので注意が必要です。
マシジミやヒメタニシなどは、酸欠になると水面近くでしきりに口を動かす過呼吸のような行動を見せることがあるため、このような症状が見られたら、エアレーションや生体の数を減らすといった対策を行ってください。
また夏場は、水温上昇が酸欠の原因となるため、水温も合わせて確認すると安心です。
水温が高い・低い
同じ貝類でも種類によって適応できる水温に違いがあります。
例えばヒメタニシは適応できる水温が5~28℃とかなり広く、水温が下がると冬眠して越冬することができますが、フネアマ貝は15~28℃が適温です。このような寒さに弱い貝は水温15℃を下回ると動かなくなり、最悪の場合そのまま命を落としてしまうこともあります。
また、28℃以上の高水温も貝にとっては大きなストレスになるので、夏場は貝類がダメージを受けやすいです。
水槽用ヒーターや水槽用クーラー、冷却ファンなどを活用して、一年を通して快適な水温に維持しましょう。
貝を長生きさせる方法

ここからは、貝を長生きさせる方法を解説します。
ご紹介してきた通り貝が死んでしまうのには、何かしらの原因が潜んでいます。
原因を特定したら、状況を改善する対策を行いましょう。
貝が食べる餌を確保する
餓死を防ぐには貝の餌を自然発生したコケに頼るのではなく、コケが無くなっても餌が食べられる環境を整えることが大切です。
例えばプランクトンを好んで食べるヒメタニシならば、グリーンウォーターやゾウリムシを用意しておき、コケが不足してきたらそれらを与えて餓死を防ぎます。
最近は貝用の人工餌も販売されているので、人工餌に餌付く種類ならばそちらを与えるのもおすすめです。
石巻貝やフネアマ貝のようにコケ以外のものにあまり興味を示さない貝の場合は、本水槽とは別にあえてコケを繁茂させた飼育容器を用意しておき、本水槽のコケが無くなったら一時的にコケがある飼育容器に移してあげると、餓死を予防できるでしょう。
また、貝類にこだわりが無いのならば、ヌマエビやオトシンクルスといった人工餌も食べてくれるお掃除生体に切り替えるのも一つの方法です。
カキガラを使用する
貝を健康的に飼育するには、水質を中性付近で安定させることと、水中にミネラル分を供給することが大切です。
そこでおすすめなのがカキガラ。
底砂やろ過フィルターにカキガラを仕込むと、水中にカルシウムやミネラルが溶けだして貝の殻を丈夫にしてくれます。また水質を中性~弱アルカリ性に保ちやすくなるのもぴったりです。
ただし、弱酸性を好む水草や魚を飼っている場合には水質の変化が悪影響となる可能性があるため、使用する際は飼育生体と水質のバランスを慎重に見極めましょう。
弱酸性環境では、貝以外のお掃除生体を飼育することも検討してみてください。
貝の飼育数を控えめにする
貝類は想像以上に食欲旺盛な生き物です。
水槽の大きさに対して飼育数が多すぎると、あっという間に水槽内のコケを食べつくして、餓死してしまうため、最初の導入数は少な目を心がけましょう。
目安としては、30cmキューブ水槽なら石巻貝1~2匹程度、45cm水槽でも3匹ほどで十分です。特に新しく立ち上げたばかり水槽や、コケの少ない環境ではさらに飼育数を絞っても問題ありません。
貝以外にもコケを食べる生体がいる場合も同様に、飼育数は控えめに全体のバランスを見ながら調整してください。
まとめ:貝が死ぬ原因とは!餓死する?アクアリウムで貝を長生きさせる方法

貝が死んでしまう原因と長生きさせる方法を解説しました。
水槽のコケ取り役として重宝される貝ですが、魚と同じ感覚で飼ってしまうとすぐに死んでしまうことがあります。
貝類が死んでしまう主な原因である餓死や水質の不適合、酸欠などは、貝の特性を理解していなかったことで起こる現象です。
なんとなく、コケ取り生体=世話をしなくても大丈夫と思ってしまいがちですが、生き物を飼育している以上、貝類にもしっかり目を向けてあげましょう。
貝類を長生きさせるには、コケ以外の餌や貝類の好むミネラル分が豊富な弱アルカリ性の水質を用意してあげるのが効果的です。
また飼育数は常に少な目を意識して、餌不足に陥らないように注意してください。
のんびりと動く貝は見ていると意外と可愛らしいものです。この記事を参考に、貝を健康的に長生きさせてあげてください。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。



 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談
お悩み相談