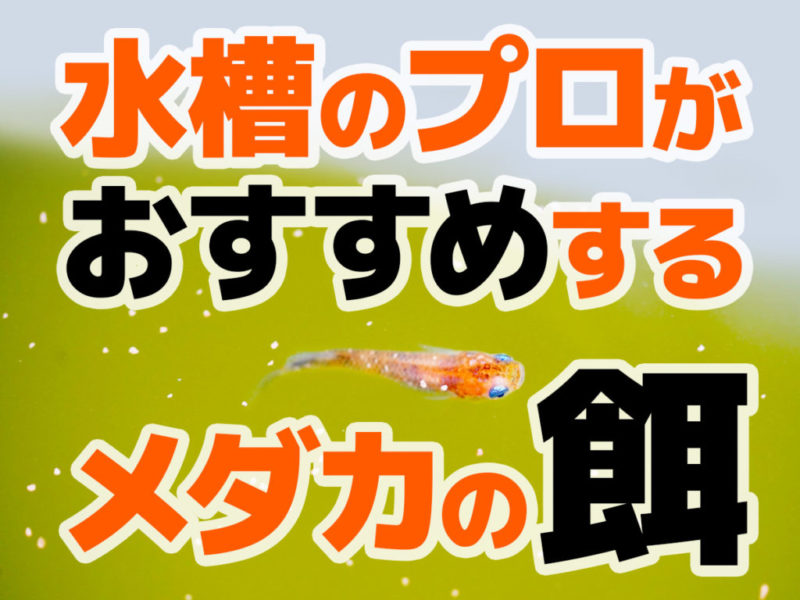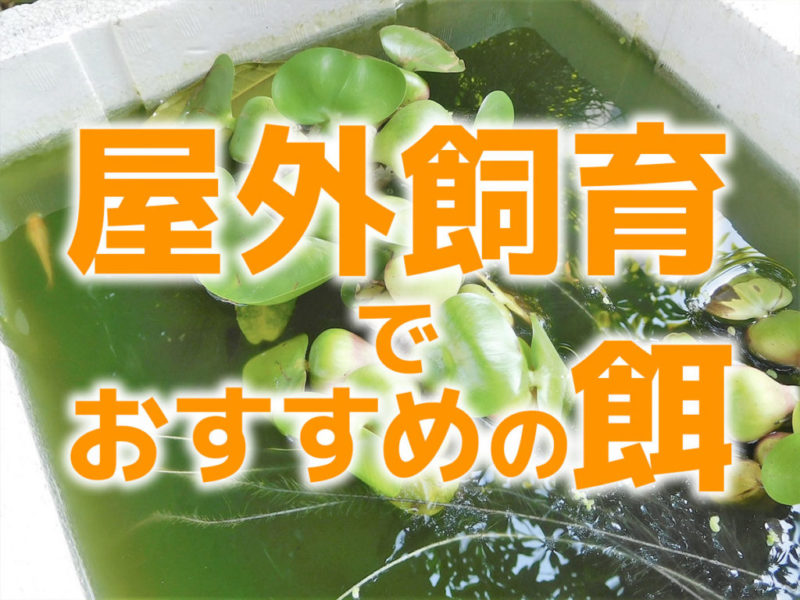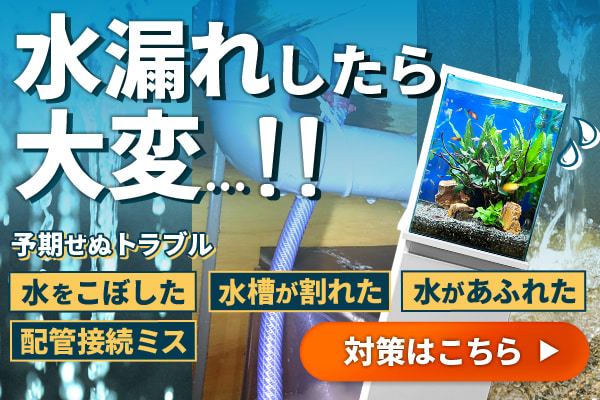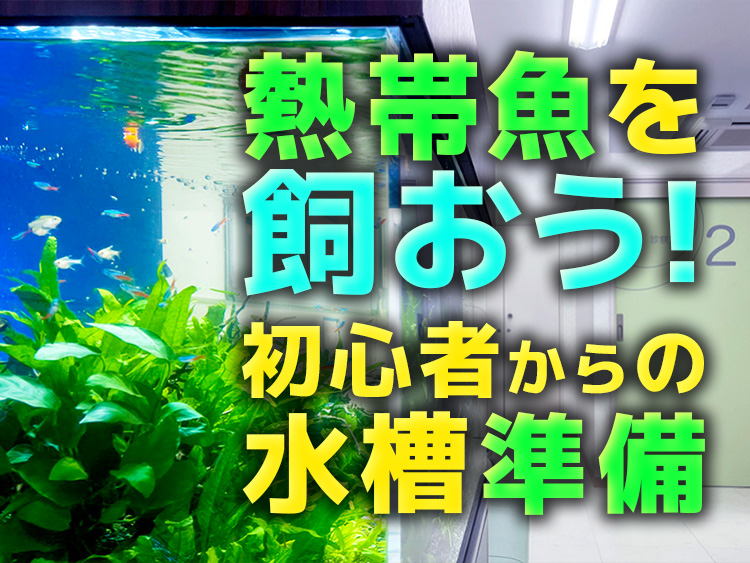アカヒレの餌とは!おすすめの餌や与え方まで飼育成功へのポイント

投稿日:2023.10.19|
コラムでは各社アフィリエイトプログラムを利用した商品広告を掲載しています。
アカヒレは、アクアリウムの入門種という位置づけで長年親しまれている小型観賞魚です。
「飼育が簡単な魚」として有名ですが、生き物ですから調子を崩してしまうこともあります。
アカヒレ飼育で失敗しやすいのは『餌の与え方』です。
アカヒレは人工飼料だけでなく、インフゾリアなどの微生物も好んで食べるため、実はこまめな餌やりが必要ありません。
かわいいので、つい餌を与えすぎてしまうと、消化不良等のトラブルが起きてしまうことがあります。
これは、アカヒレに限らず他の熱帯魚・観賞魚も同じです。
このコラムでは、アクアリウム初心者向けに、アカヒレの給餌について解説します。
「どうやって魚の給餌頻度を決めたらいいのか?」という疑問のヒントになれば幸いです。
目次
プロアクアリストの意見をもとにアカヒレの餌やりについて解説

このコラムは、東京アクアガーデンに在籍するプロアクアリストたちの意見をもとに作成しています。
アカヒレは『コッピー』という流通名でも知られているなど、ボトルなどの小さな容器でも飼育できる魚種です。
それほどに丈夫ですが、長期飼育となると意外に難しいこともあります。
このコラムでは、アカヒレの餌やりや飼育ポイントをご紹介します。
アカヒレが好む餌とは
まずは、アカヒレが好む餌の種類についてご紹介します。
アカヒレは雑食性の魚なので、さまざまな餌を食べます。
口に入るサイズなら小粒の人工飼料からブラインシュリンプなどの生餌まで食べるため、餌に困ることはないでしょう。
しかし、食べるからといってどんどん与えていては、アカヒレが弱る原因になります。
あくまでも「適量」であることが肝心です。
まずは、アカヒレが特に食べやすい・消化しやすい餌について解説します。
アカヒレに最適な餌の種類

アカヒレの餌は、浮上性か沈降性のものが向いています。
水面近くに餌がある方が口に入れやすく、素早く沈んでしまう沈下性の餌とは相性が良くないです。
餌を選ぶ際は、成分や粒の大きさ、沈下速度などに注意して選びましょう。
おおよそ、沈む速さは以下のような順番です。
- 浮上性:浮いている時間が長い餌。『キョーリン メダカの舞』『キョーリン メダカプロス』など
- 沈降性:ゆっくりと沈んでいく餌。『テトラ プランクトン』『テトラ カラシン ベーシック』など
- 沈下性:すぐに沈む餌。『テトラ ウエハーミニミックス』『ニチドウ メディ コリドラス』など
食いつきやすさにさえ気を付ければ、餌自体は比較的なんでも食べます。
熱帯魚のエサ以外では、メダカのエサがおすすめです。
人工飼料
人工飼料は栄養バランスが良く、安心して与えることができます。
また、保存が簡単で与えやすい点も、便利でしょう。
熱帯魚用の小型フレークや顆粒、金魚やメダカ用の人工飼料のものが適しています。
人工飼料を与える際は、前述の沈む速度以外に、粒のサイズを確認して選ぶことが大切です。
ごく小さな粒を選び、少量を2~3日に1回与えましょう。
食べ残しは水質の悪化を招くため、取り除きます。
特に、アカヒレはボトルなど小さな容器でも飼育することが多いので、水が汚れやすくなってしまうのは問題です。
1~2分以内に食べくれる程度の量にしましょう。
生餌
アカヒレは生餌も好んで食べます。
よく食べるものとしてミジンコや冷凍赤虫、ブラインシュリンプなどが挙げられますが、生餌は人工飼料よりも水を汚しやすいため、適度に与えるようにします。
ビオトープ飼育などで、活きたミジンコを餌にする場合には問題ないのですが、冷凍餌を与える場合は残ったものはスポイトなどで取り除きましょう。
冷凍餌からはどうしても解凍時に汁がでます。それが飼育水を汚しやすいのです。
ちなみに乾燥赤虫も食べますが、栄養価は冷凍のほうが高いです。
アカヒレの給餌方法!与えないほうが良い場合もある?

アカヒレに餌を与える際には、いくつかのポイントを押さえることが大切です。
アカヒレが健康的に育つように工夫しましょう。
体の大きさによる餌の量と回数
餌の量は、アカヒレの体調や成長に大きく影響します。
過剰な給餌は水質を悪化させ、病気になる確率を上げてしまいます。
また、成魚の場合は2~3日に1回程度ですが、これはあくまでも「目安」です。
お腹の膨らみ具合などを確認しながら随時調整しましょう。
アカヒレ稚魚には、メダカ稚魚用(パウダータイプ)のエサを与えるのが良いです。

ちなみに、アカヒレは餌を控えめにしたほうが体色が濃くなる傾向があります。
また、飼育容器内に自然発生するインフゾリアやプランクトンもよく食べるので、餓死することはほぼないとさえ言われるほどです。
その点からも、少量の給餌がおすすめでしょう。
飼育環境による餌の調整

魚は、飼育水の水温がそのまま体のコンディションに反映されます。
比較的低水温に強いアカヒレも例外ではなく、寒い季節は給餌量を減らす必要があります。
水温が低い冬の管理
屋外飼育の給餌は、11月までは2~3日に1回程度が目安となります。
11月下旬ごろを過ぎたら、あまり与えなくても良いです。
また、屋外飼育では氷が張る時期になると、冬眠のような状態になります。
冬眠した場合は再び春になるまで餌を与えず足し水などをそっと行いながら様子を見守りましょう。
しかし、アカヒレにとって冬眠は、メダカとは異なり負担になるようです。
そのため、なるべく冬眠を避けるように、秋のうちに発泡スチロールの飼育容器に移し替えるのがおすすめです。
室内飼育の場合は冬眠しませんが、水槽用ヒーターを使用しない無加温飼育の場合は、それほど活発に動かなくなるので、餌の頻度と量を落とします。
そうすることで消化不良を防いでいきましょう。
水温が高い春から夏の管理
春から夏のアカヒレの飼育では、水温が高くなることで活動量が増え、食欲も旺盛になります。
この時期は、飼育水温が適切であれば、2日に1回程度、餌を与えることもできます。
とはいえ、食べ残しが出てしまうのは良くありません。
特に、動物性の原料を多く含む餌や生餌の場合は、水質が悪化しやすいので十分な注意を払いましょう。
アカヒレが餌を食べない原因

アカヒレが餌を食べない、元気がないと感じる場合、いくつかの原因が考えられます。
原因1:水質が悪い
飼育水の水質が悪化している場合、アカヒレはストレスを感じたり体調を崩すなどして、餌を食べなくなることがあります。
これは、どの魚種も同じです。魚が体調を崩すほとんどの原因が、水質悪化です。
おかしいな、と思ったらまずは掃除や水換えを徹底し、ろ過フィルターの汚れなどもキレイにしましょう。
原因2:病気や寄生虫
アカヒレは丈夫な魚ですが、飼育環境が適切でないと、尾ぐされや口腐れなどの細菌感染症や寄生虫がつくことがあります。
そうした場合には症状に応じて治療を行いましょう。
- 尾ぐされ病:グリーンFゴールド顆粒
- 赤斑病:観パラD
- 白点病:ヒコサンZ
- 水カビ病:メチレンブルー など
病気の症状が出たらバケツやプラケースなどに隔離して治療します。
白点病の場合は、同じ水槽内に広がってしまうので、全匹薬浴しましょう。
まとめ:アカヒレの餌とは!おすすめの餌や与え方まで飼育成功へのポイント

アカヒレの餌について、適切な種類や与え方、飼育環境による影響などを解説しました。
アカヒレの健康を維持するためには、適切な餌の選び方や与え方が大切です。
水質にも注意を払い、アカヒレが元気に過ごせる環境作りに努めましょう。
これは、アカヒレだけでなくすべての魚飼育の基本です。
初心者向けの丈夫な魚であるアカヒレは、アクアリウムの基本を学ぶのに最適な魚です。
アカヒレに関する知識を活かし、さまざまな魚飼育に挑戦してみましょう。
お問い合わせ
水槽や機材、熱帯魚のレンタル・設置・メンテナンスがセットになった水槽レンタル・リースサービス、
お手持ちの水槽をプロのアクアリストがメンテナンスしてくれる水槽メンテナンスサービス、
水槽リニューアルサービスや水槽引っ越しサービスなど様々なサービスがございます。
お見積りは無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。


 水槽メンテナンス
水槽メンテナンス 水槽レイアウト
水槽レイアウト アクアリウムテクニック
アクアリウムテクニック 水槽レンタルサービス・水槽リースサービス
水槽レンタルサービス・水槽リースサービス メディア掲載
メディア掲載 水槽器具類
水槽器具類 ろ過フィルター
ろ過フィルター 水槽用照明
水槽用照明 水草
水草 熱帯魚飼育
熱帯魚飼育 金魚飼育
金魚飼育 メダカ飼育
メダカ飼育 エビ飼育
エビ飼育 その他の生体飼育
その他の生体飼育 水槽用ヒーター
水槽用ヒーター 水槽メンテナンス道具
水槽メンテナンス道具 水槽・飼育トラブル
水槽・飼育トラブル お魚図鑑
お魚図鑑 水草図鑑
水草図鑑 メダカ図鑑
メダカ図鑑 お悩み相談
お悩み相談